

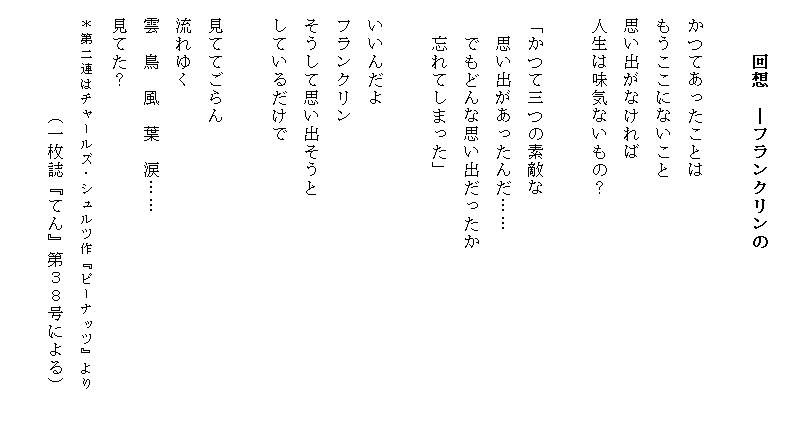
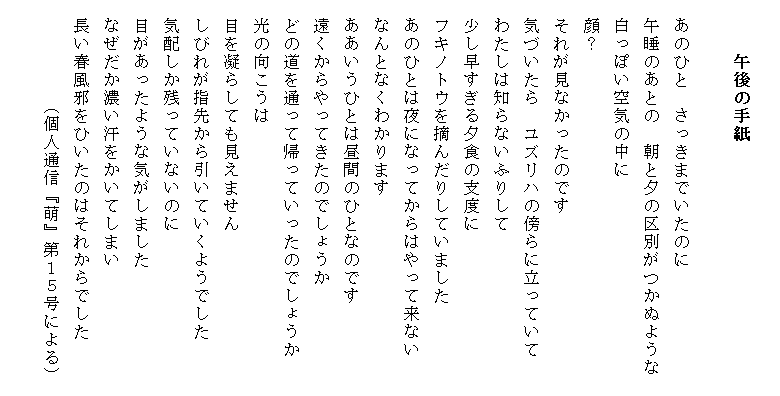
ここには、伊藤氏によって新たに見出された世界がある。その世界が、無駄のない、洗練された詩的表現によって、リアリティが確保されながら、みごとに表現されている。こういうことは、めったにない出来事である。一連の詩は、「異界」の広がりにそのままつながっているような「日常」の“ゆらぎ”や“奥行き”を実感させる作品として、「日本の現代詩」の中に位置づけられるべきものだ、と考える。
最後になるが、大場義宏氏(山形市在住)の詩を取り上げたい。筆者が、ここで大場氏の詩に言及しようと思ったのは、次の詩を読んだからである。
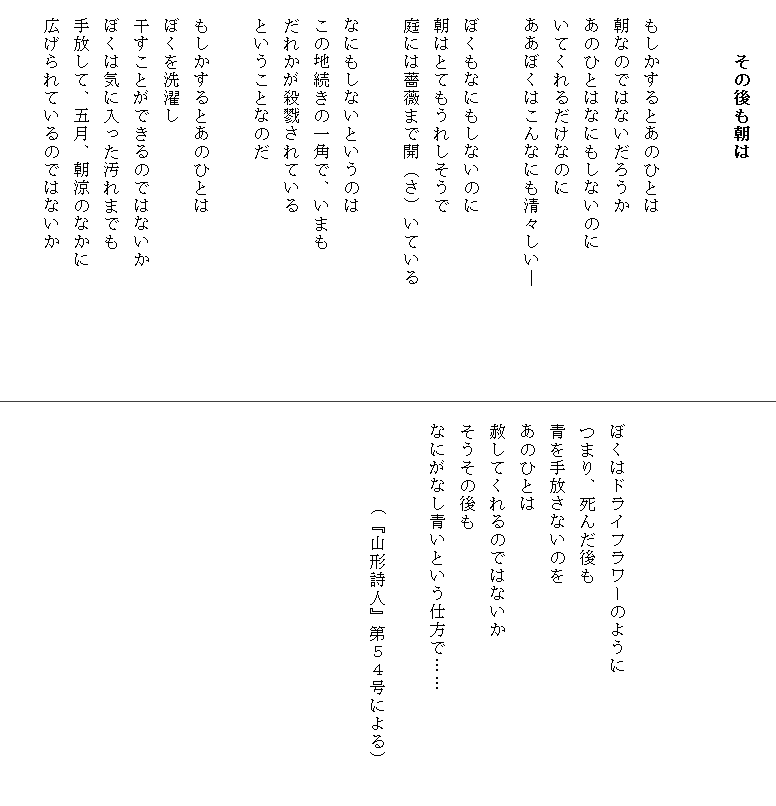
第二連までを読んで想起される、透明な、朝の空間の広がりに、突如、第三連の先鋭な世界認識が挿入されて、はっとさせられる。第四連の諧謔は、第一連・第二連の清澄さの、いわば裏返しとなっており、その諧謔的な発想は最終連の切なさを感じさせる表現につながって帰結する。「あのひと」と「朝」が一体化されて表現された清々しく透明な世界の広がりのうちに、「なにもしない」「気に入った汚れ」「死んだ後も/青を手放さない」といった、“厳しさ”と“こだわり”を感じさせる自己認識と、第三連の世界認識とが入り込んで、読む者に、感じさせ、思わせ、考えさせる。大場氏の詩の中には、暗示性と多義性に富んだ言葉によって、世界や人間、自己のありようについての、鋭く、視野の広い認識が、魅力的なイメージの展開、跳躍を伴って表現されたものがあり、この詩もその一つである(ほかに、『山形詩人』第45号に発表された「柳」などがある)。こうした作品がこの先も作られ続けるならば、大場氏の詩もまた「日本の現代詩」の中にしっかりと位置づけられるものになるのだろう、と思っている。
以上、三人の詩人の詩を紹介してこの文章を終えることになるが、それでも、山形における「現代詩」の実りが、決して乏しいものではないことを、感じとってもらうことができたのではないだろうか。
最後に、どうしてもことわっておかなければならないことがある。それは、筆者の狭い視野の中に入っていて、しかも、筆者がその作品の魅力を理解(実感)することができていると判断されるものでなければ、この文章で取り上げることはできなかった、ということである。言うまでもないことではあるが、すぐれた詩であっても筆者の視野と理解力の範囲の外にあるものは、取り上げることができなかった。また、過去の作品によって全国的な評価がすでに定着していると判断される詩人については、取り上げる対象からあらかじめ外した。ともに、おゆるしいただきたい。
(平塚 志信)