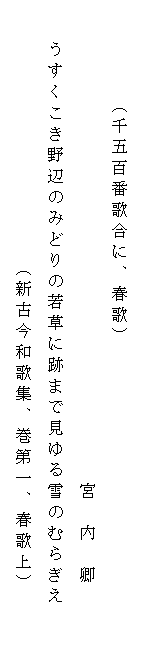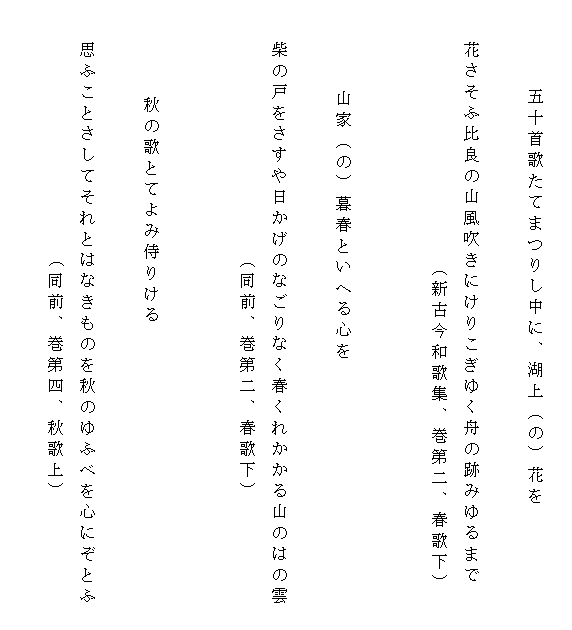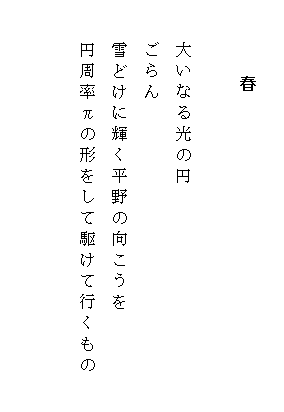2月から3月にかけての時期は、「冬から春への移りゆきの時期」。「暦」をたどると、「立春」が2月4日ごろ、「雨水(うすい)」(雨がぬるみ、草木が芽ぐむころ)が2月19日ごろ、「啓蟄(けいちつ)」(冬ごもりしていた虫が地上に姿を表すころ)が3月6日ごろ、そして「春分」が3月21日ごろ。まさに、2月から3月にかけてが、冬から春への移りゆきの過程となっています。
さて、「冬から春への移りゆき」を表現した詩としてまっ先に思い浮かぶのは、私の場合、次の和歌です。
「あるところは薄くあるところは濃くなっている野の緑の若草の生え具合によって、まだらに(あるところは遅くあるところは早く)消えていった雪の消え方までもが見えることだ」という内容の歌です。「若草」(生えてまだ間もない草)の生え具合から、「雪のむらぎえ」が意識されるわけですから、雪が消えてまだ間もない、春の初めの歌と考えられます。「うすくこき」若草の生え具合が、「むらぎえ」に消えていった雪の消え方を表しているという、一つの発見によって、春と冬との間に、いわば架け橋がかかって、春と冬とが一緒に意識されることとなっており、そこに「冬から春への移りゆき」が感じられます。
「よくものを見る目と感じやすい心」を大切にすることが、詩を作る上での基本であると、私は考えていますが、宮内卿(くないきょう)のこの和歌は、まさにその二つがはたらくことによって成り立った歌であると思われます。
作者の「宮内卿」は、新古今和歌集編纂の命を下した後鳥羽院(1180~1239)に仕える女房であった女性です(「後鳥羽院宮内卿」とも呼ばれます)。その歌才を後鳥羽院に愛された人で、南北朝時代の歴史物語「増鏡(ますかがみ)」(第一、おどろのした)では、「まだいと若き齢(よはひ)にて、そこひもなく深き心ばえをのみ詠みし」と評されており、千五百番歌合(せんごひゃくばんうたあわせ。後鳥羽院が主催した、史上最大規模の歌合。三十人が百首ずつ歌を詠み、計三千首の歌を、左右に分けて判を下そうとした)に際して後鳥羽院から「こたみは、みな世に許(ゆ)りされたる古き道の者どもなり。宮内はまだしかるべけれど、けしうはあらずとみゆればなん。かまへてまろが面(おもて)起こすばかり、よき歌つかうまつれよ」(今度の歌合に参加するのは、みな世の中で歌の名人として認められている、長年歌道に精進してきた者たちである。そなたはまだそこまで達しているわけではないけれども、参加させてもおかしくはないと思われるので、特に参加させるのだ。きっと(そなたを抜擢した)自分の面目が立つほどに、よい歌を詠んでくれよ)と声をかけられたことが紹介されています。「増鏡」では、「さて、その御百首の歌いづれもとりどりなる中に」のことばに続けて、「うすくこき」の歌一首が取り上げられ、「草の緑の濃き薄き色にて、去年(こぞ)のふる雪の遅く疾(と)く消えけるほどを、おしはかりたる心ばへなど、まだしからん人は、いと思ひよりがたくや」と賞賛されています。続けて、「この人、年つもるまであらましかば、げにいかばかり、目に見えぬ鬼神をも動かしなましに、若くて失(う)せにし、いといとをしくあたらしくなん」と記されています。正徹(しょうてつ。室町時代前期の歌人)の歌論書「正徹物語」(下、一〇三)には、「宮内卿は二十よりうちになくなりしかば」の記述があり、十代で亡くなったのか二十歳を越えて亡くなったのかははっきりしないようですが、二十歳前後で亡くなったことは確かなようです(ということは、「うすくこき」の歌を詠んだとき、宮内卿は十代だった可能性があります)。
「正徹物語」では、「三十七にて薨じ給ひし」後京極摂政藤原良経とともに、宮内卿を、高い境地に至るのに長期間の修行を必要としなかった「生得の上手」として取り上げています。先の「増鏡」の記述と合わせて考えると、没後(没年は未詳ですが、1205年ごろと考えられているようです)百年以上の時を経て、なお、宮内卿は、「夭折した天才歌人」ととらえられていたことがわかります。
宮内卿と同時代に生きた鴨長明(1155~1216)は、歌論書「無名抄(むみょうしょう)」(俊成卿女宮内卿両人歌読替事)の中で、宮内卿の死について、「あまり歌を深く案じて病(やまひ)になりて」一度死にかけ、そのため父親に「何事も身のありての上の事にこそ。かくしも病になるまでは、いかに案じ給ふぞ」といさめられながら、しかし、父のいさめを聞き入れることなく、「終に命もなくてやみにしは、そのつもりにや有りけん」と記しています。「歌作の魅力にとりつかれ、そのために夭折した天才歌人」という、数々の近代の芸術家にも通じる人物像が浮かんできます。
ちなみに、長明が「無名抄」で「今の御代には、俊成卿女と聞ゆる人、宮内卿、この二人ぞ昔にも恥ぢぬ上手どもなりける」と述べた、俊成卿女は、八十歳を越えてなお存命であったことがわかっています。宮内卿と俊成卿女、同じく歌才を高く評価されながら、対照的な人生を送った、この二人の女性を思うと、二人を主人公とする小説があってもよいのではないか、などと思われます。
和歌の歴史の上で、それまでにない「感性の時代」となっている「新古今の時代」においても、宮内卿の歌の中には、目立ってみずみずしい感性のはたらきの感じられる歌があります。次の3首も、そうです。
「花さそうふ」の歌は、湖一面に散り敷いた花びらを舟が分けてゆく情景が、鮮烈に目に浮かびます。その情景には、「比良(ひら)」(近江国の比良山)という歌枕を離れても失われない、情景としての魅力があります。「柴の戸を」の歌からは、戸を閉ざし、春の日差しをさえぎってしまったあと、春の日の名残としては、ただ山のはの雲を見上げるしかなくなってしまった、そういう時間のものさみしさ、暮れてゆく春の一日へのいとおしさが、実感として伝わってきます。「思ふこと」の歌は、「特に気がかりなことがあるわけではないのに。秋の夕方にはどうしてこんなに気持ちがかげってしまうのか、自分の心に問いかけてしまう。」といった意味でしょうか。大伴家持の「うらうらに照れる春日に雲雀あがり心悲しもひとりし思へば」(万葉集、巻十九)と、時代は違うものの、特別な理由がなくとも悲しみを感じてしまう、心の感傷的な動きをとらえた歌として、春・秋で好一対をなすと言ってもよいような歌と思います。
次は、「春への移りゆき」を内容とする、私自身の詩です。習作と言うべき作品ですが。