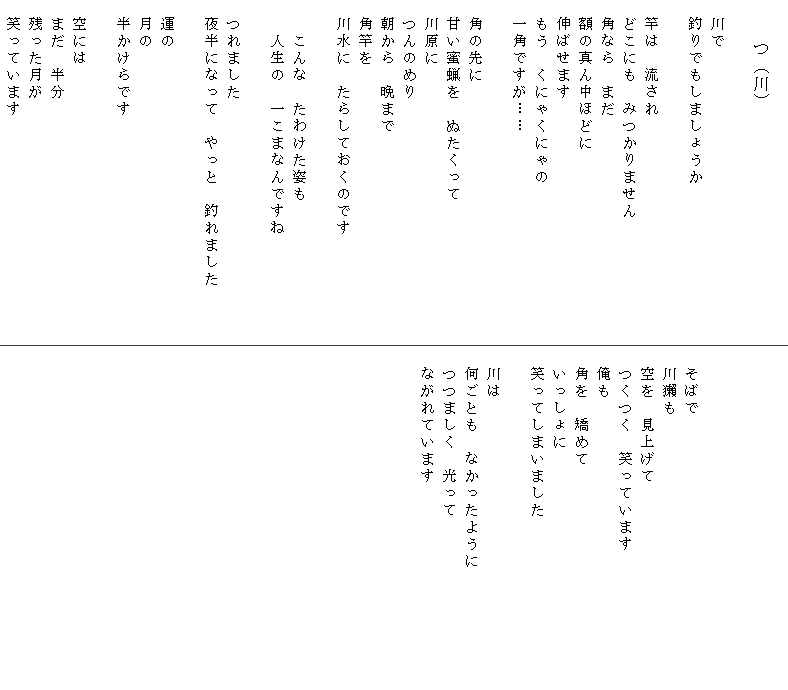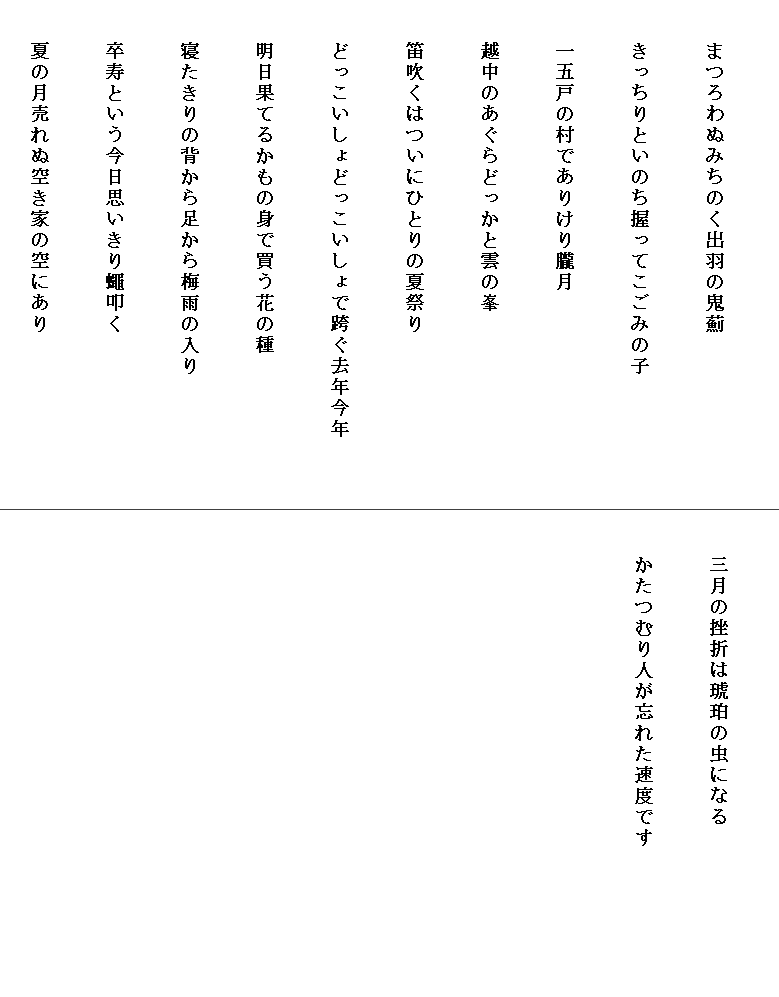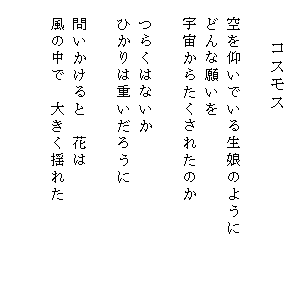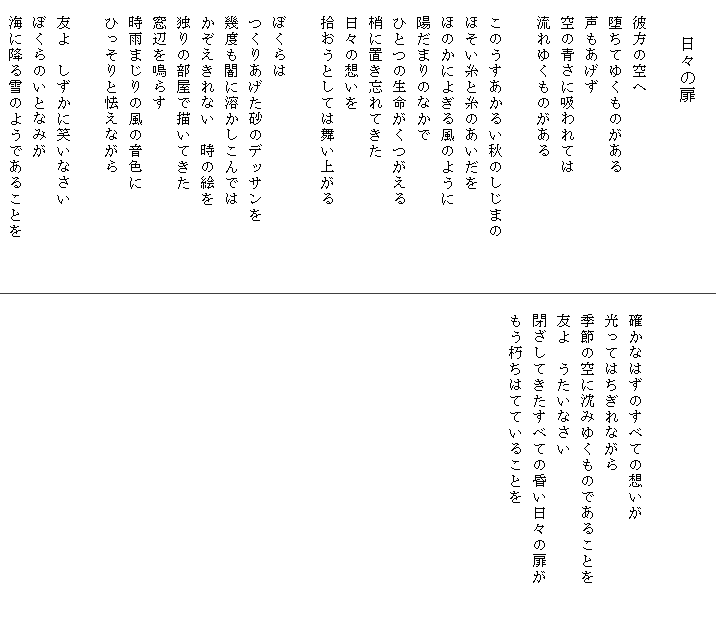詩集を読んで〈2013〉
菊地隆三詩集『いろはにほへと』(書肆山田、2013年2月5日発行)
「いろは歌」に表現された、「い・ろ・は…も・せ・す」の四十七字のひらがなに、「ん」を加えた、四十八字のひらがなをもとにして、それぞれのひらがなからの連想を、「語」のレベルで紡いで作られた、四十八編の詩が収められている。「語」のレベルで紡いで、と言うのは、例えば、「い」であれば、「いつものごとく」「いつのまにか」「いろんな」「いい」「いろいろ」「今では」「今さら」「いかんとも」「いつも」「命」「
絲」「いやさ」「犬」「いか」「いっしょに」「
縊死」といった語、つまり「い」で始まる「語」が、詩の中に散りばめられていて、作者は、そうした語をたどりながら詩想を展開していると考えられるからである。したがって、それぞれの詩には「ことば遊び」のおもしろさがあり、そのおもしろさを楽しみ、味わうことが、本詩集の大きな魅力の一つである。
もう一つの大きな魅力は、生・老・病・死の苦しみを、いわば「おかしみ」に変えてしまうような、作者の、諧謔的でかつひょうひょうとした、姿勢と語り口である(もっとも、このことは、本詩集に限ったことではなく、作者に特徴的なことではあるけれども)。満八十歳を過ぎた作者は、「あとがき」の中で、次のように言っている。「毎晩毎晩、酒は充分にうまいし、先々のことは、いくら考えてもどうにもならない。この先は、良寛さまのいう『任天真』でいくしかないであろう」。この言葉によく表われている考え方や身構えが、集中の詩にもはっきりと表現されている。
どの詩も、それぞれに読みごたえがある。「代表作」を選ぶことは、できそうにない。私にとって特に魅力的な一編を、次に引いておきたい。
ホームページを作成しているソフトの都合で、詩にルビを振ることができないので、次に、ルビの使用を示しておきたい。「川(かわ)」「角(つの)」「額(ひたい)」「川獺(かわうそ)」「矯(た)めて」。以上、( )内がルビとして振られている。
「角」があるのだから、その
主としては鬼を想像してよいだろう。とすれば、「川」は、三途の川ととってもよいのかもしれないが、その必要もないように思う。むしろ、三途の川ではなく、自然の中の川を想像した方が、この詩の情景は、少なくとも私にとっては、より魅力的である。着目しておきたいのは、一字下げて表現されている、第四連。「こんな たわけた姿も/人生の 一こまなんですね」。この二行で表現されている「人生観」。この抽象的な思念の挿入がなければ、この詩の読みごたえ(魅力)は大きく減ってしまう。そして、第六連と第七連における、「月」に「尽き」を掛けての、イメージの飛躍。第八連も、「鳥獣戯画」を想起させるおもしろさがある。作者の非凡の表われとして、特記しておきたい。
阿部宗一郎句集『出羽に青山あり』(文學の森、2013年3月27日発行)
作者は、反骨の人である。句集の書名は、「序」として置かれている巻頭句「母われを出羽に青山ありと生む」から取られている。「白河以北一山百文」という言葉に象徴される、地域観と歴史に対する反発を含んでいることは、明らかだ。「錦の御旗」にたてついた、古くは「
阿弖流為」に代表される「
蝦夷」の地であった、東北の地への蔑視と、侵略戦争及びそれに伴う悲惨な出来事につながっていく歴史に対する反発である。
句集には、「出羽」の地に生きる者としての反骨や、雪深く過疎の進む地域に暮らす者としての気迫など、「反骨の精神」が前面に出ている句が多くあり、その一方で、九十歳を過ぎてなお衰えない、生きる気力やしなやかな感性がみごとに表現された句、中には、前衛的と言ってもよいような感覚が表現された句もある。私にとって特に印象的な句を、次に引いておきたい。どの句も、それぞれ、一篇の詩として読むことのできる、それだけの表現と内容を兼ね備えた、味わい深い句であると考える。なお、ルビが振られているのは、「朧(おぼろ)月」「跨(また)ぐ」。( )内がルビである。
近江正人/詩 小野孝一/写真
『希望への祈り もがみ風景と抒情』(ウインかもがわ、2013年4月30日発行)
近江正人の詩と小野孝一の写真による、詩と写真のコラボレーションの書である。基本的に詩一篇と写真一枚を組み合わせて見開きの紙面を構成している。計三十六篇の詩(巻頭の詩「コスモス」を除けば)を、「春~生命のいぶき」「夏~風のかおり」「秋~花のいのり」「冬~雪の底から」に分類して収める。山形県最上地方の風土に基づく詩と写真を集めているが、書名に表われているように、東日本大震災をそれぞれの立場で体験した私たちが未来へと向かう、希望への祈りを込めている。また、本書に収められている近江の詩は、一部の詩を除いて、これまでに近江が上梓した六冊の詩集から選ばれており、その点で、本書は、近江の詩のアンソロジーともなっている。
最初に本書をひもといたとき、写真の美しさに息をのんだ。なんと美しい写真だろう。単に、風景をみごとにとらえた、というような写真ではない。どの写真からも、撮影者の「感性のはたらき」がはっきりと伝わってくる。優れた写真機とレンズ、写真家としての腕前(技術)、この三つがそろっていても、こういう写真は撮れない。どういう風景を、どのようにとらえるか、そうした点に、必ず「感性」がかかわってくるわけであるが、小野の「感性」は、見る者を広く共感させるだけの力をそなえたものであり、いわば普遍的な価値を写真に定着させることのできる、卓抜なものである、と私は思う。
さて、次に、写真の印象を残したままで詩を読んだ。ここで、困惑してしまった。詩の言葉が、すっと頭の中に入ってこないのである。詩の世界に入ってゆけないと言ってもよいし、言葉を読んでもイメージが広がらないと言ってもよい。これは、どうしたことだろうか…、と、そのときは困惑した。今は、その原因を説明できる。写真と詩をいっしょに味わおうとしたことがまずかったのだ。
コラボレーションと言っても、詩と写真の場合には、例えば、音楽とダンスのコラボレーションや、絵と音楽のコラボレーションのようには、いかない。詩も写真も、ともに視覚を用いるからである。写真をじっと見ながら詩を読むことはできないし、詩を集中して読みながら写真に目を向けることもできない。つまり、詩の鑑賞と写真の鑑賞を同時に行うことは、不可能である。はじめ、私は、そのことに思いが至らず、不可能なことをやろうとしていたのだと思う。せっかくのコラボレーションなのだから、写真の印象を生かして詩を読もうとし、結果的に詩を読む際に必要な意識の集中を欠いてしまっていたのだと思う。
では、本書におけるコラボレーションの試みは失敗なのか、というと、そうではない。
「同時に」鑑賞することは不可能だが、「それぞれに」鑑賞することはできる。写真は写真として、詩は詩として、別々に、鑑賞する。すると、そこには、感性の競演が成立する。近江の詩も、小野の写真も、それぞれ、一個の作品として成立しており、それぞれが集中しての鑑賞に堪えるだけのものを備えているのだ。読者は、一篇の詩について、すぐれた感性のはたらきを、二つ味わうことができる。それだけでも、コラボレーションの意義はあると言うべきだろう。
ここで、本書におけるコラボレーションについての言及を終われば、私のここまでの発言は、「コラボレーションの意義・成果を、ある意味で評価した」というようなことになるだろう。そして、ここで終わらないと、これまでの発言はいったい何だったのだと叱られそうである。
しかし、ここで終わるわけにはいかない。次のことも言っておかなければならない。そうしないと、本書におけるコラボレーションについての、私の、最終的な考えを述べないで終わってしまう。
近江の詩を集中して読んだあと、あらためて小野の写真にじっくりと目を向けてみる。すると、どうだろう。そこには、近江の詩を読む前には見えなかったものが「見える」。近江の詩が、小野の写真に、ある「奥行き」(とでも言うべき「意味」)をもたらしたのだ。そして、そのあと、もう一度近江の詩を読む。すると、どうだろう。小野の写真が、近江の詩の「背景」となって、「見える」。ここに、詩と写真のコラボレーションが、十全にその機能を発揮した、と言ってもよいのではないだろうか。
ここに至って、「あとがき」の中で近江が述べる、本書におけるコラボレーションの意図も達成されていると、私は、評価したい。近江は、次のように述べている。
「ぜひ、彼の風景にぼくの詩を添えてみたいと思った。故郷の何気ない風景の中に言葉を供え、花や雪やひかりの中で言葉が新たに発色し発酵し、より深い意味を有して新しい抒情と物語がそこから匂い立ってくるような、そんなコラボを二人で試みたつもりである」。
迂遠なもの言いとなってしまったが、おゆるしいただきたい。本書における、詩と写真のコラボレーションについての、私の体験と感想を、率直かつ丁寧につづったつもりである。本書をひもといた人が、みな、私と同じような体験をし、同じような感想をもつかどうかは、わからない。もししたら、はじめから、十全にコラボレーションを楽しみ、味わえる人もいるかもしれない。しかし、中には、私のように、はじめは「困惑」を感じる人がいるかもしれない。そういう人にとっては、ここまで書いてきたことが、あるいは役に立つこともあるかもしれないと思い、書きつづっておく次第である。
さて、長くなってしまったが、近江の詩に言及しないわけにはいかない。特に魅力ある詩が、いくつも収められているのだから。
本書の巻頭に置かれた詩である。本書全体を代表するような、特に思いを託された詩と考えてよいだろう。
短い詩であるが、表現されていることがらは、単純でなく、たいへんに豊かで、大きい。
第一連。「生娘」も「コスモス」も、「宇宙から」「願いを」「たくされた」存在としてとらえられている。そのとらえ方の、視点の大きさと説得力の強さを思うべきだろう。
第二連。「ひかり」が「重い」と感じるのは、普通の感じ方ではない。こういう、普通でなく、しかも説得力のある表現に出会えることが、詩を読むことの醍醐味である。なぜ「つら」いのか、なぜ「ひかり」が「重い」のか。もちろん、「宇宙からたくされた」「願い」とのかかわりで考えるべきだろう。その「願い」がどういうものであれ、それは、“生きる”ことによって、あるいは“生をつなぐ”ことによって実現されるものと考えられる。「ひかり」の「重」さは、「宇宙から」「願い」を「たくされ」て“生きる”ことの、そして“生をつないでいく”ことの、重さと考えられる。「願い」がどういう内容のものであるかは、読者がそれぞれに思いをはせればよい。
第三連。「花」が「大きく揺れた」ようすが、第二連での「つらくはないか」という「問いかけ」に対する、何らかの「こたえ」であるかのように、表現されている。イエスとも、ノーとも、考えられる。イエスであれば、「それは、もちろん、つらいけれど…」といったようにこたえたことになり、ノーであれば、「ありがとう、でも、別につらくはないよ」といったようにこたえたことになる。どちらかに決めたい人は、そうすればよい。「どちらともわからなかった」と受けとめてすませたい人は、そうすればよい(ちなみに、私は、「どちらともわからなかった」と受けとめてすまたい。その方が、「表現に即している」と考えるから)。
このように、この詩に表現されているのは、はかなく、頼りない存在ではあっても、「宇宙からたくされた」「願い」をかかえて“生き”、“生をつないでいく”ものの姿であって、その姿に、近江は、本書全体を貫く「希望への祈り」を託したのだと、私は考える。
アンソロジーとなっていることもあり、「樹の歩み」「日々の扉」「雪おぼれ」といった、傑出した作品が収められている。中から、近江の処女詩集『日々の扉』のタイトル詩である、「日々の扉」を、引いておきたい(以上、敬称を省略させていただきました)。