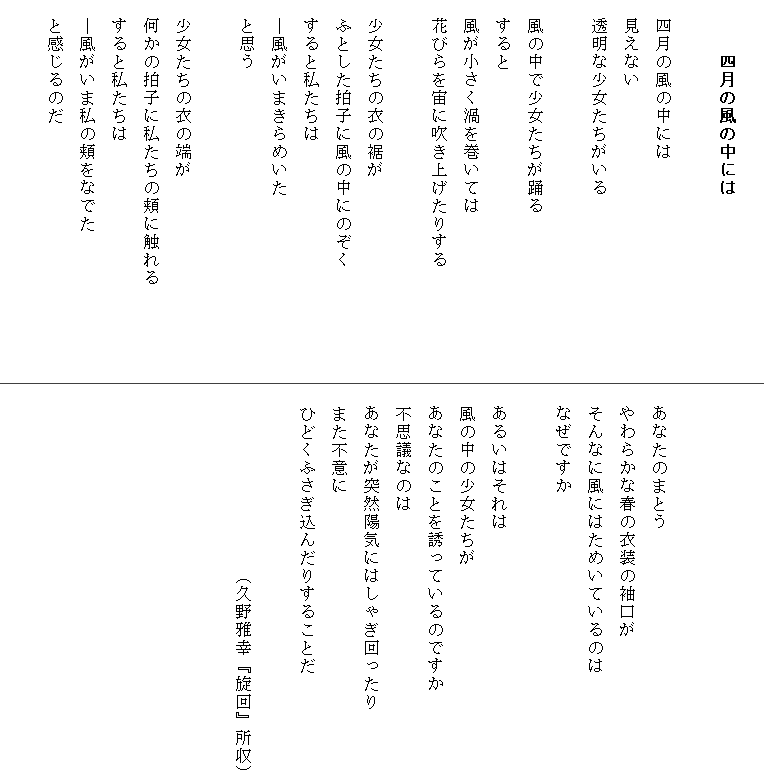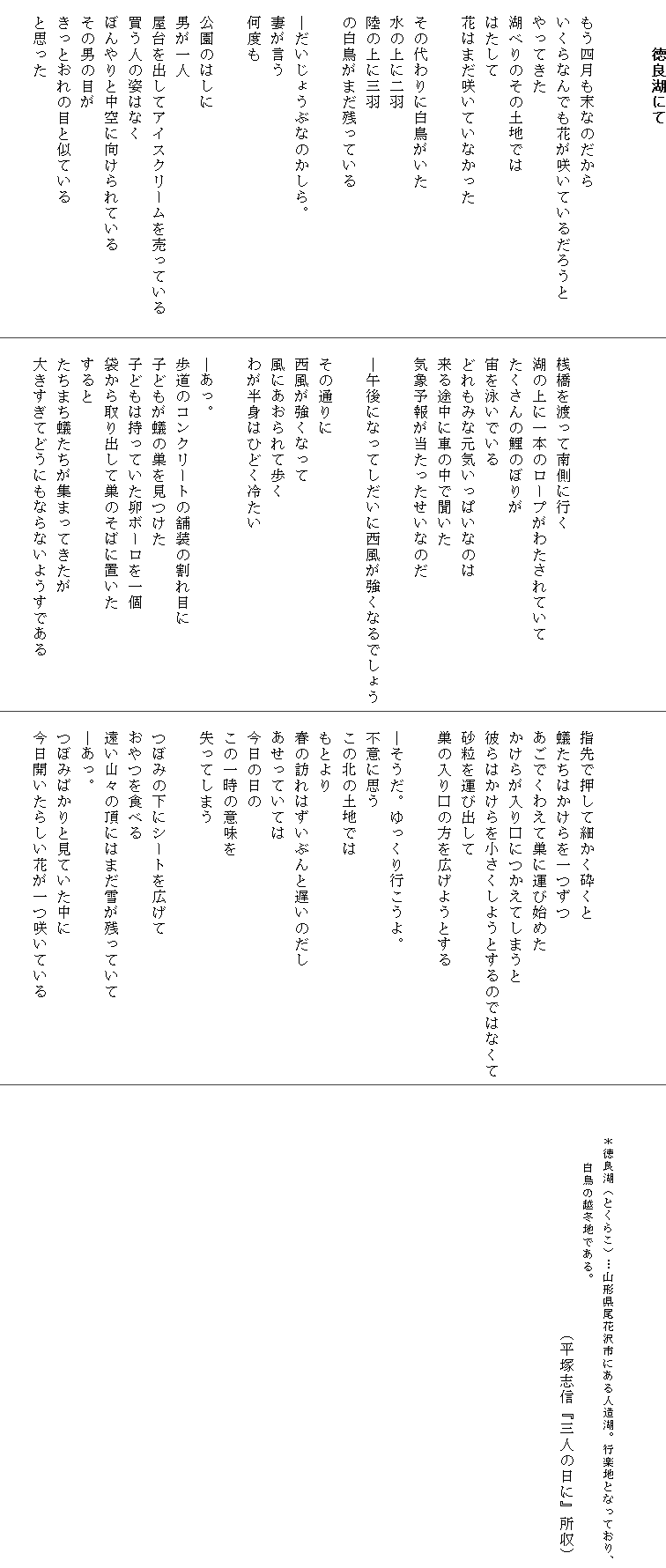四月は、「決意」が求められる時期です。
トップページに載せた「前線」という詩の中に、「美とはひとつの音楽であり/人は人生を奏でている」という言葉があります。この言葉には、実は、私が高校を卒業して大学に進学するときに抱いていた“決意”が反映されています。
高校生のときに、私は、人の生き方を価値づける「原理」のようなものを求めていました。金銭的な富の多少や、集団・組織内の地位の上下、あるいは身体的・肉体的な強弱など、「それを規準として価値づければ根本的・必然的に上下に序列化されてしまう」ような規準ではなく、人の生き方を価値づける、もっと適切な規準となる「原理」を求めていたのです。もし、そういうものがないとしたならば、「人生に上も下もない」というようなことが言えなくなってしまう。それでは、おかしい。そんな思いをもっていました。
結果として、私が人生を価値づける規準としてふさわしいと考えたのが「美」でした。「美」には、「美」であるか「美」でないかという判断はあっても、「美」であれば、上も下もありません。桜の花も、薔薇の花も、ともに「美しい」けれど、比較してどちらかがどちらかより「より美しい」と決定することはできません。「それぞれに美しい」とするしかないのであって、あとは好みの問題となります。つまり、「美」には「価値」を付与するはたらきがあり、したがって、それは、ものごとを、人の生き方=人生をも含めて、価値づける規準(「美しい」か、「美しくない」か)となり得るわけですが、一方、「価値づけることによって上下に序列化してしまう」というはたらきはともなっていない、と、そのように考えたのです。
たとえ総理大臣になっても、誤った考えによって、国を破滅的な事態に導くようでは、その人生は「美しい」とは言えない。たとえ、巨万の富を得ても、それが正当な手段によって得られたものでなかったり、あるいは富を増やすこと自体が目的化してしまったりすれば、「美しい」とは言えない。一方、たとえ、世間的に高く評価される職業ではなく、大きな収入を得ることができないとしても、他人を欺くようなことがなく、誠実にはたらいて誰かを幸せにする人生であったならば、それは「美しい」と言える。そのような価値規準をもって、生きていこう。大学に入学するころ、私がもっていたのは、そのような決意でした。
もう一つ。「人は何のために生きるのか」という問題が、高校生のとき、私を悩ませていました。もし、この問いに答えを見つけられないのであれば、それは、つまり、生きることには意味がない、ということになってしまう。そのように、思っていたのです。
この問題を、自分なりに解決するきっかけとなったのが、小林秀雄の評論を読んだことでした。具体的に、どの文章が、どの言葉がということではありません。しかし、『モオツァルト・無常という事』(新潮文庫)等の小林の文章を読むことで、私は、次のようなことを「実感」したのです。
「人生とは、『何のために生きるのか』というような、観念的な問いを立てるのにふさわしいものではない。人生は、本来的に、“理解”の対象ではなく、文字通りに、“生きる”ものである。『生きることの意味』と言うのであれば、それは、『生きる』ことについて観念的に思考することによって得られるものではなく、実際に『生きる』ことによって“立ち現れてくる”もの、生きるにつれて“感受される”ものだ。」
小林の文章を読んで、私が「実感」した(「理解」したというのではなく、言い換えれば「感受」した)のは、以上のようなことでした。
美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない。
これは、たいへんよく知られている小林の言葉ですが、出典から、前後の文章を含めて引用すると、次のような文脈の中で使われています。少し長くなりますが、引用します。
無用な諸観念の跳梁しないそういう時代に、世阿弥が美というものをどういう風に考えたかを思い、其処に何 の疑わしいものがない事を確かめた。「物数を極めて、工夫を尽して後、花の失せぬところを知るべし」 美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない。彼の「花」の観念の曖昧さに就いて頭を悩ます美学者の方が、化かされているに過ぎない。肉体の動きに則って観念の動きを修正するがいい、前者の動きは後者の動きより遙かに微妙で深淵だから、彼はそう言っているのだ。不安定な観念の動きを直ぐ模倣する顔の表情の様なやくざなものは、お面で隠して了うがよい。彼が、もし今日生きていたなら、そう言いたいかも知れぬ。
(前掲新潮文庫p63、「当麻」より)
「美」とは、「観念」によって理解するものでも、されるものでもなく、ただ感受するしかないものだ。そのように、小林は言っているのだと、私はとらえています。そして、ここでの「美」を、「人生」と置き換えても、小林の考えからそれるものではないのではないかと、思っています。
「美とはひとつの音楽であり/人は人生を奏でている」には、「美とは、音楽と同じく、感受することによってはじめてその価値が立ち現れるもの、そして、たとえばモーツァルトの音楽とベートーヴェンの音楽の優劣を決定することができないように、価値の優劣の決定を伴わないものだ/音楽はそれが奏でられている限りにおいて音楽として意味をもつ、そのように、人生もまたそれが生きられている限りにおいて意味をもつ、そして、音楽を奏でるとき奏者は美しく音楽を奏でようとする、音楽を美しく奏でるようなつもりでこれからの人生を生きていこう」、そうした「決意」が反映されています。
もちろん、このような「決意」の読み取りを、詩句の解釈として、読者に求めることはできません。ただ、言葉それ自体が、なんとなくではあっても、読者の心の中に残って、それこそ音楽の一節のように、心の中で思い出されることがあってくれればいいとは思います。