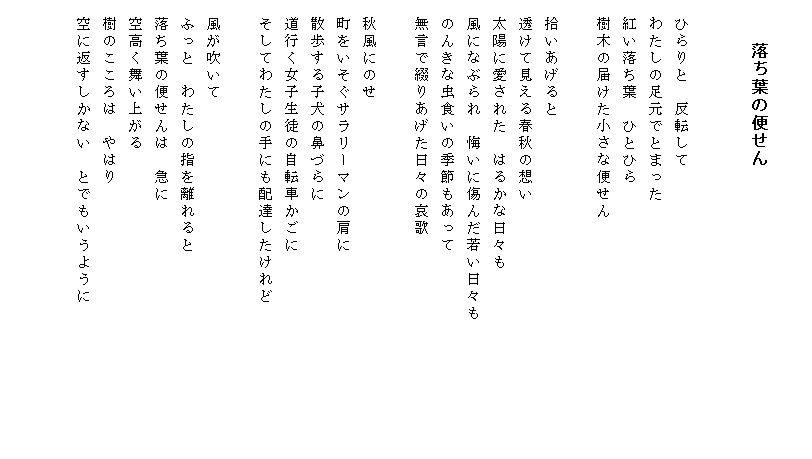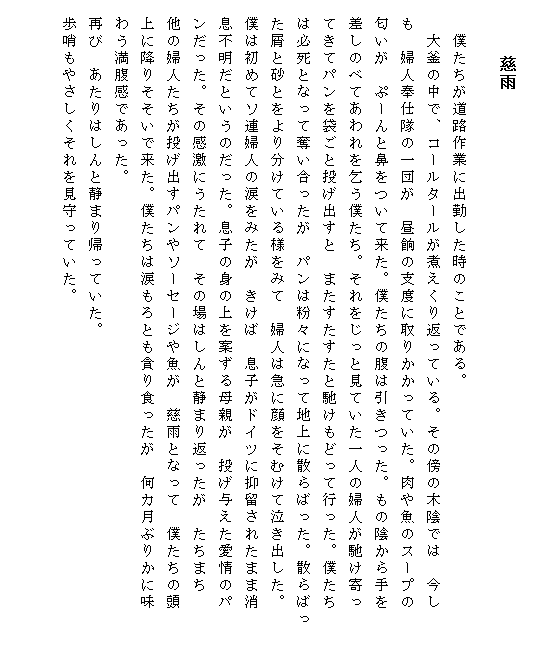山形県内在住の詩人を中心に、二十人の詩人の手になる二十三の詩集と一篇の詩(真壁仁「峠」)をとりあげた、計二十三本の論考に、万里小路自身の詩を引き合いにした論考一本を加えて、全部で二十四本の論考を収めている。
取り上げている詩人は、近江正人、久野雅幸、いとう柚子、芝春也、高橋英司、佐々木悠二、高瀬靖、菊地隆三、本郷和枝、高沢マキ、佐藤登起夫、庭野富吉、北原千代、房内はるみ、池田瑛子、真壁仁、佐藤總右、芳賀秀次郎、大滝安吉、長尾辰夫。近江正人から佐藤登起夫までが、現在、山形県内在住の詩人。庭野富吉から池田瑛子までが、県外の詩人。真壁仁から長尾辰夫が、かつて県内在住で活躍した詩人(いずれも故人)である。
本書における万里小路の詩の読み方には、大きな特徴がある。詩の鑑賞を行いながら、同時に、詩を「思索するためのテキスト」(「あとがき」より)として、宇宙や生命、人間、人生等のあり方について、実存主義の概念を用いて、自己の思索を展開している点である。
詩とそれに基づく思索が、ともに、多くの読者の共感を得るであろうと思われる例を、次に紹介しておきたい。
詩は、近江正人の詩「落ち葉の便せん」。全文を引いておきたい。
詩をもとに、万里小路は、詩の鑑賞を行いつつ自己の思索を展開する。次に引くのは、この詩を読むことによって展開された、万里小路の思索の最後の部分(と言っても、引用部分のあとに、近江の別の詩についての鑑賞と思索が続くのだが)である。
実存するとは、「いまここ」を超え出ることによって遠い彼方へと行くこと。すると、願うという営為それ自体が生命存在の核である可能性がある。花は咲くことを宇宙 に願われ、蕾が願いの具現化された形であったように、蕾を開いてゆく志向性こそが花という生命存在の願いである。そして、開花し、成熟し、散ってゆく。どこへ? 此岸から彼岸へと。そこがどこであれ、跳躍しようとする志向性にこそ、生きとし生けるものの存在の秘密が潜んでいる。一枚の落ち葉は、町をいそぐサラリーマンの肩に、散歩する犬の鼻づらに、道行く女子生徒の自転車かごに、そしてわたしの手にも配達され、それぞれの音信を通わせたけれど、落ち葉もまた帰るところがあった―<樹のこころは やはり/空に返すしかない>。高いところへと。
サラリーマンも子犬も女子生徒もわたしも、そして一枚の落ち葉もまた、それぞれの世界を生成している。驚くべきは、それぞれが互いの存在原理を生きることによって、他者と共生する世界を志向していることである。ミクロコスモスが響き合うマクロコスモスへの志向性によって、存在は宇宙によって夢見られた夢である。
ここに引用した文章は、詩「落ち葉の便せん」をもとに万里小路が行った思索の、あくまで一部であることを、あらためて確認しておかなければならない。詩と引用部分との間には、引用部分の倍以上の文章量の思索が展開されている。その部分を欠いているために、詩と引用部分とのつながりが不明確になっていることを承知しておいてほしい。しかし、ここに引用した、わずかな部分からでも、万里小路の思索の特徴は理解可能であると考える。
詩を読み味わうとともに、その詩をもとに展開される万里小路の思索について思考をめぐらすこと。そこに、本書を読む楽しみがある。
さて、本書は、当然のことながら、取り上げられた詩人と詩集・詩作品についての紹介の書ともなっている。本書を読むことで、既知の詩人・詩について認識を深めたり(例えば、いとう柚子が「月の詩人」というべき特徴をもっていること)、未知の詩人・詩についてその魅力を教えられたりすることが、少なからずあった。
後者の例としては、特に、新潟県在住の詩人、庭野富吉の詩に魅力を感じ、戦後を山形県内で過ごした詩人、長尾辰夫の詩に感銘を受けた(もっとも、この二人の詩人について未知であったことを、無知として恥じるべきなのかもしれないが)。とりわけ、長尾の次の詩は、私に、ある衝撃を与えた。
長尾は、終戦後シベリヤで四年間の抑留生活を送った人である。この詩が収められている詩集は、『シベリヤ詩集』のタイトルをもつ。
シベリヤ抑留については、決してあってはならないことであり、その罪や責任が糾弾されてしかるべきことである。そして、この詩に表現されているような出来事があったからといって、そのことによってシベリヤ抑留の非人道性が少しも軽減されるものでないことは言うまでもない。また、こうした出来事が、たとえ繰り返しあったとしても、そのことがその場にいる抑留者の根本的な救済につながるものでないことも明白である。
では、この詩に述べられているような出来事は、記述する価値のない出来事なのだろうか。大事の中の小事として無視されてしかるべきこと、巨大な非人道性の中にたまたま紛れ込んだわずかな人間性の発揮として記録にも記憶にも残す価値のないことなのだろうか。あるいは、このような出来事を記述することは、シベリヤ抑留の非人道性と悲惨さへのフォーカスをぼやけさせる危険性をもって、むしろ避けるべきことと判断すべきなのだろうか。この詩の中の「一人の婦人」や「婦人たち」、「歩哨」は、その場しのぎの善行を行うのみで、非人道的な措置への根本的な抵抗を行わなかった偽善者として、むしろ責められるべきなのだろうか。
私には、そのようには思われない。
この詩について、万里小路は、次のように書いている。
消息不明の息子のドイツ抑留という事情があってこそではあろうが、ここには紛れもないゾルゲ(思いやりの心)が見て取れる。この瞬間においては敵も味方も存在せず、ただひととひととの優しい関係性の時間が流れている。その証拠に、他の婦人たちも触発されて、たとえ犬に投げ与える餌のようにであろうとも、パンやソーセージや魚を投げ与えたではないか。それだけではない。歩哨もやさしくそれを見守っていたのだという。この一瞬のうちに現成しえた日向性の心こそ、世界を変える力を持ちうるだろう。それは、逆境のうちで芽生えたにせよ、人間存在への信頼と生きることへの愛である。
万里小路の考え方に、私も賛同する。確かに、この詩は、シベリヤ抑留の中で死んでいった死者たちの無念を晴らすということにはつながらないかもしれない。死者たちの無念を晴らす、無念に応えるという点では、シベリヤ抑留がいかに非人道的であったか、いかに悲惨なものであったかを記述し伝えることこそ必要であるという主張には説得力がある。シベリア抑留という出来事においては、死は必然的であるが、一方、生きのびるということは偶然にすぎない、という考え方にも、説得力がある。この詩においては、「息子がドイツに抑留されたまま消息不明」の「一人の婦人」に「僕たち」が出くわしたのは偶然だろう。しかし、その「一人の婦人」が「僕たち」に「パンを袋ごと投げ出す」という行為には、日本がドイツと同盟を結んでいたという事実や当時の政治的な状況を乗り越えた、人の心の必然的な動きがあることも確かなのではないか。「一人の婦人」の心情を思って「パンやソーセージや魚」を投げ上げ与えた「他の婦人たち」の行為、そして、「やさしくそれを見守っていた」という「歩哨」の行為についても、同じことが言える。そうした心の動きを、「思いやり」という言葉でとらえるのは、適切なことだろう。加えて言えば、空腹を極めていた「僕たち」がそうした行為に、不当に抑留されているという状況を越えて、感謝の気持ちをもつのも、人の心のはたらきとして必然性があるのではないか。
この詩には、読む者を“安心”させる力がある。その“安心”は、政治的・軍事的な状況を越えてはたらいた「思いやり」からくるものだろう。「一人の婦人」や「婦人たち」、「歩哨」の行為が状況を根本的に変えるものではないからといって、また、その行為を記述することが死者の無念を慰藉する方向性をもたないからといって、表現する価値がないということにはならないのではないだろうか。彼女たちの行為が、身体的にも、精神的にも、「僕たち」を、と言ってまずければ、少なくとも「僕」を、救ったという事実の重みにも注意する必要がある。
本書の執筆動機を、万里小路は「あとがき」の中で、次のように述べている。
執筆の動機は、書き手はいても読み手はいないのではないか、という思惑にあった。つまり、地元で出版される詩集について、多少の紹介や寸評は出るものの、ほとんどが未読の状態にあるのではないか。ならば、誰かが読み手に徹し、読みの結実を表す必要があるのではないか、と。
賞賛すべき志であると思う。
拙詩集『旋回』については、本書に先立つ『詩というテキスト』(2003年2月16日発行、書肆犀)でも取り上げてもらっている。私の詩についてのまとまった言及があるのは、万里小路以外には、残念ながら、皆無である。繰り返しての言及に対し、深く感謝していることを、ここに明記しておきたい。
(以上、敬称と敬語表現は省略させていただきました。)