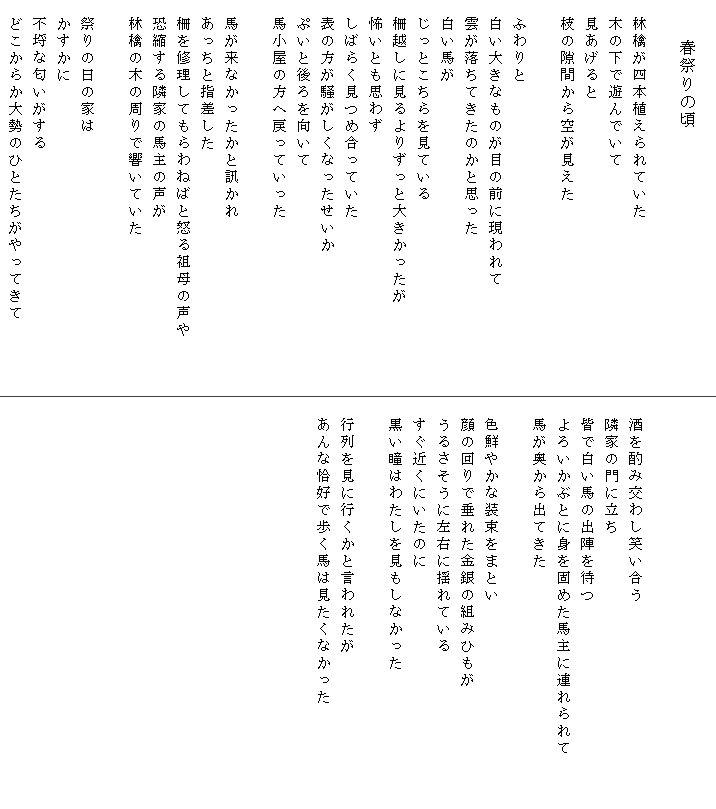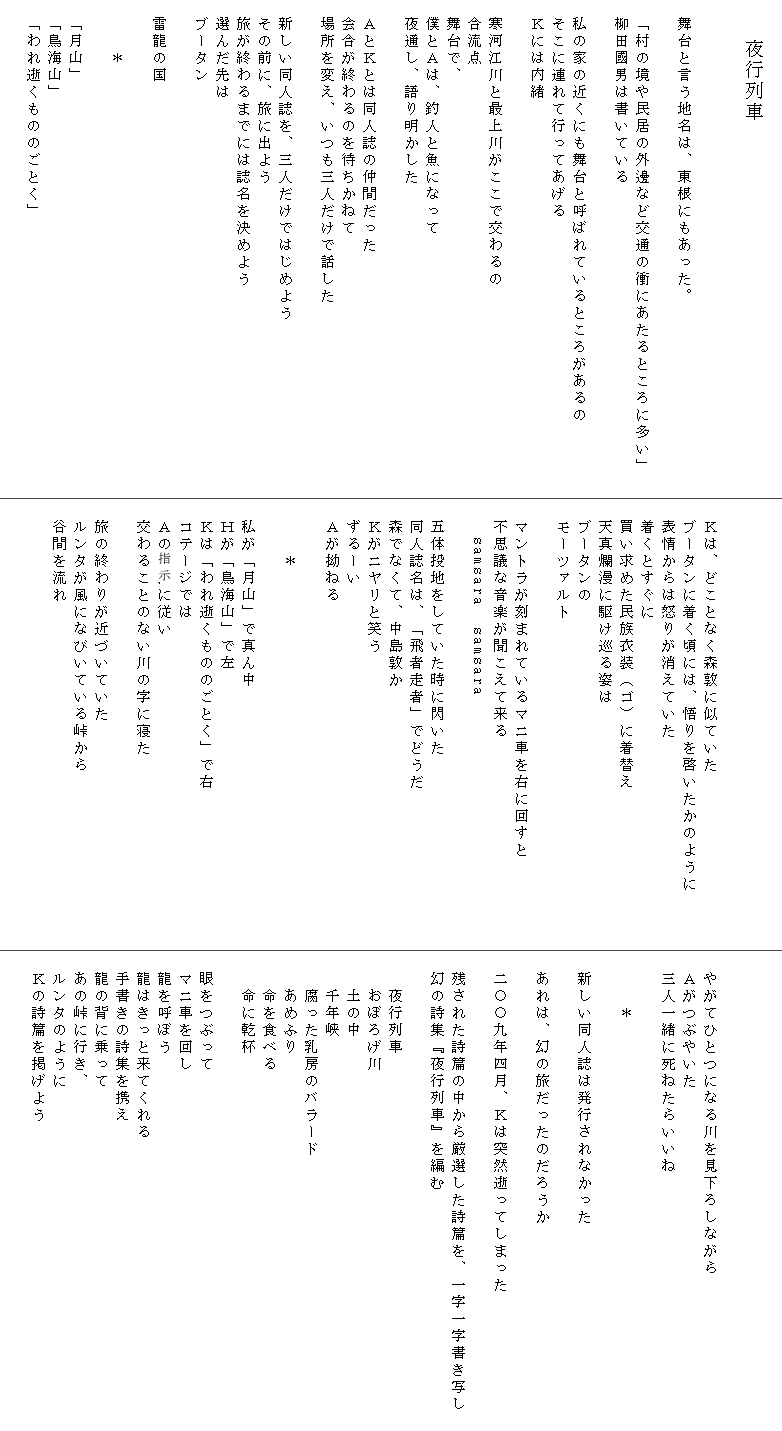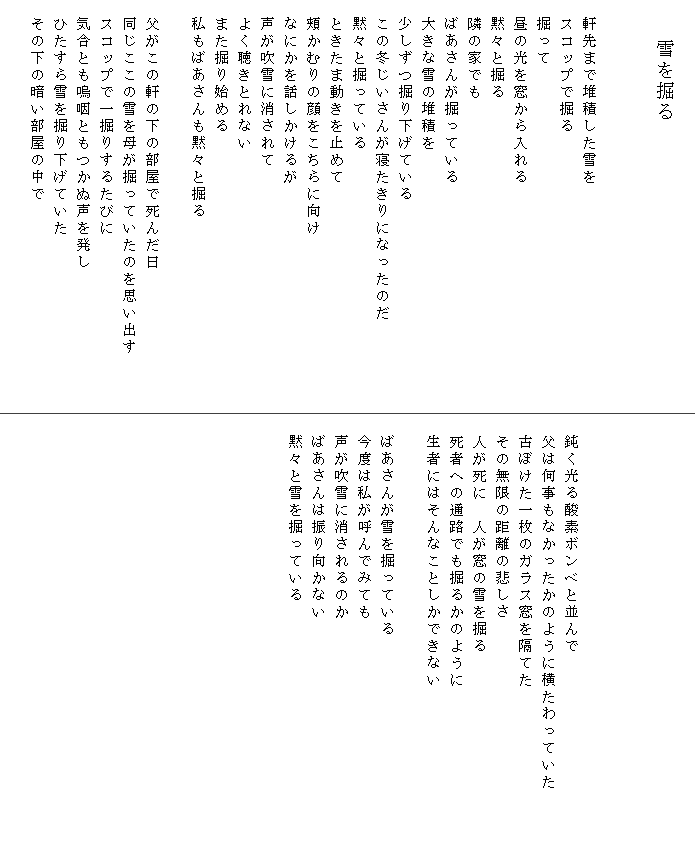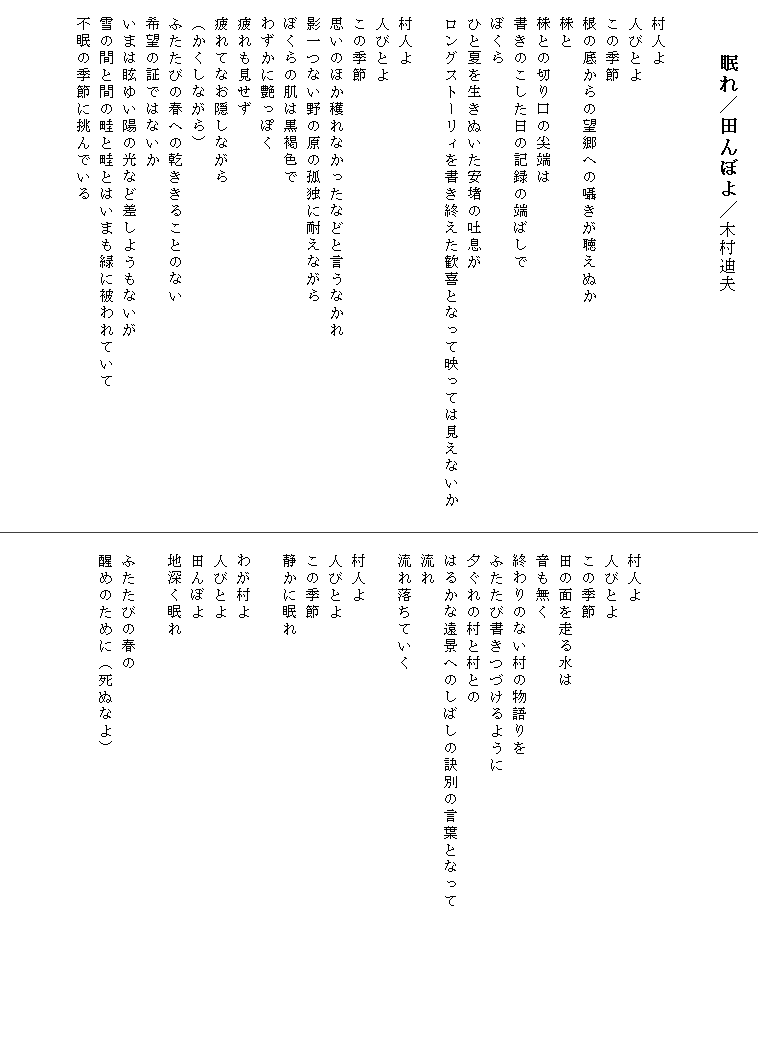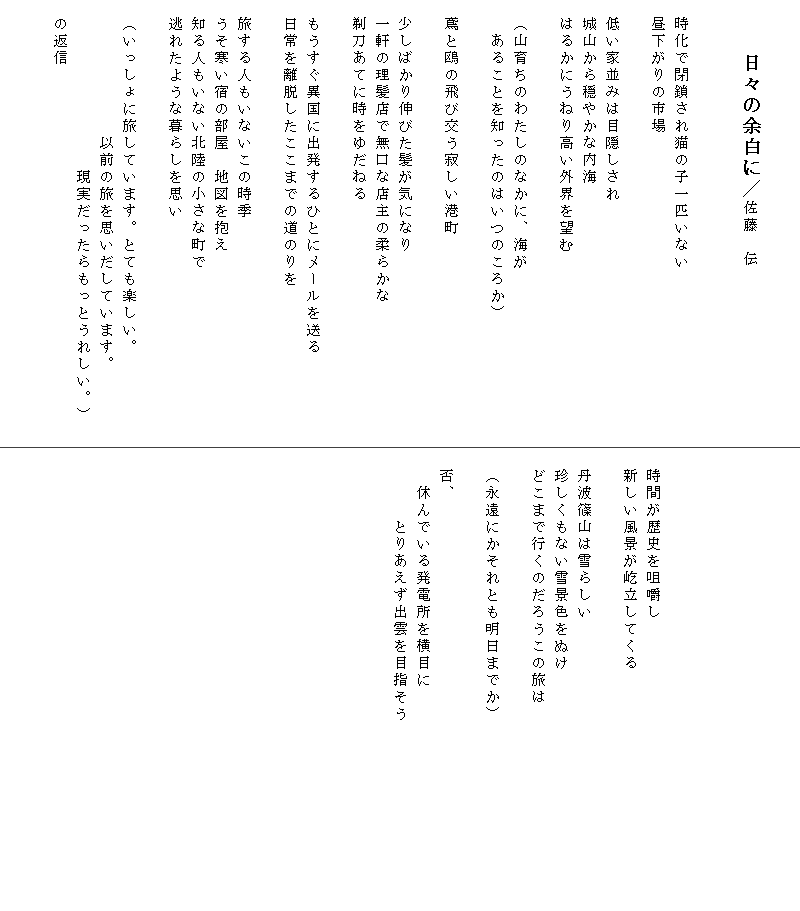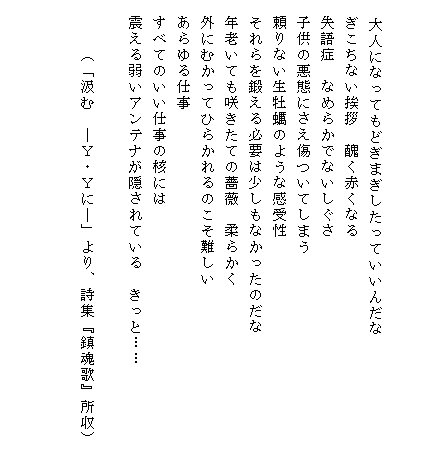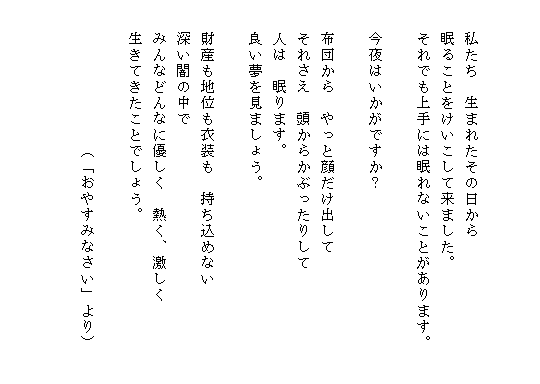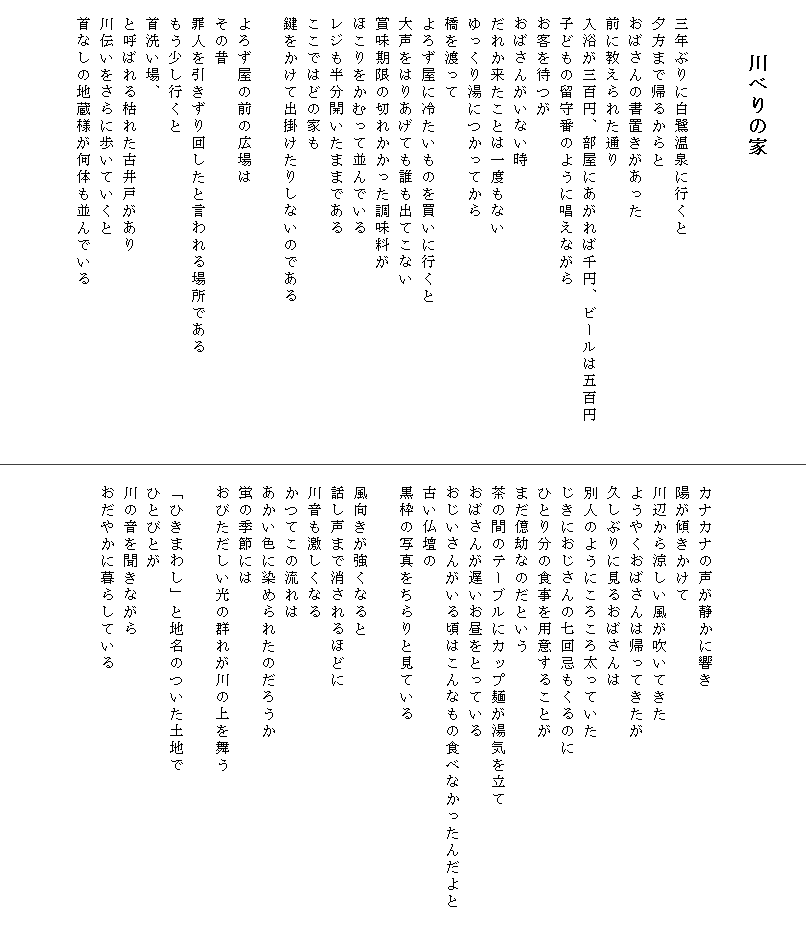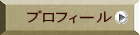

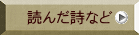
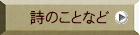
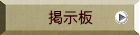
詩誌を読んで〈2013〉
『きょうは詩人』第24号(2013年4月24日発行)
長嶋南子、万亀佳子、小柳玲子、森やすこ、伊藤啓子、古谷鏡子、鈴木芳子、苅田日出美、福間明子、吉井淑による詩、計13篇と、伊藤啓子のエッセイを、読むことができる。
私にとって最も魅力的だったのは、伊藤啓子の次の詩である。
「祭りの日の家は\かすかに\不埒な匂いがする」と述べられる第四連を除けば、事実を淡々と述べて終わっているかのような表現である。しかし、そうではない。単に事実を述べているかのような表現が、実は、言葉で直接に表現されてはいない、大きく、豊かなものを表現している。
第一連。作者がまだ幼い時のことだと、言葉で直接に表現されてはいない。しかし、四行からなる表現は、そこに述べられていることが、作者がまだ幼い時のことであることを、しっかりと伝えている。「木の下で遊んでいて/見あげると/枝の隙間から空が見えた」の三行は、幼い者の視点をみごとにとらえていて、読む者に、幼い時に特有の、いわば空間の感覚を、実感として想起させる。そして、このことには、「林檎」が低い位置に枝を張っているということもかかわっている。
第一連の「枝の隙間から空」を「見あげ」る視点は、そのまま、第二連につながっていく。
第二連。「驚いた」とも「あっけにとられた」とも述べられていないが、突然の出来事に対する、あっけにとられたような気持ちは、十分に伝わってくる。というよりも、「白い馬」が突然目の前に現れて、思いがけず目を合わたときの、現実感を欠いたような感覚、出来事に意識が十分に追いついていないような、そのときの出来事に固有の感覚が、読む者に、きちんと伝わってくる。その感覚は、第三連にもつながっている。
第三連。第二連に述べられた出来事が実は持っていた、意味、すなわち、一つ間違えば命を落とすことにさえつながった、出来事の危険性が、大人たちのやりとりを通して表現されている。
第四連。詩全体の構成において、起承転結の「転」の役割を果たしている。「祭りの日の家は\かすかに\不埒な匂いがする」と、この作者に独特の感覚によってとらえられた、「祭りの日の家」のようすが表現される。そして、読む者は、第二連に述べられた出来事の背後に「祭り」があったこと、その「祭り」と「白い馬」とにどういうかかわりがあるのかを知る。
第五連。述べられている馬のようすは、第二連でのそれと対照的である。「色鮮やかな装束をまとい」「顔の回りで垂れた金銀の組みひもが」「左右に揺れている」という、祭りの日にふさわしく華やかに装われたようすは、しかし、第二連で述べられた体験をした作者にとっては、「うるさそうに」の一語で表現されているように、嫌悪の対象でしかない。そして、第二連の体験では「しばらく見つめ合っていた」馬が、「すぐ近く」を「わたしを見もしな」いで通り過ぎてしまう。ここでの、馬の姿と態度に対する嫌悪と幻滅が、最終連につながる。
最終連。「あんな恰好で歩く馬は見たくなかった」の一言について考えたい。この一言に込められているのは、直接的には、第二連の体験で感じた馬の“尊厳”をだいなしにしてしまうものへの反発であると考えられる。そう読んで、終わりにしてもよいだろう。しかし、加えて、次のように考えることもできるのではないか。第二連で述べられている体験は、幼い時にしかありえない、幼い時に固有の体験である。一方、馬に華やかな装いを施し、「祭り」を執り行うのは大人たちである。幼い時に固有の、価値ある体験が、大人たちの振る舞いによって、あっけなくだいなしにされてしまった、そのことに対する悔しさ。そういう気持ちが込められていると読むことも可能であると考える。
以上、伊藤の詩が、言葉で直接に述べていることのほかに、いかに、大きく、豊かなものを表現しているか、そして、いかに無駄のない、緻密な言葉の使い方で作られているかを、述べたつもりである。
詩を評価する規準には、もちろん、さまざまな規準があるわけだが、私は、こうした点をも、詩を評価する際の規準として大切にしたいと考えている(以上、敬称を省略させていただきました)。
細矢利三郎、福岡俊一、安達敏史、いとう柚子、阿部栄子、いであつし、芝春也の詩、計10篇と、安達敏史、いとう柚子、芝春也のエッセイを読むことができる。
細矢の詩「夜行列車」が、深く心に残った 。長い詩であるが、全文を引かせていただきたい。一部の引用だけでは、この詩について語ることはできそうにない。
ルビが振られているのは、「
飛者走者」。中島敦の小説「悟浄出世」中の「
飛者を走らしめ、
走者を飛ばしめる」という言葉からとっていると思われる。
この詩で述べられている、友人の死という出来事それ自体については、私は何も言う資格がない。私が言えるのは、もっぱら詩の表現についてである。
第一節。「舞台」という地名の説明から始まる。友人の死という、悲痛な出来事を語る詩を、地名の説明から始めることのできる人は、いったいどれだけいるだろうか。私が言いたいのは、悲痛な心情をそのまま言葉にしてぶつけるのではなく、その心情をいったんしまいこんで、詩全体の構成を構想する、その構成力についてである。「舞台」という地名の説明は、詩の書き出しとして読む者を惹きつける力をもっており、さらに、「僕」と「A」と「K」三人の間に起こった出来事(思い出)を伝える展開の中で、「僕」と「A」との一夜の出来事の“舞台”として活かされている。
第二節。ここでも、地名が出てくる。「月山」と「鳥海山」。地名であるとともに、森敦の小説の題名でもあり、「森敦に似ていた」「K」の面影につながっている。第一節には、「寒河江川」「最上川」という地名があり、この詩における、山形県内の地名の活用は、詩に、独特のリアリティと雰囲気を与えている。山形県という、一地方、全国から見れば、狭く限られた地域の中で、文学に深い関心をもつ者三人が、身を寄せ合うようにして活動していたことを思わせる、そのような雰囲気、とでも言えるだろうか。この雰囲気には、「月山」と「鳥海山」が、地名であるとともに森敦の小説の題名であること、それに、「
飛者走者」という同人誌名が、中島敦の小説中の言葉からとられた、文学によほどの関心がなければ思い浮かばないものであることもかかわっている。
第三節。この節も、地名の使用から始まっている。「私が「月山」で真ん中/Hが「鳥海山」で左/Kは「われ逝くもののごとく」で右」という「A」の指示は、「H」(当然、作者であろう)と「K」が自分から等距離になるようにという、「A」の配慮を表すと同時に、「月山」と「鳥海山」がともに位置する、出羽山地の山なみを想起させる。山形県に住む者にとっては、「月山」も「鳥海山」も“西方”を意識させる山であり、その向こうには、「ブータン」があり、インド(天竺)があり、西方浄土がある。そのことも、この詩に、独特の雰囲気を与えている。つねに、どこかに“浄土”を感じさせるような、薄暗く、かつ澄明な雰囲気である。加えて言えば、「Kは「われ逝くもののごとく」で右」という言葉は、「K」の行く末を暗示するかのようでもある。
さらに、地名とのかかわりということで言えば、「川」のイメージが、第一節と第三節で、使われている。第一節「寒河江川と最上川がここで交わるの」、第三節「交わることのない川の字に寝た」「谷間を流れ/やがてひとつになる川を見下ろしながら」。こうした「川」のイメージは、「僕」「A」「K」三人の存在と重なっており、第三節の最終行「三人一緒に死ねたらいいね」という言葉につながって終わる。
第四節。使われている言葉のほかには、言葉を加えることも減らすこともできないような表現が並ぶ。特に効果的なのが、第二連、「あれは、幻の旅だったのだろうか」の一行。この一行の言葉が、この詩に述べられている出来事のはかなさを実感させ、言葉とは逆に、この詩にリアリティを与えている。特に、「眼をつぶって」で始まる最終連のリアリティは、この一行によって保障されている。
このように、この詩では、友人の死という悲痛な出来事が、非常に巧みに構成された言語表現によって語られている。そうでなければ、「K」と「僕」「A」三人のかかわりや、「K」の死が「僕」にとってどういう意味をもつものであるかを、十分に、読者にきちんと伝わるように、表現することはできなかっただろう。悲痛な気持ちをいったん心の中にしまいこんで、出来事と思いを詩によって表現するためには、数年間の時間の経過が必要だったのではないか、と私は考えている。
さて、本誌には、もう一篇、身近な人の死を表現した、深く心に残る詩が収められている。芝のエッセイ「永訣の冬」の中で紹介されている、芝自身の詩「雪を掘る」である。一冊の詩誌から、あまりに多くを引用することは避けなければならないと自戒しているが、この詩は、ぜひとも引かせていただきたい。この詩の存在を、一人でも多くの人に知っておいてほしいからである。
生きることを励ます力をもった詩であると思う(以上、敬称を省略させていただきました)。
『山形詩人』第80号(2013年2月20日発行)、第81号(2013年5月20日発行)
「山形詩人」には、私も同人として所属している。以前は、新しい号が発行されると、集まって合評会を行っていた。このごろは途絶えているが、互いの詩を遠慮なく批評し合う厳しさをもった集まりである。掲載の作品について、私がここで勝手なことを述べても、ゆるしてもらえることと思う。
第80号には、阿部宗一郎、木村迪夫、近江正人、高啓、佐野カオリ、万里小路譲、平塚志信、山田豊、佐藤伝、菊地隆三、高橋英司による、計十一篇の詩が掲載されている。中で、私が最も高く評価したいと思ったのは、木村の詩「眠れ/田んぼよ」である。
全文を引用させていただいた。
まず、特筆したいのは、この詩の「調べ」である。全体に、生命感の感じられる、生き生きした調べが一貫している。全六連のうち四連が「村人よ/人びとよ/この季節」で始まっており、その繰り返しの効果があることは言うまでもない。だが、それだけではない。第一連の5行め~10行め、第二連の5行め~12行め、第三連の3行め~11行めが、それぞれ、一文での表現となっていることに着目したい。そうした、息の長い表現が、冗長さを感じさせることなく、むしろ生命の躍動を思わせる、「勢い」を伴っていること。そこにこそ、この詩の生き生きした調べの根源があると考える。
そして、そうした息の長い表現が、散文的な説明に陥ることなく、詩的な想像力の発露として、散文ではあり得ない、詩ならではの表現となって、農にたずさわる者としての木村の思いを表している。
周知のとおり、木村は、「農民」の立場から詩を書き続けている人である。この詩は、まさしく農民の思いを表現しながら、その一方で、農民であるかどうかの区別を越えて、広く、読む者を魅する力をもっている。農民ではない、私のような者にも、繰り返し読んでみたいと思わせるものとなっている。
うれしいことに、「生命の躍動を思わせる」「生き生きした調べ」で、「散文ではあり得ない、詩ならではの表現」となっており、「農民であるかどうかの区別を越えて、広く、読む者を魅する力をもっている」という点では、『山形詩人』第81号掲載の木村の詩「吹く春が」も同様である。あるいは、木村の詩が、丸山薫賞受賞の詩集『光る朝』(2008年発行、書肆山田)所収の詩篇とも、また異なる魅力をもつものになってきているのだろうか。
第81号には、佐藤伝、佐野カオリ、平塚志信、阿部宗一郎、万里小路譲、近江正人、木村迪夫、菊地隆三、山田豊、高橋英司による、計十篇の詩が収められている。私にとって特に魅力的だったのは、先に触れた木村の詩「吹く春が」と、次に引く、佐藤の詩「日々の余白に」である。
やはり、全文を引用させていただいた。
佐藤の詩は、「危機」を感じさせる。「危機」とは、人生の危機、生きることの危機である。この詩も、そうだ。「わたし」は、何らかの理由によって、日常の生活を逃れて、旅の途中にある。その理由は、この詩を単独で読む限りにおいては、不明である。そして、理由が明確である必要もない。「日常を離脱」せざるをえない、「危機」の状況にあることは、この詩の全体から強く感じられる。すなわち、この詩を読む者は、その「危機」を気持ちの上で共有して(つまり共感して)、この詩を読むことができる。
いま「わたし」が身を置いている、「港町」の情景が、無駄のない、卓抜な表現によって、ありありと目に浮かぶ。その情景は、「日常を離脱して」来た人の心象風景そのものと言ってよいだろう。ひどく寂しく、そして、どこか「惹かれる」ところがある。
「わたし」の行動も、まさに「日常を離脱して」来た人のそれであり、同じ状況であれば「自分もそういうことをするのではないか」と思われる。
第三連の挿入、第六連~第八連の挿入(エピソード)も、効果的だ。
終わりの三連は、圧巻というべき表現になっている。これから向かう、旅先の地のイメージに心情表現を重ね(第十連)、見通しの定まらない「危機」の旅であることを端的な表現によって表し(第十一連)、「とりあえず」旅を続けるしかない心情を表現しつつ、「わたし」の危機と日本の危機とがさりげなくすれ違っている(最終連)。
こうして、この詩は、「危機」によって「日常を離脱」する人の、いわば“「典型」をとらえて、表現する”ことに成功している。それによって、この詩のことばは、作者である佐藤のことばでありながら、広く、読む人に共有されるものとなった。
「危機」が、佐藤にとって、いかに深刻なものであっても、それが、「読者によって共有されることばの表現」として表現されていなければ、読者にとっては、つまりは、他人事である。表現されている内容が深刻なものであれば、あるいは、社会的に重大ないし重要なものあれば、そのことによって高い価値を認めるというのは、詩を評価する視点としてはいかがなものか、と私は考えている(以上、敬称を省略させていただきました)。
『表象』第31号(2013年3月2日発行)~第41号(2013年7月7日発行)
万里小路譲が編集発行を行っている一枚誌である。詩は、近江正人「ひかりのたい焼き」「雪の魂は」(第31号)、尾崎まりえ「整理タンス」(第32号)、岩瀬眞砂子「きっと…」(16首の短歌からなる、第33号)、近江正人「ナマハゲ」(第34号)、近江正人「妻のへそ」(第35号)、万里小路譲「桜雪」(第37号)、尾崎まりえ「カラー・チャート(2)」(12首の短歌からなる、第38号)、平塚志信「またね」(第39号)、尾崎まりえ「人差し指」(第41号)を読むことができる。ほかに、万里小路が、茨木のり子と石垣りんの詩の鑑賞を継続的に行っている。
茨木と石垣の詩は、やはり読みごたえがある。その理由は、私なりに一言で表現すると「見えないものごとを見えるようにしてくれる」からだ。ここで「見えない」とか「見える」とか言うのは、もちろん、視覚の話ではなくて、認識の話である。そして、その際、詩を読んで得られる認識には“感動”が伴っている。
例えば、茨木の詩の、次のようなことば(『表象』第31号より引用)。
人前で話すことが苦手な私を、このことば(詩)は、大いに励ましてくれる。特に、引用部分の終わりの三行「あらゆる仕事/すべてのいい仕事の核には/震える弱いアンテナが隠されている きっと……」は、茨木のこの詩を読んではじめて「見える」ようになったことがら(はじめて得られた認識)であり、私は“感動”を覚えながらこのことばを読んだ。
石垣の詩の、次のことばも同様である(『表象』第39号より引用)。
特に、引用部分の最初の三行「私たち 生まれたその日から/眠ることをけいこして来ました。/それでも上手には眠れないことがあります。」と最後の連の一行め「財産も地位も衣装も 持ち込めない」は、私に、眠りについての新しい認識を与えてくれた。そして、私は、やはり、“感動”を覚えながらそれらのことばを読んだ。
さて、話は変わるが、今回、私が“感動”ということばを使ったことには、きっかけがある。ここのところ、私は、谷川俊太郎が詩について論じた文章を集めた『詩を考える』(思潮社、2006年6月10日発行)という本を読んでいる。その中に、次のような文章がある。
現代にこそ詩人は最も必要なのである。我々はあくまで
詩人としての誇りを捨ててはならない。そしてそれ故にこそ私は、我々があくまで詩人として人々に対しなければならぬということを主張したい。詩人が人々に供給すべきものは、
感動である。それは必ずしも深い思想や、明確な世界観や、鋭い社会分析を必要としない。むしろかえって、それらが詩人を不必要にえらぶらせ、そのため詩の感動を失わせることが少なくない。詩人は感動によって詩を生み、感動によって人々とむすばれて詩人になるのである。(前掲書p68~69、「世界へ!」より)
初出は、1956年10月、『ユリイカ』誌に掲載されている。今から、五十年以上前に書かれた文章であるが、現在の状況においても、十分に通用することばである。
この文章が書かれた当時と比較して、詩が置かれている状況は、厳しさを増している。①日本のポピュラーミュージックが発展して、多様な表現が行われ、より幅広い立場の人々に共感され、感動を与えるようになった。②質の高い、漫画やアニメが多様に、数多く作られるようになった。③SNSの展開により、人々はこれまでになかった形で、言語を含めた表現のやりとりを楽しむようになった。などの理由によって、「詩が相手にされない」状況は、いっそう深刻になっている。しかし、「詩を読むことによってしか得られない感動」は、今日、なお存在する。そして、いわば「感動が大量に生産され、大量に消費されている」ような、今日の状況において、「詩を読むことによってしか得られない感動」は、いっそうその価値を増しているとさえ言えるのではないか。「見えないものごとが見える」ようにし、いっとき消費されて終わるような感動とは別種の感動を与えることばとして。茨木や石垣の詩は、その好例を示していると考える(以上、敬称を省略させていただきました)。
『個人通信 萌』第39号(2013年春の号)
『個人通信 萌』は、伊藤啓子の「個人通信」誌である。とはいえ、毎号、伊藤の詩の雰囲気を的確に捉えて伝える(伊藤の詩を「サポートする」という表現が適切と思われる)モノクロームの写真が添えられており、「制作 書肆犀」の記載が表紙にある。伊藤一人の手になるものではなく、コラボレーションで制作されていると考えてよいだろう。
伊藤の詩2篇「川べりの家」「雨の合間に」とエッセイ1篇(無題)を読むことができる。
2篇の詩は、どちらも読みごたえがある。もし、先に引いた「春祭りの頃」と、今回の詩2篇を並べて、3篇の詩の中でどの詩がいちばんよいと思うかとアンケートをとれば、いちばん多く選ばれるのは「川べりの家」で、「春祭りの頃」と「雨の合間に」は、好みによって同数程度に分かれるのではないかと、私は想像する。申し訳ないくらいに勝手な想像だが、そのように想像する理由は、それなりにある。怪異譚的な雰囲気を漂わせながら、「異界」の存在をリアルに感じさせる、という、これまでの伊藤の詩の本流(と私は考えている)につらなり、その点で伊藤ならではの持ち味・伊藤の伊藤らしさがいちばん発揮されているのが、「川べりの家」だからだ。
2篇の詩のうちの1篇を、全て引用することはためらわれる。しかし、詩の「紹介」がこのホームページのねらいの一つであり、丁寧に感想を述べていこうとすると、結果的にほぼ全文を紹介することになりそうなので、全文の引用・紹介をおゆるしいただきたい。
以前の伊藤の詩には、「異界」の表現が目立っていた。詩集『夜の甘み』(2010年、「港の人」発行)に収められているは、「異界」の表現が前面に出た詩である。
「川べりの家」は、そうではない。展開されているのは、「白鷺温泉」の日常の世界である。第一蓮の8・9行め「おばさんがいない時/だれか来たことは一度もない」が、奇妙で、「異界」の雰囲気を漂わせるが、それとて、「異界」を表現しているとはっきり言うことができるものではない。
「川べりの家」では、「異界」が日常の世界の背後に収まっていて、前面に出てこない。「首洗い場」や「首なしの地蔵様」、「ひきまわし」という地名が、土地の歴史を表現し、あわせて、日常の世界の裏側にひそむ「異界」の存在を思わせるが、第一連から最後の連まで、表現されているのは、あくまで「白鷺温泉」の日常の世界である。最後の連の4行「「ひきまわし」と地名のついた土地で/ひとびとが/川の音を聞きながら/おだやかに暮らしている」は、この詩における、日常の世界と「異界」の位置関係をよく表している。
この詩を読むと、伊藤の関心は、「異界」そのものの表現から、「異界」と背中合わせに展開される日常の世界の表現へと移ったかのようにも思われる。もちろん、この詩1篇のみをもって判断することはできないが、もしそうした変化が持続的で今後も続くものであれば、それが意図的な変化であれ、自然な展開であれ、今後が楽しみである。
ところで、「白鷺温泉」は、おそらく、実在のものではない。私は、山形県の内外を問わず、地理や地名に、たいへん疎い人間なので、間違っているかもしれない。もし間違いであればたいへん申し訳ないことになるが、私が調べた限りでは、架空のものと判断される。愛知県豊田市に“白鷺温泉”という名の温泉はあるが、そこのことではあるまい。山形県内では、飯豊町に「しらさぎ荘」という浴場があるが、「株式会社飯豊町産業開発公社」によって運営されているもので、そこでもあるまい。県内ではもう一カ所、湯田川温泉に「しらさぎの湯」という足湯があるが、まさか、そこではないだろう。
モデルとなった場所があるかもしれないし、もしかしたら、添えられている写真がその場所を示しているのかもしれないとも思うのだが、私は、写真を見ても、それがどこなのか、まったくわからないので、何とも言えない。
「白鷺温泉」は架空の場所であり、したがって、この詩に表現されていることがらは、基本的に、作者の想像力の産物と考えられる。もちろん、もとになった体験や、見聞、知見は、事実としてあるだろうが、それらを統合して、この詩に表現された「白鷺温泉」を作り上げたのは、作者の想像力であろう。
そのような、「虚構」の詩、「つくりごと」の詩を、私は、優れた詩として受け入れることはできない、と言いたいのでは全くない。
問われるべきは、 事実かどうか、ではなく、話主(その詩の発話主体、詩中の“わたし”)としてその詩を読んだときにそのことばを自分のことばとして受け入れることができるかどうか、受け入れることができるだけのリアリティ(真実み)が確保されているかどうかである。その点で、伊藤の詩には、十分にリアリティがある。第一連の12行め~16行めの「よろず屋」のようすは、山すその小さな町などにいかにもありそうだ。それに続く2行「ここではどの家も/鍵をかけて出掛けたりしないのである」は、少し前までは日本ではあたりまえだったが現在では普通でなくなっている状況を表現していて、その点で一種の「異界」の雰囲気を醸し出すことにもなっている。リアリティという点では、これもまた、山すその小さな町などではありそうなことで、十分だ。
以後も、最終連まで、リアリティの確保に問題はないと考える。ただ、一カ所だけ、第一連の4~6行め「前に教えられた通り/入浴が三百円、部屋にあがれば千円、ビールは五百円/子どもの留守番のように唱えながら」は、秀逸なことばの使い方である一方、リアリティという点では問題が残ったように思う。
秀逸なのは、「言外のことを表現する」ことばの使い方である。これは、先に、「春祭りの頃」をとりあげたときにも、伊藤の詩の優れた点として述べたことだ。「入浴が三百円、部屋にあがれば千円、ビールは五百円」ということばは、そこが、飲み食いに提供するものとしては「ビール」しか置かず、「部屋にあが」ることがいささか“ぜいたく”となるような、小さな浴場であることを、言外に表現している。「おばさん」が一人できりもりしていることを考え合わせれば、そのことは確信してよいことだろう。
一方、リアリティという点で問題が残ったのではないか、というのは、次のような疑問をもってしまうからだ。「三年ぶりに」尋ねたのに、値段が「前」と同じだとどうして話主にはわかったのだろうか。もちろん、その場に表示されていたと考えることはできる。むしろ、表示されているのが、普通だろう。しかし、それなら、「子どもの留守番のように唱え」る必要はないのではないか。また、第一連の2・3行め「夕方まで帰るからと/おばさんの書置きがあった」は、浴場を開いたままで「おばさん」が出掛けることはふだんからよくあることで、先に引いた第1連の終わり2行のことばとともに、「白鷺温泉」は、留守番を特に必要としない、人と人との間の信頼関係の上に日常の生活が営まれている場所であることを表現している。そういう場所だからこそ、話主は、おばさんが帰ってくる前に、「橋を渡って/よろず屋に冷たいものを買いに行く」こともできたのだろう。そのことと考え合わせても、「前に教えられた通り」~「子どもの留守番のように唱えながら」の三行には、違和感が残る。
とはいえ、このことは、全体のリアリティの確かさに比べれば、ちょっと切り傷がついた程度の小さな傷である。もしかしたら、私の読みに不足があるのかもしれない。ただ、リアリティの確保という点では少しことばを変えれば修繕できることなので、ぜひことばを変えて、作品のリアリティをより確かなものにしてほしいというのが、私の、はなはだ勝手なお願いである(何をおせっかいに余計なことをとお考えになるのであれば、私には、これ以上何も言う資格がないことは、言うまでもありません)。
全体として、詩は、血なまぐさい歴史の上に、人々が、他人に対して警戒心をもつ必要も感ぜずに、ゆったりとした時間の中で生活している、その場所全体が、ふだん私たちが暮らしている場所と比べれば、一種の「異界」と言えるような、そして、かつては確実に存在していたがいまは確実に失われつつある場所としての懐かしさをも感じさせる、そういう場所(時間と空間)を表現していて、みごとである。
さて、ここからは、伊藤の詩を離れての問題提起である。先に私は、「問われるべきは、 事実かどうか、ではなく、話主(その詩の発話主体、詩中の“わたし”)としてその詩を読んだときにそのことばを自分のことばとして受け入れることができるかどうか、受け入れることができるだけのリアリティ(真実み)が確保されているかどうかである。」と書いた。だが、「虚構」が無条件にゆるされるわけではないのではあるまいか。このことは、以前、ある会合で、高啓(こうひらく)の詩集『女のいない七月』(2012年発行、書肆山田)を話題にしたときにも、述べたことだが(このときの会合については高啓がブログに書いているので、参照していただければと思う)、例えば、宮澤賢治の詩「永訣の朝」において妹の死が実は虚構であったというようなことがゆるされるだろうか。もし虚構であったとき、その詩を私たちは、感動的な詩として受け入れる(あるいは、高く評価する)ことができるだろうか。あるいは、高村光太郎の『智恵子抄』において、智恵子の病が虚構であったとしたらどうだろうか。私は、とても受け入れることはできない。「だますんじゃないよ」としか思えない(ちなみに、高啓の詩集『女のいない七月』は、その点で受け入れることができない詩集ではない。それどころか、2012年に全国で出版された詩集の中でも、最も高く評価されるべき詩集の一つであると、私は考えている。「2012年に全国で出版された詩集」を、私は、寄贈していただいたもの以外はほとんど読んでいない。が、他の詩集との比較によってではなく、いわば絶対評価で評価できるものと考えている。そのことを具体的に述べたくて、5月の連休中にかなりの時間をかけて読み返したが、最終的には論じることをあきらめた。高の頭の中にあって、私の頭の中にないもの、言い換えれば、高が準拠しているのに、私は準拠どころか参照すらできないものが多くて(そして、大きくて)、とても、私には論じることができないと考えたからだ)。
例えば(ばかりで恐縮だが)、このページでとりあげた詩に言えば、佐藤伝の「日々の余白に」において、作者佐藤が実際には「日常を離脱」しての「旅」になどまったく出ていなかったとしたらどうだろう。あなたは、あの詩を受け入れることができるだろうか。私は、受け入れることができる。というか、「旅」自体は虚構である可能性があることを踏まえて、私は、あのように評価した。たとえ、「旅」は虚構であっても、詩に表現さている「危機」は、佐藤にとって真実であり、表現されたことばには、たとえ事実ではなかったとしても真実として受け入れることができるだけのリアリティが確保されていると考えたからだ。では、細矢の詩「夜行列車」において、「Kの死」が虚構であったという場合は、どうだろう。私は、とても、受け入れることができない。細かな事情はさておき、死自体が虚構であったとしたならば、まったく受け入れることができない。詩の「感動」が、友人の死という出来事に完全に依拠しているからだ。
さて、では、どのような虚構であればゆるされ、どのような虚構であればゆるされないのか。あるいは、このような問題の設定自体が間違っているのか。私には、正直、よくわからない。ただ、小説あれば、特にことわりがない場合は、読者は、その内容を虚構として読む。一方、詩の場合、読者は、あらかじめ虚構であることを了解して、前提にして、詩を読むわけではない。この違いは、詩を書く者としては、自覚しておかなければならないと考える。「ことばによる表現は、結局のところ、みな虚構である。ことばは、虚構をつくる道具に過ぎない。」などという考えにあぐらをかいて平気でいるのは、学者や思想家ならともかく、詩人のとるべき態度ではあるまい(以上、敬称を省略させていただきました)。