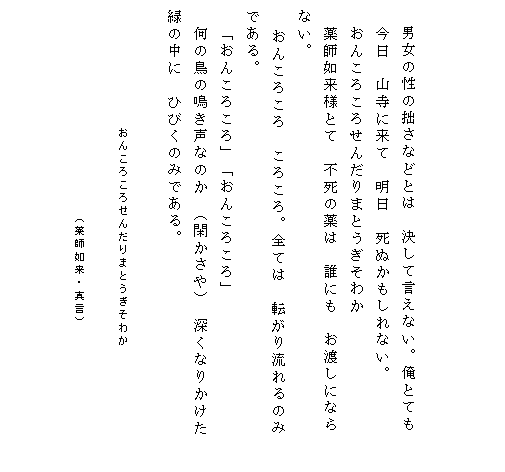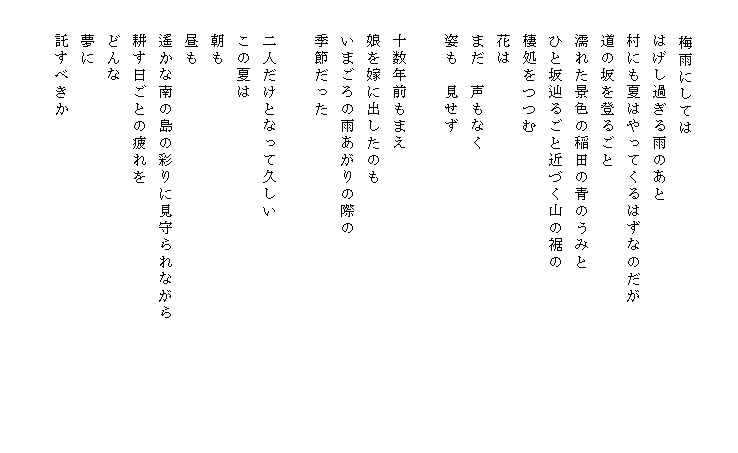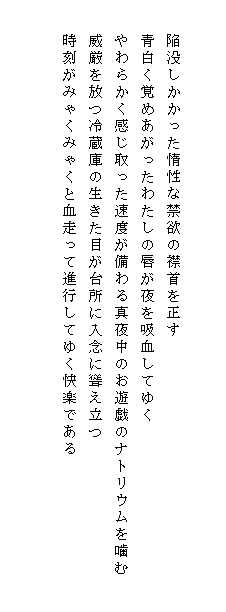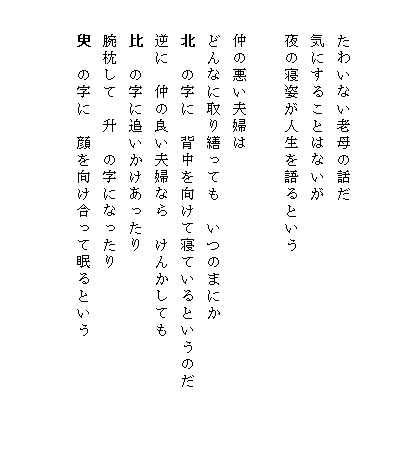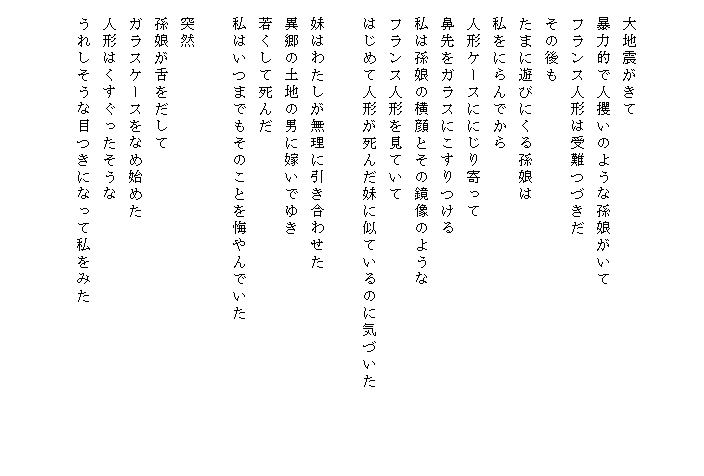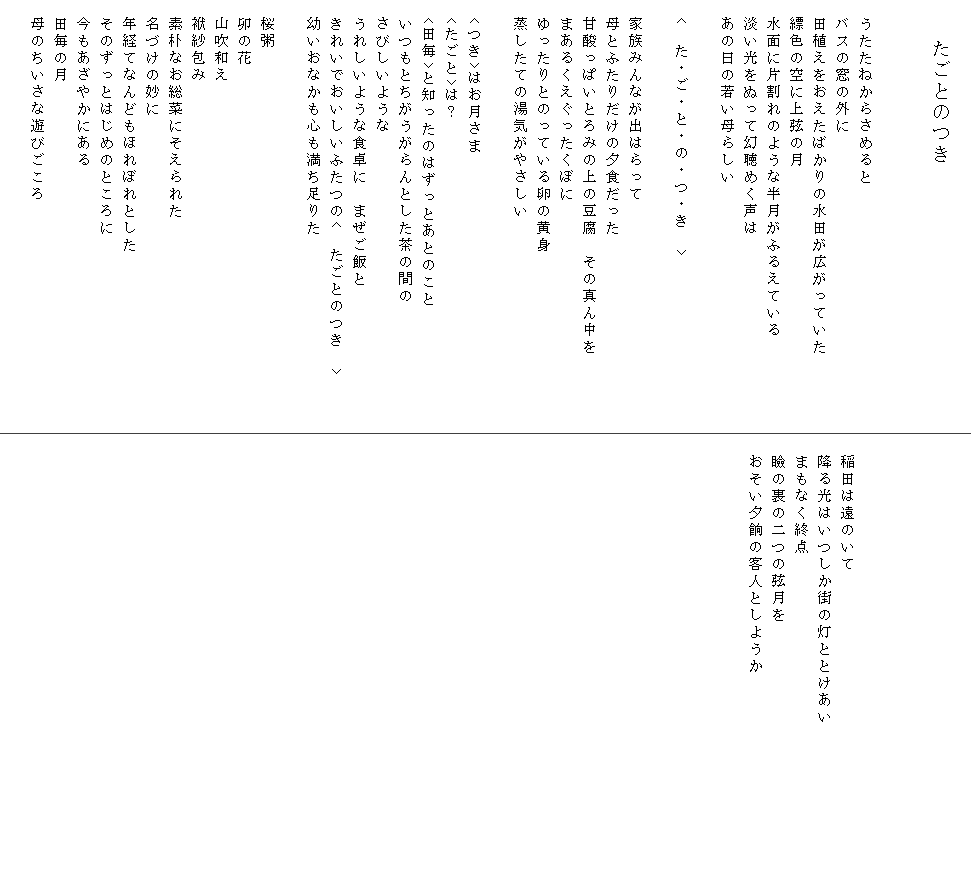阿部宗一郎、菊地隆三、木村迪夫、高啓、近江正人、佐藤伝、佐野カオリ、万里小路譲、山田豊、島村圭一、高橋英司、平塚志信による詩、計12篇を読むことができる。
以下、私にとって特に魅力的な三つの作品について、感想を述べたい。
菊地隆三「
悉皆流転(三)」は、前半と後半に構成が分かれている。前半は、広島に住む、筆者と遠戚関係にある「男」とその「妻」が、二人とも「原爆の災」を逃れながら、それぞれ、山寺(立石寺)に参詣したことをきっかけに亡くなってしまったという出来事を述べて、人生の不条理を実感させて、次のような二つの段落(行分けの詩ではなく、散文詩の形式で書かれている)で終わる。「 この
女も
男と同様 偶然にも原爆の災を免れ 巡りあって
夫婦になった。後に 別々に 山寺に来て 原爆ではない不発弾にでも当たったように 別々に 亡くなった。なぜ どうして? どうして なぜ?/ 分からない。分からないけど 事は このように 起こり このように 進み このように終わった。」
後半は、今年(2013年)が五十年に一度の御開帳の年に当たり、例年にない賑わいを見せた山寺に、御開帳の期間が終わったあと、一人で出掛けた「俺」が、山寺にあって、思いを述べる(ちなみに、私も、御開帳になった御本尊を拝むことはできませんでした。山寺に向かう長い長い車の列は2回ほど見かけましたが…)。「八十歳」の「俺」は、「俺は生きているのだから 少しでも上を目差そうと歩を進めたが 息切れ酷く 途中で諦め 石段に腰を下ろし」て、「広島から山寺に来てその後亡くなった
男女のことを 思う。」。次に引くのは、その直後から詩の最後までの部分。「男女」には「ふたり」、「性」には「さが」、「拙さ」には「つたな(さ)」とふりがなが振ってある。
「おんころころ」という薬師如来真言の響きから(「ころころ」に擬態語を重ねて)、「転がり流れるのみ」という「悉皆流転」の世界観を発想し、さらに、「おんころころ」と鳴く「鳥の鳴き声」を重ねることで、「閑さや」と芭蕉が詠んだ、「寂莫」(芭蕉『奥の細道』より、この言葉も詩中に( )書きで引用されている)たるその場の雰囲気を表現することに成功している。作者の卓抜で軽妙な言語感覚と発想が、読みごたえの詩を作ることにつながっていると思う。
なお、『奥の細道』の山寺来訪時の記述が、詩中の各所に、( )書きで引用されて、詩に複層的な深みをもたらしている。
木村迪夫の「夏の花」。この詩での「夏の花」は、「ハイビスカス」のことである。「ピンク色の/ときには燃える深紅の花弁をつける」、南国の花を代表すると言ってもよいような華やかな花であり、その花が、「こころやすい美人の同僚に促されて/会議のあと/役所の地下通路で買った」ことによって、木村の自宅にもたらされることになった。しかし、木村が、この花を詩中の素材に持ち込んだのは、この花に次のような体験が重なっているからである。「もう何年になるだろうか/慰霊の旅をした彼の島の/街路に咲き満ちていた/褪せることのない花の/色に/身の内に還らない血の色を見たのは」。ここに引いたのは、詩の第三連に当たるが、この表現がなければ、この詩は、後に引用するように、一語の無駄もない効果的な言葉の使い方と、息の長い詩的表現があるにもかかわらず、読みごたえという点では、もの足りない詩になってしまっていただろう。なお、「身の内に還らない血の色」とは、さりげない表現ではあるが、実に卓抜な表現であると思う。例えば「その地で倒れた同胞たちの血の色を見たのは」と表現しても、表現されている内容は基本的に同じである。しかし、読んだときの印象は大きく異なる。「身の内に還らない血の色を見たのは」という表現には、“詩人の想像力”と言うにふさわしい想像力のはたらきがあり、木村の非凡が現れている、と私は思う。
さて、話がわきにそれてしまったが、次に引用するのは、先に引いた表現の直後、すなわち第四連から、最後までである。
「梅雨にしては」で始まる第四連は、文が切れることなく結局は「姿も 見せず」の連用終止で終わり、きちんと終止することなく第五連に続く。以前にも同様な指摘をしたが、その息の長い語り口が、一種の音楽性を伴ってイメージを表現し感慨を伝えている。第四連では、梅雨明け間近な時期の情景とともに農民としての不安が誇張なく表現され、第五連と第六連では、子どもが自立したあとの「二人だけ」の生活の落ち着きとさみしさがこれもまた誇張なく、それだけに心にしみ入るように表現されている。最終の四行「耕す日ごとの疲れを/どんな/夢に/託すべきか」は、子どもが自立したあとの生活の中で誰もがもつのではないかと思われる思いと農の先行きへの心配が入り混じって、とりわけ味わい深い表現となっている。
山田豊「クラゲの時間」。まず最初の四行を引く。「正体不明な時刻である/時刻に、部屋に、人格が潜んでいる/朦朧として醒めた思考を固持し、わたしの人格は海底のようだ/わたしはひとつの軟体として場所に存在する」。おもしろい表現である。ありきたりでなく、自己の感性を百パーセントはたらかせて表現をつかみ取ろうとしている。何より、“絶対にあきりたりな表現はしないぞ”という、その姿勢・態度がすばらしい。そして、そうした態度によって獲得された表現には、新しさと説得力がある。第二連のはじめの四行「わたしは、今起きている/午後1時から4時30分までの闇しか知らぬが/ 闇の体重しか知らぬが/それ以前の記憶は無いに等しい」。この表現もまた、先に引いた表現と同じように、おもしろい。次に、この詩の最終の(第四連の)五行を引く。
全体として、この詩は、私たちが幼い子どものころには感じていて、成長するにつれて感じなくなってしまった、“真夜中”という時間に対する感覚を表現しているように思われて、その点で説得力がある、と私は思う(もっとも、こういうとらえ方は、作者の山田にとってはあまりうれしいものではないかもしれないが)。
また、最初の二行「正体不明な時刻である/時刻に、部屋に、人格が潜んでいる」と最終の二行「威厳を放つ冷蔵庫の生きた目が台所に入念に聳え立つ/時刻がめちゃくちゃと血走って進行してゆく快楽である」が、「時刻」に“生き物の存在(感)”を感じている点で共通しており、表現として首尾一貫している。つまり、一つの詩作品として全体を構成しようという、意識のはたらきがあると思われる。その点でも、この詩は、私にとって、魅力的である。しかし、人によっては、一つの作品としての構成とか、バランスとか、まとまりとか、そういうことは気にせず、もっと感性のはたらきにませて、秩序よりは無秩序を、意味よりは無意味を目指してほしいと考える人もいるかもしれない。そうした点で、山田自身がこれからどのような方向を目指して進んでいくのか。今後の展開が注目される。
最後に、近江正人「寝姿考」も、おもしろく、なるほどと思いながら読んだ。全部で六連から成る詩であるが、最初の二つの連を引く。
以上、敬称は省略させていただきました。
いであつし、いとう柚子、阿部栄子、福岡俊一、芝春也の詩、計9篇と、いとう柚子、芝春也のエッセイを読むことができる。
いであつし「フランス人形の帰還」。「私」の家には、一体の「フランス人形」がある。「飾り台にのせたガラスケースの中」に入っており、「日本でいえば江戸末期の作で/こうしてドレスを着せられて/ヨーロッパ地方の貴族のところを回ったのです/いまでいうモデルなんですよ」と言われる、人形である。詩では、第一連で、その人形が、大震災の翌日、「灰色のガラスの玉がすこし動いたらしい/寄り目になったせいか/ストーカーのように狂信的で/それでいてすねているように/私を見つめている/ケースをゆするとハッとしたように/直った」という出来事が語られ、第二連では、遊びに来た「孫娘」に「お嫁に行くときお祝いにあげるからねと/心にもないことを言うといきなりその場で/ひと抱えもする人形を/ケースがらみ持ち上げようとして/ケースだけがはずれて/孫がひっくりかえった」という出来事が述べられる。第三連は、人形それ自体のことと人形への「私」の思いが述べられる。「私」は、人形のことを、「愛らしい顔立ちで/それに知っている誰かに似ているようで」と思っているが、誰に似ているのかまではわからないでいる。次に、第四連の途中から最後まで引用する。
第四連の最後の行「はじめて人形が死んだ妹に似ているのに気づいた」の一行によってこの詩は成り立っている。タイトルの「フランス人形の帰還」も、人形に「死んだ妹」の面影が重なったことによって、人形にとって“ここが帰るべき場所だったのだ”と気づいたという思いを込めたものだろう。「孫娘の横顔」と「その鏡像のような/フランス人形」を一緒に見ることで気づいたということも、「孫娘」と「妹」との血のつながりがそのことに気づかせてくれたということであり、感慨深い。最終連に表現された、それまでとは異なる、「うれしそうな」人形のようすが印象的である。
いとう柚子「たごとのつき」と「六月」は、どちらも“いまはもうないもの”への思いを述べていて、せつない気持ちを実感させる。
「六月」では、「夢の中」で「先年どこでもないところに行ってしまった人」から「まだ宿題はできていないようだね」と言われ、「宿題」=「その人」が作った曲のために「詞」を作ることを思い出す。「―もう曲はできているんだ―/ギターをつまびいて唇が動いたけれど/耳に届くのは風と水音だけ―/―雨がやんだら 見つかるかもしれない/もう行かなければ 舟を待たせているので―//遠ざかる気配の半ばでめざめれば/ふたたび激しくなる荒梅雨の濁音//濃い闇のざわめきをかきわけて/夢の人からの/古い宿題のしまい場所をさがしはじめる」。全部で六連(おそらく)から成る詩。引用したのは、第四連の途中から詩の最後まで。印象的な言葉が続いている。「六月」という梅雨時の情緒をともなって、忘れていた亡き人とのことを思い出すせつなさが実感される。
「たごとのつき」は、次に全文を紹介したい。類例のない内容と魅力をもった詩ではないかと思うからだ。
「田毎の月」は、田の広がりを目にすることのできる地域に住む者が見ることのできる、特権とも言うべき美しい景色だが、この詩は、その実景を描くのではなく、「母」が「遊びごころ」で作った料理の名前からその景色を連想させるという、独自性をもっている。「母」と過ごした、失われた時間が、「さびしいような/うれしいような」そして疑いなく“豊かな”食事時のようすとともに、せつないながらにほのぼのと思い出される。
先に私が「類例のない内容」と述べたのは、実は、この詩に表現されている“食”のあり方、その“豊かさ”である。それは、かつて、そういう“食”の文化をもった家庭のうちにあり、そうして、いまでは、経済的にどんなに豊かな家庭からも、もしかしたら失われてしまったのではないかと思われるものである。「スローフード」という言葉があるが、この詩で表現されている“食”のあり方には、スローフードの、“ゆっくりとした”時間のあり方に加えて、文化的な洗練・優雅がある。その“豊かさ”が、この詩の内容的な豊かさにつながっている、と私は思う。
最終連には、誇張されない孤独と、漢詩のような、すなわち、孤独のうちに風流を愛した、かつての文人の心の持ち方のような趣がある。その点も、私にとって、この詩の魅力となっている。
最後に、いとう柚子のエッセイ「子供たちに託するもの」は、冒頭で紹介されている、北村真の詩「未来」とともに、大切で、かつ重い内容をもっている。「未来」に向けて「子供たちに託するもの」。一言で言うならば、それは、「時に残酷な仕打ちをする現実に立ち向かい、前に進む強さ」ということになるだろうか。このように書いていて、自分にはそれがあるのか、と自問してしまう。