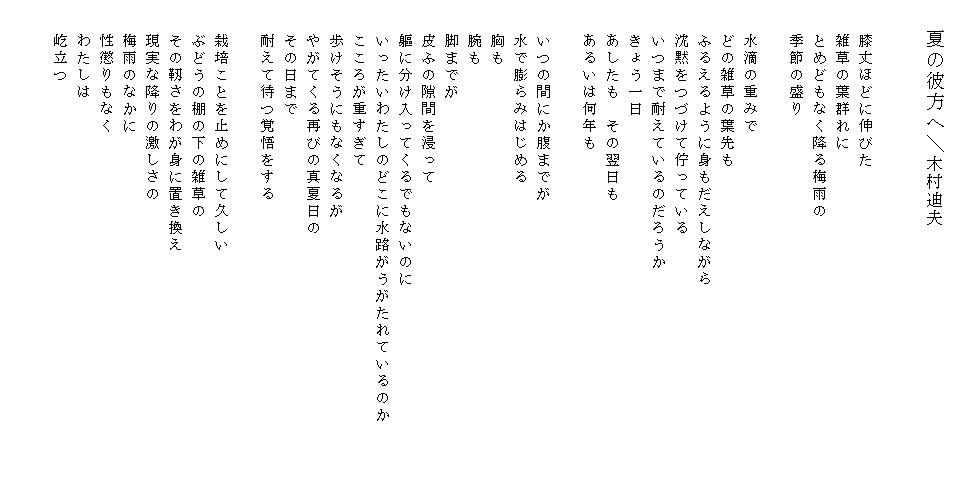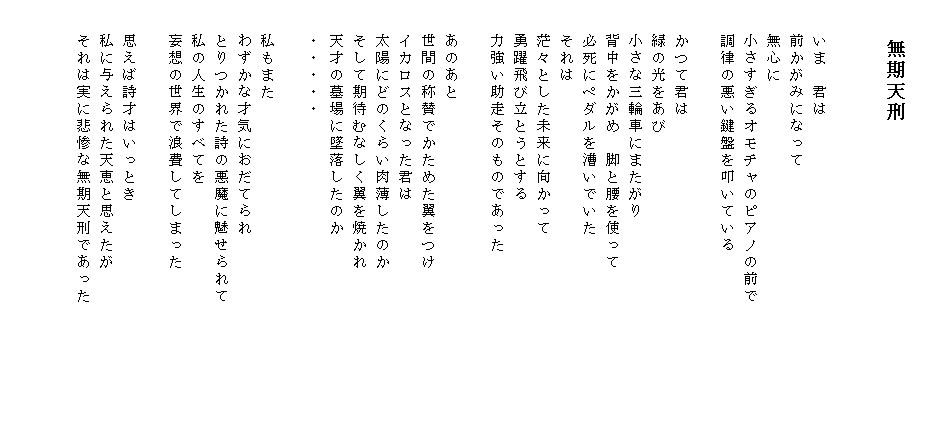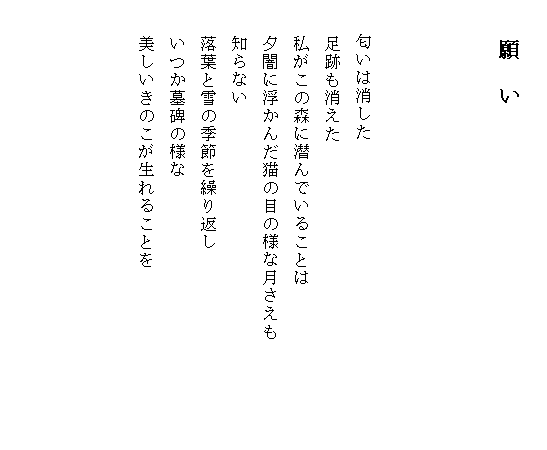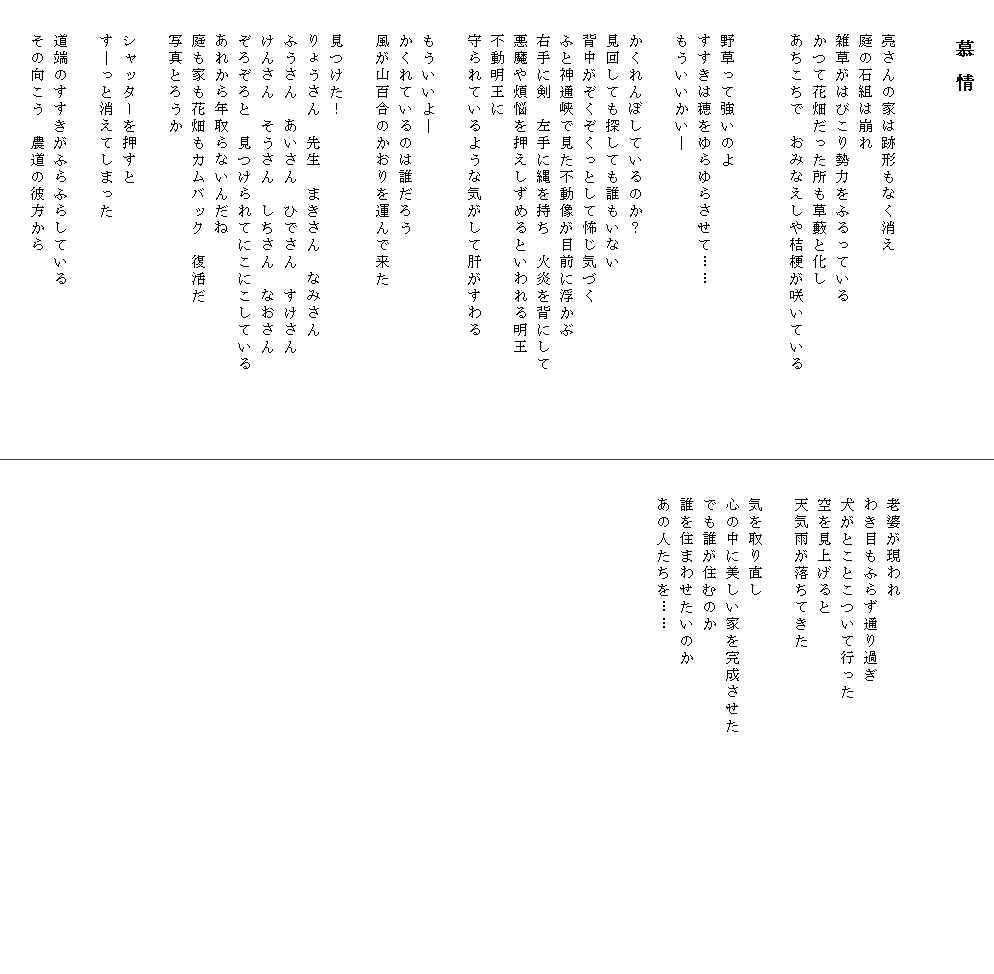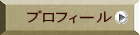

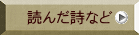
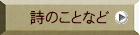
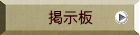
詩誌を読んで〈2013〉 その4
『山形詩人』第83号(2013年11月20日発行)
高啓、阿部宗一郎、佐藤伝、木村迪夫、佐野カオリ、万里小路譲、久野雅幸、近江正人、山田豊、高橋英司、菊地隆三による詩、計11篇を読むことができる。
自分が所属する詩誌なのでほめ言葉を述べると「われぼめ」となり、適切でないという考え方もできるかもしれない。しかし、客観的な立場から言って、この詩誌は読みごたえのある詩がそろっていると言えるのではないだろうか。載っている詩の性質がそれぞれ異なり、どれも個性的で、バラエティに富むという点も、まとまりがない・全体としてある立場や考えを主張していないという点でもの足りないと考える方もあるかもしれないが、「印象に残る詩に出会える可能性が大きい」という点では一つの長所となっている。
自分自身や日本社会の現実と正対し、「自分の立ち位置」を確認・表現している詩が多い。
高啓「バックスタンドの憂鬱」、阿部宗一郎「日米もし戦はば」、木村迪夫「夏の彼方へ」、近江正人「貼り紙」、山田豊「出口」、高橋英司「恋について」、菊地隆三「悉皆流転(四)。以上の詩は、詩の最後の部分において、「自分の立ち位置」(自分はどのような立場に立つか、自分はどういうものであるか)を確認・表現して終わっているという点で、共通している。
とはいえ、もちろん、各詩において、作者が見出し、表現している「自分の立ち位置」は、それぞれ異なっている。そして、各詩人に「自分の立ち位置」の確認・表現をうながした動機(=問題意識)もまた、それぞれ異なっている。表現という点でも、それぞれに、特色があり、ありきたりでなく、個性的である。
問題(それぞれ、問題として広く共有されるものだ)の切実さと、「自分の立ち位置」を表現(=表明)するにあたっての毅然とした(ユーモアを含んでいたり、がむしゃらであったりもするけれど、「毅然とした」という点では共通していると思う)態度、個性的で、読みごたえのある表現。そうしたものを、どの詩も、もち合わせていて、ぜひ多くの人に読んでもらいたいと思った。
ここでは、木村の詩(全文)を、引いておきたい。私がここまで述べてきたことが、偽りでも大げさでもないことを感じとってもらえればと思う。
(第一連の「雑草」に「くさ」、「梅雨」に「あめ」、最終連の「栽培」に「つくる」、「現実」に「あらわ」、「梅雨」に「あめ」、「屹立(つ)」に「た(つ)」と、ルビ。)
さて、「自分の立ち位置」を確かめているという点では、佐野カオリ「わたしの好きな浮舟ⅡⅩ」と万里小路譲「脳裏の春」も、共通していると言えるように思う。
佐野の詩では、「ときどき 現れては消える」「私を取り巻く この不思議な王国」について、次のような表現があって、詩が終わっている。「月日がたち あるとき/ふと 気がついたのだ/つまり 橋はふたつあ/って 行きと 帰りと/別々の橋を渡っていた/のだと 気がつけばを/を道はちゃんと開かれ/ていて そのときいき/なりふしぎの王国を放/り出される 私 どう/して気がついたりした/のだろう 戻ろうか /竹の花 咲いた」。「どう/して気がついたりした/のだろう 戻ろうか」に、幻想と現実とのあわいにあり、その間を行き来していたい、と望む「自分の立ち位置」の確認が行われていると考える。
万里小路の詩は、五句の俳句を柱に据えて、構成されている。その五句のうちの最後の句「惑星空間の片隅で聴く雨の音」は、先に述べた7人の詩とは、視点のとり方が大きく異なるけれども、「自分の立ち位置」を確認しているという点では、共通していると言えるように思う。
佐藤伝「虫森」は、「自分」ではなく「周囲の世界」に目を向け、そこに〝見出した世界〟を表現している。「空気はより鮮明に澄み風は梢を吹き抜け/乾いた甲虫の匂いのする昼下がり/夏だけに現れる現象/虫森の前にバス停が立った」(第一連3~6行目)と、「虫森」の出現が表現され、「季節を縁取る風物詩/祖母がこどもの頃は立て札であった/木々の緑のざわめきにうたた寝する午後/夏の休みに都会から来た少年が/捕虫網を持ったまま森に入り消えた」(第二連全行)のように、「虫森」の性質が表現され、「みどりの田圃の真ん中の/舌切りや花咲か民話の原形があるという/美しさと残酷さを秘めた/神隠しの伝説のある土地/知らぬ間にバス停は消え秋が降る」(最終連にあたる第六連の全行)と、詩は閉じられる。人間の生活空間と自然が接することによってもたらされる、見通すことのできない「世界の奥行き」を表現していて、リアリティがある。
私は、この号から、本名ではなく、「久野雅幸」の名前を使うことにした。「 」(かぎかっこ)の世界を表現した詩を載せているが、他の方々の作品を読むと、「自分と社会の現実をきちんと見つめ、そこから目をそらさないようにしなさい」と叱られそうである。
最後に、編集者の高橋が、「後記」で、詩の感想や批評を述べることの〝難しさ〟を述べている。他人に読んでもらうために詩集や詩誌によって詩を発表するのだから、読者は、「自分なりにきちんと読んだ」という自覚があれば、読んだ詩について感想や批評を率直に述べることに遠慮はいらないように思われる。しかし、そう簡単に割り切れるものではないと高橋は述べる。「筆者は、過去に、正直な感想を述べて、相手から憎まれた経験がある。(一文を省略)だから、遠慮が生まれ、口を噤む。」と、高橋は述べている。私も、高橋と同様な経験がある。
根拠のない批判は、慎まなければならない。それは、「悪口」と同じであり、作者を傷つけるだけである。根拠がなくほめることも、慎むべきである。それは、作者が詩人として成長していく上でマイナスにはなってもプラスにはならないだろう。個人的な事情や好悪を、根拠のように扱って、作品に対する意見を述べることも、当然、避けなければならない。こうしたことは、肝に銘じているつもりである。
また、「批評」とまでは言えない、「感想」に過ぎない場合であっても、単に「よかった」で終わるべきではないとも思っている。「どこがよかったのか」、「なぜよいと思ったのか」、「根拠」とまではいかなくとも「理由」は添えたいと思っている。
加えて言えば、ここは、ホームページ上であり、広く開かれた場であるから、「共有する価値のない批判的なもの言い」はしないようにしている。
もとより、特定の人物を、個人的な好悪によって、持ち上げたり、おとしめたりするつもりはいっさいない。
しかし、それでも、私がここでさまざま述べることによって、あるいは、述べないことによって、不本意に思われる方はあるかもしれない。そういう場合は、しょせんは一読者のすることであるから、ご容赦願いたい。どうしてもゆるせないという場合は、ご面倒でもお知らせいただきたい。できるだけ誠実に対応するつもりである。
社交的な配慮によって、〝不正直〟になってはいけないと思う。「文学の場を社交で終わらせたくはない。」という高橋の言葉に、同感する。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『E 詩』第23号(2013年12月25日発行)
いであつし、福岡俊一、安達和明(筆名:安達敏史)、阿部栄子、いとう柚子、芝春也の詩、計7篇と、安達和明、芝春也のエッセイ、計2篇を読むことができる。
巻頭の詩、いであつし「無期天刑」に、一種の衝撃を受けた。全文を引かないと、その「衝撃」を説明できないと思われるので、次に全文を引きたい。
詩を書くことに時間を費やしている者で、第四連と第五連に表現されている「私」の思いに、まったく共感することができない者は、稀なのではないだろうか。「詩才」、あるいは“詩を書いていると時がたつのも忘れることができる”ということが、「天恵」ではなく「天刑」と思われる経験をすることなしに、詩を書き続けている者は、わずかなのではないだろうか。
「詩が書けない」と思うとき、「時間を費やして詩を書き、金を使って発表する、そのことにどれほどの意味があるのか」と疑問に思うときは、長く詩を書いている者であれば、一度は経験しているのではないだろうか。そういう経験をしながらも、しかし、詩を書くことをやめることができない。だからこそ、「無期天刑」なのだろう。
私事を述べることになるが、私の場合は、高校時代から詩を書き始めて、
今日に至るまで詩を書き続けている。しかし、大学を卒業し、職を得て数年がたつまで、一篇の詩も完成させることができなかった。イメージは浮かんだ。思い浮かんだ詩句を書きとめてはいた。しかし、そうしたイメージや詩句を、一つの詩としてまとめ上げることができなかった。その間、大学の3年目のころだったろうか、「自分には詩を書くことができないのだ」と思い、イメージや詩句を書きとめ、書き綴っていたノート数冊を、すべて破ってゴミ箱に捨てた。
それでも、再び詩を書き始めたのは、月並みと思うが、詩を書くことが好きで、詩を書いている時間が自分にとって最も生きがいを感じることのできる時間だったからだと思う。その後も、ノート上でいたずらに推敲を繰り返して数年がたち、「イメージやことばをまとめて一つの詩を(作品としての良し悪しはさておき)完成させることができる」ようになったのは、ワープロを使い始め、2ヶ月間の海外(アメリカ合衆国インディアナ州)での生活を経た、1994年以降のことである。年齢は、30歳をすでに越えていた。
現在は、自分が書く言葉にどれほどの“需要”(自分以外の人にはらきかけ、その人に受け入れてもらえるだけの魅力)があるのか、不安に思いながらも、「自分以外の、できるだけ多くの人に読んでほしいと(自分では)思える詩」を書くことができている間は、たとえそれが結局は自己満足に過ぎないと言うべき結果、大きな勘違いであったと言うべき結果に終わるものであっても、詩を書き続けるつもりでいる。
いでの詩に話をもどそう。第四連と第五連の表現が、個人的な感慨の吐露に終わらず、迫真性をもって読み手の心情にはたらきかけるのは、それが書き手と読み手の体験に裏打ちされたものであるからということももちろんあるが、その一方で、第一連から第三連に表現された「君」のイメージが読み手の心情に強い印象を与えるからだろう。
「君」が「私」とどういう関係にあるのか、何歳ぐらいなのか、そもそも「君」は実在する人物なのか…、不明であるが、与える印象は強烈である(表現に即して考えれば、「君」は「私」の子どもか、もしくは、血縁のある者と思われ、年齢は、10代後半から20代前半と想像するのが適当と思われる。また、表現のもつリアリティ、特に第二連のリアリティは、「君」の実在を感じさせる。しかし、いずれも、確信はもてない)。たとえ事実ではなくとも、事実と感じさせるリアリティがあり、また、事実として十分にあり得ることである。何より、「君」の姿は、「芸術的な活動」の魅力に「とりつかれた」人間であれば、誰もがそうなり得るものであるという点で、心に迫る。
とはいえ、もしかしら、私は、この詩を書いた、いでの悲痛な心情に対して、いわずもがなの、あまりに気楽なもの言いをしたかもしれない。もし、そうであれば、ご容赦願いたい。
安達敏史が、本名「安達和明」の名前で、詩「願い」を載せている。今後も、本名を使っていくとのこと。
「願い」は、よい詩だと思った。個人的には、こういう詩をもっと読みたい。残念なことに、誌上では、四行目に明らかに脱字がある。編集発行人の芝に確認して、訂正した上でこのHPに載せることを認めてもらった。次に、全文を載せたい。
三行目の「私」は、当然「きのこ」(の胞子)だろう。短い詩だが、夕方から夜へ移ろうとする時の森のようすが、はっきりと目に浮かぶ。静寂と深さが、十分に伝わってくる。季節は、晩秋から初冬、“きのこ”の生える時期が終わったころと読むのが、適当だろう。「森」でしかありえない世界が表現されている。四行目が、この詩の世界に、独特の緊張感と彩りを与えている。「願い」というタイトルも秀逸だ。
この詩では、詩によってしか表現されえない世界が、時間と空間が、表現されている。そのことを、私は、高く評価したい。詩を読むことの楽しみを実感させてくれる詩であり、少し大げさなもの言いになるが、なぜ詩が必要なのかという問いに答えてくれる詩(「こういう世界は詩によってしか表現できないからだ」という答え方で)、すなわち、詩の存在意義を知らしめてくれる詩だと考える。
安達のエッセイ「近況」によれば、健康状態が思わしくないようだが、私は、こういう詩をもっとたくさん読みたい。そして、自分では詩を書かない者も含めて、そう思う者、すなわち「詩の愛読者候補」とも言うべき者は、いまの日本にも、実は、少なからず存在するのではないかと、私は考えている。
阿部栄子「慕情」も、繰り返して、何度も読みたいと思わせる詩だ。作者の、心からあふれるほどの思いが、実感として読み手に伝わってくる。
じっくりと読み進むうちに、涙をこらえる必要があった。その原因は、内容にあるとともに、表現にもある。
奇を衒う表現はないが、平凡ではない。どの一語をも削ることができないような、無駄のない表現。第五連の「りょうさん」に始まる、名前の連呼も、なされるべくしてなされている。視点の変化が多く、しかも効果的だ。
いでの詩も、安達の詩も、阿部のこの詩も、散文的な「説明」がない。そのことが、詩の表現としての、言葉の密度を高めていると考える。
芝の詩「ラーメンを食べに」は、芝のエッセイ「エロスの詩①」にも通じるところがあり、“簡単には老いないぞ”という気概が感じられる。まさか、一つの詩誌から、四つの詩を全文引用するわけにはいかないと思うので、全文の引用は避けるが、特に読みどころと思われる点について述べたい。
「人間は逆立ちした植物だ」という「プラトン」の言葉を引いての、終りまでの11行。「ただ 恥じらいの生殖器を/花のように晒さない/オホホ/寒々と林立する/晩秋の千手観音の街路(久野注:「枝葉を剪り落とされ」た「プラタナスの街路」のこと)を/直立歩行して/これから/熱々のラーメンを食べに行く/口から たっぷり/栄養を補給するのだ/冬にそなえて」。味わい深い表現であると思う。とりわけ、最後の1行「冬にそなえて」の含意。冬に備える樹木の姿を背景にして、人生における「冬」の時期を含意する表現であることは間違いあるまい。加えて、昨今の政治の状況を考えるとき、「冬の時代」までを見据えた表現であるように思うのだが、どうだろうか。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)