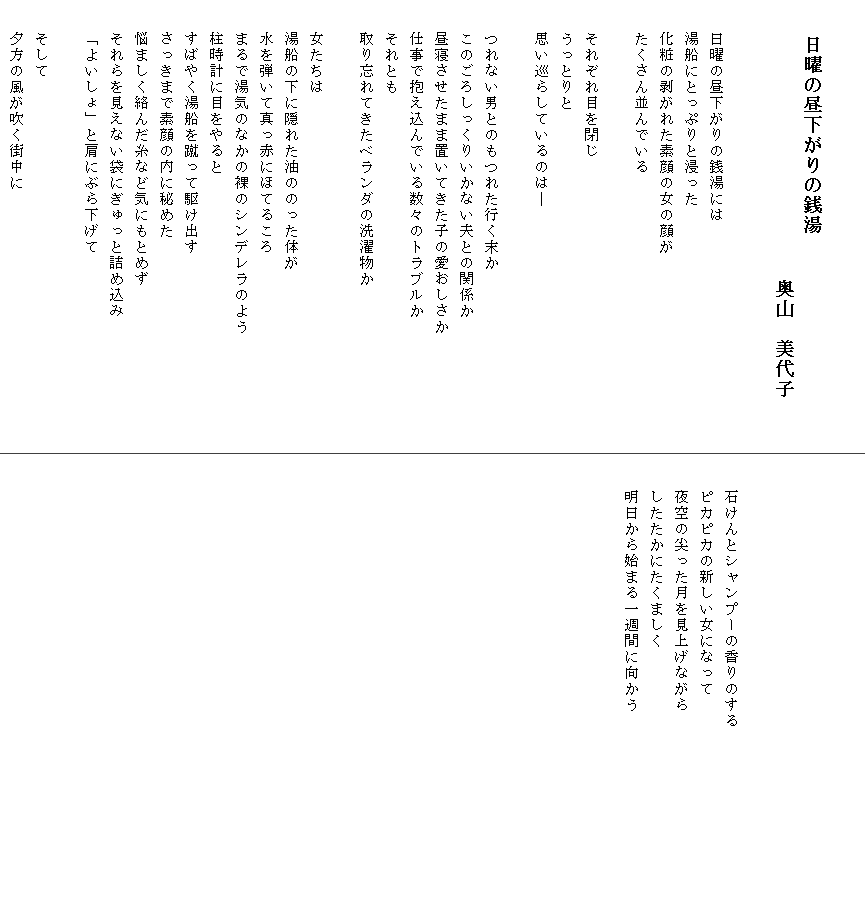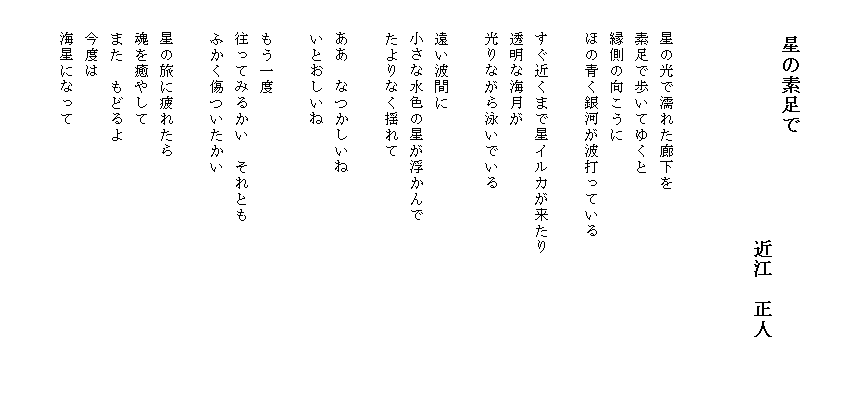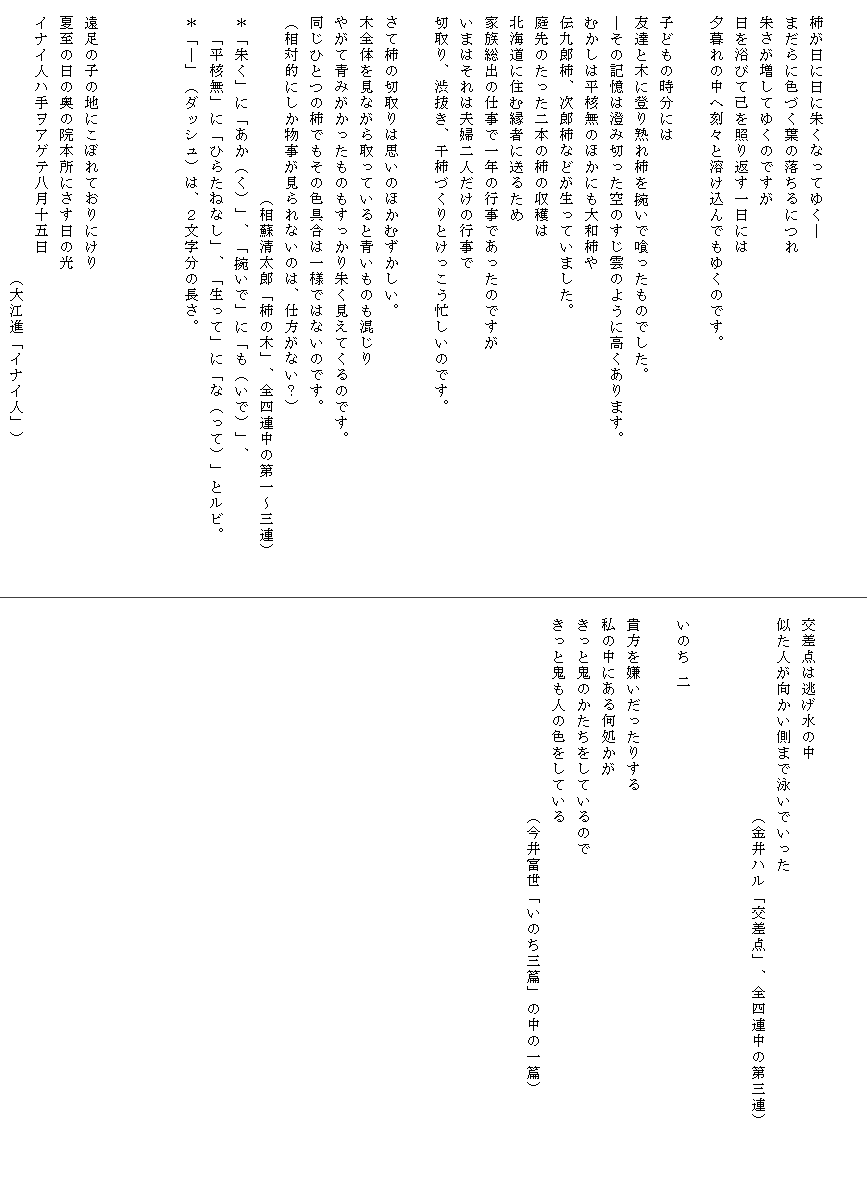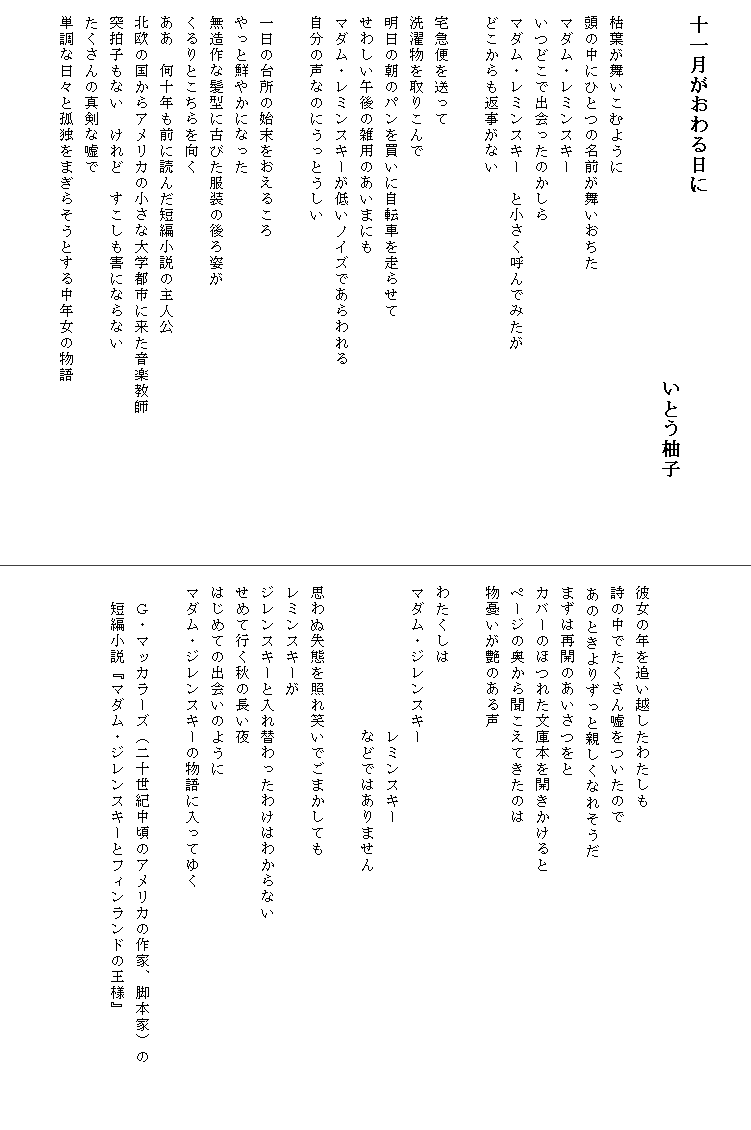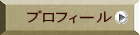

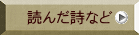
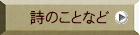
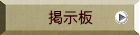
詩誌を読んで〈2015〉
『表象』第58号(2014年5月3日発行)、第59号(5月21日発行)、第60号(6月1日発行)、第61号(6月29日発行)、第62号(8月15日発行)、第63号(10月10日発行)、第64号(11月3日発行)
第58号。万里小路譲による、「浅茅生の小野の篠原忍ぶれどあまりてなどか人の恋しき」(「小倉百人一首」の39番の歌。先に、「後撰和歌集」に載る。作者は「小倉百人一首」では「参議等」。紛らわしいが、「参議」が役職で、「等(ひとし)」が名前。「後撰和歌集」では、「源ひとしの朝臣」と、名前が載る)の和歌の鑑賞と、「コパカパナコⅡ」という筆名の詩人(万里小路の文章によれば、山形県寒河江市在住)の詩集『ブルー・イソギンチャク』(1996年、近代文芸社)と赤塚豊子の詩「アスファルトの道」、比暮寥の『香華散りゆく ―亡妻愛霊の記』の紹介と鑑賞・批評・感想が載る。
「コパカパナコⅡ」という詩人の存在を知ったことが、私にとって大きな収穫であった。短い詩が3篇紹介されているが、どれもおもしろい。万里小路が述べている通り、その詩は「鋭い内省をさりげなく示して」いて、そこでは「常識や固定観念が疑われている」。ことばの使い方も、軽妙で、よいセンスがあると感じられる。1篇だけ、ここでも紹介しておきたい。「そうすれば と 軽く言う/そうするっ と 軽く言う/そうすることは/とても重いことなのに」(詩「かるおも」全行)。
第59号。詩は、奥山美代子「日曜の昼下がりの銭湯」。万里小路による、茨木のり子の詩「清談」、「知」、石垣りんの詩「家」の鑑賞が載る。万里小路による、3篇の詩の鑑賞は、詩も文章も読みごたえがあり、詩からも文章からも教えられることが少なからずあった。奥山の詩は、実感を離れない、そして、実感で終わらない、よい詩だと思った。次に、紹介したい。
起(第1連)・承(第2・3連)・転(第4連)・結(第5連)の、安定した構成に乗って、「日曜の昼下がりの銭湯」のようすが、過不足のない表現でとらえられている。「明日から始まる一週間」に向かう、元気をもらえる詩であると思う。
第60号。詩は、奥山美代子「山の残像」。万里小路による、「安全地帯」のアルバム『ワインレッドの心』、松任谷由実のアルバム『Neue Music』、茨木のり子の詩「知らないことが」の鑑賞・感想・批評が載る。茨木の詩が、収められいる詩集(第一詩集『対話』1955年)出版から数えても60年がたつのに、少しも「古さ」を感じさせないこと、特に最終連「精密な受信器はふえてゆくばかりなのに/世界のできごとは一日でわかるのに/〝知らないことが多すぎる〟と/あなただけには告げてみたい。」が、情報社会の今日にあってますます“ことばの重みがましていく”ことに、驚きに近い気持ちを感じた。“何をいかに表現するか”で詩の価値は決まると言ってよいように思うのだが、茨木の詩が、“社会のあり方”という時とともに変化していくものを見つめる視点をもちながら、“何を表現するか”という点で、“時がたっても変わらない問題”をとらえて表現していることに、茨木の詩人としての(社会学者等とは異なる)まなざしの鋭さを、あらためて感じた。
奥山の詩「山の残像」は、よい味わいのある詩であると思う。ただ、私としては、第1・2連の設定をなくして、第3・4・5(最終)連(のイメージ)を生かすように再構成したほうがよりよいのではないかと思うのだが、どうだろか。「振り返ると/後からぴったりとついてきた風景達が驚いて/瞬時に夜のしじまに落ちていく//はずむ心を抑えながら/残してきた心の半分の行方を探しに/体の中に持ち帰った/五月の光に濡れた山という/一冊の絵本の中に入って行く」(詩「山の残像」、第4連・最終連)。
第61号。詩は、久野雅幸「天使のいる町で」。万里小路による、星川清躬(ほしかわきよみ、1896~1940、山形県鶴岡市出身)の詩「春風 ―亡兄の繪に歌へる」、「魚塘の家 -nach
“Weiherhaus” von Albrecht Duerer-」の紹介・鑑賞・批評、ブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団演奏のマーラー交響曲第1番「巨人」のレコード・CDの鑑賞・批評が載る。
星川の詩には、あらためて読み直され、再評価されるべきだと思わせる、魅力がある。紹介されている2篇の詩は、ともに絵画をもとにして表現された詩であるが、「絵画を言語の世界へ転移させる手法が清躬の天才を伝えている」という、万里小路のことばに同感である。
第62号。詩は、近江正人「百合」。万里小路による、池田瑛子の詩「海」、「海辺」、石垣りんの詩「弔辞」の紹介・鑑賞・批評が載る。「家持 石黒信由 遙かな祖たちも仰いだ立山/くりかえし くりかえす 波の音/生れていなかった昔の海辺に/夕日が射している/幼い母が母の母とはしゃぎながら走ってゆく//巻貝は子らの夢の渚にうずめよう/遠い未来 海の響きに引き寄せられ/故郷の海に逢いに来るだろう/そのとき私は大欅の樹に棲む鳥であればいい」(池田瑛子「海辺」、第3・4(最終)連)。池田の詩、石垣の詩、万里小路の文章、みな読みごたえがある。
近江の詩「百合」は、まさに“百合そのもの”を表現しようとしている(ほかの印象的なできごとと合わせたりすることなく)。私は、第1連だけでも、魅力的な四行詩として成り立つように思ったのだが、どうだろうか。「梅雨空の下/百合のつぼみが ふくらんだ/合掌した手のなかに/ひかりを 包みかくしてでもいるように」(近江正人「百合」、第1連)。
第63号。詩は、近江正人「星の素足で」。万里小路による、加藤千晴(1904~1951、山形県酒田市出身)の詩「流れに寄せて」、「静かなこころ」、茨木のり子の詩「古潭」の紹介・鑑賞・批評が載る。加藤千晴の詩は、「加藤千晴詩集刊行会」(発行所:酒田市千石町、齋藤智)によって『加藤千晴詩集』(2004年)と『加藤千晴詩集Ⅱ』(2005年)の二冊の詩集にまとめられているが、万里小路がこの号で紹介している詩「静かなこころ」は、そのどちらにも収められていない。『加藤千晴詩集Ⅱ』の刊行後に、齋藤智によって発掘されたもので、「完全に失明したあとの生涯最後の作品であろう」とのこと。「静けさと平穏を祈る内省そのものが言葉となる」、「内省そのものが吐息となり言葉となり、詩篇を構成する」という万里小路のことばに、同感である。「ああ このひととき/生きている 生きている/ただ安らかに/ただ充ちたりて/静かなこころよ/われに在れ われに在れ/生きる日の/この神のたまもの」(加藤千春「静かなこころ」、最終連)。
近江の詩「星の素足で」が、印象的である。次に、紹介したい。
ルビは付されていないが、「海月」は「くらげ」、「海星」は「ひとで」と読んでよいだろう。
私は、しばらく、この詩の“文脈”をつかめなかった。たいへん幻想的な詩であることは、一読してわかる。私がわからなかったのは、第4連と第5連のことばを、どう解釈すればよいのか、ということだった。なぜ「なつかしい」のか、「いとおしい」のか。「ふかく傷ついた」とは、どういうことか。判然としなかった。それが、「わかった」と思ったのは、第3連の「水色の星」を「地球」と考えて読んだときである。つまり、この詩は、地球から宇宙を見るという“文脈”の中ではなく、宇宙のかなたから地球を見ているという“文脈”の中で読むべきなのだ、と考える。そう考えれば、なぜ「なつかしい」のか、「いとおしい」のかが、わかる。第4連のことばも、深い実感のこもったことばとして読むことができる。すなわち、この詩の「話主」(作品中の“わたし”)は、かつて地球で生きていて、いまは、地球を「遠い波間に」見る場所にいるのだ、と考える。特別な設定を考えないならば、話主が、「水色の星」=地球から、この詩の場所に移るきっかけとなったのは、地球での“生”の終わり、すなわち“死”ということになるだろう。そのように考えると、「なつかしい」、「いとおしい」のは、かつて「水色の星」=地球で生きていたからであり、第4・5連のことばは、かつて地球で生きていたときに「ふかく傷ついた」かもしれない者へのやさしい呼びかけのことばとして、読者は受けとめることができる。最終連の「星の旅に疲れたら/魂を癒やして/また 戻るよ/今度は/海星になって」には、深いせつなさがこもる。
私は、宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」を思った。ジョバンニと別れたあと、カムパネルラが行き着いた場所。この詩は、そのような場所を想像させる。そう考えれば、この詩は、「銀河鉄道の夜」を“本歌取り”して、その後日譚を、詩の世界に、いわば二重映しに、想起させる、そういう仕掛けを持っていると読めるのだが、そういう読み方は不適切だろうか。
第64号。詩は、近江正人「水晶の
刻」。万里小路による、茨木のり子の詩「十二月のうた」、「四月の歌」、石垣りんの詩「公共」の鑑賞が載る。
第65号。詩は、万里小路譲「晩秋初冬抄」。万里小路による、「テイラー・スウィフト」と「ステイシー・オリコ」という、二人のアメリカ人女性アーティストとその歌についての紹介・批評、吉野弘とキース・ジャレットについてのエッセイ「死と花あるいは生という幻想―吉野弘とKeith
Jarrett」が載る。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『シテ』第5号(2014年11月25日発行)
今号は、詩が8篇。相蘇清太郎「柿の木」、南悠一「ヒグラシの降る坂」、西方ジョウ「干し柿」、大江進「イナイ人」、早藤たかこ「露天風呂」、金井ハル「交差点」、今井富世「いのち三篇」、阿蘇豊「おれとおれ」。
たいへん魅力的な表現を読むことができる。「詩をとらえよう」「体験の記述や思いの表出にとどまらない、詩としての表現を追求しよう」という意識が強いからではないか、と私は思う。
私が特に魅力を感じた表現を、次に、抜き出して、示したい。
相蘇清太郎の「柿の木」。相蘇にとって、「柿の木」は、“郷土”と“家”と少年期”を象徴するものと言ってもよいようだ。「柿の木」への思いは、自然に“郷土”や“家”や“少年期”への思いにつながる。
第一連。“ものをよく見る目”に支えられた観照と“感じやす心”による抒情とが一つになった、詩的な表現であると思う。「夕暮れのなかへ刻々と溶け込んでもゆく」は、主語を「柿」とする、柿の実が夕日に重なる、情景の表現であるが、“私の気持ちは”を主語とする文脈がひそかに重なる、心情の表現ともなっている。
第二連。三行目の「―その記憶は澄み切った空のすじ雲のように高くあります。」が、一、二行目の「記憶」の、現在の“わたし”にとっての“位置”と“距離”と“ありよう”を表現する、非常にみごとな比喩となっている。加えて、「子どもの時分」に「友達と木に登り熟れ柿を捥いで喰った」ときにも、柿の木の上で、“わたし”はそうした情景を目にしたのではないかと想像させる
構造をもっている。
第三連。実際に「柿の切取り」を体験した者だけが知る“色彩の惑わし”が表現されていておもしろい。
第四連(最終連)は、「書に倦みて燈火に柿をむく半夜」という「柿を好んだ子規の句」が引かれて始まるのだが、私としては、例えば第一連で読むことができるような、詩情が巧みに表現された、詩的表現による締めくくりを読みたいと思った。
大江の「イナイ人」は、12句の俳句(と言ってよいと思う)からなる。 「遠足の子の地にこぼれておりにけり」は、遠足に来た土地で、その土地から「こぼれ」出るように、元気いっぱいに遊び回る子どもたちのようすが目に浮かぶ。季語は「遠足」、春の季語。「夏至の日の奥の院本所にさす光」は、他の季節であれば影が目立つ場所であろうと思われるが、「夏至の日」であるがゆえに影は目立たず、日の光にさらされているような状態の「奥の院」のようすが目に浮かぶ。それとともに、視覚のみにうったえる表現であることがかえって深い静寂を感じさせる。「イナイ人ハ手ヲアゲテ八月十五日」は、“戦争がなければここにいたはずの人たちがいない”ことを不条理として実感させる、奥の深い句であると思う。
金井ハルの「交差点」は、「私」への愛情が足りないと思われる「あの人」への愛情が、その裏返しの憎しみと一つになって表現されている詩。抜き出した第三連は、ユニークなイメージが印象に残る。
今井富世「いのち三篇」は、「いのち 一」「いのち 二」「いのち 三」とそれぞれ題された四行詩が、三篇並ぶ。抜き出した「いのち 二」は、自己の心中を見つめる視点が印象的で、「貴方を嫌いだったりする」という、誰もがもっているであろう“だれかを嫌う気持ち”を、しかし、「鬼のかたちをしている」と厳しく自覚し、さらに「鬼も人の色をしている」と、「私」のことが嫌いで「私」にとっては「鬼」とも感じらる相手を「人の色をしている」とやさしく捉える(ということであろうと私は読んだ。もしからしたら、作者の理解は違うかもしれないが…)詩であり、とかく“対立”から“憎しみ”へと発展しがちな人間関係をいわば“和解”へと向かわせる志向をもった詩であると考える。
阿蘇の詩「おれとおれ」は、一篇の詩としてのまとまりがよく、ユーモアがあり、おもしろく、魅力的である。『びーぐる』誌第26号(2015年1月20日)は、「特集 詩とエロス」を組んでいる。「エロス」については、さまざまな捉え方ができるわけだが、詩「おれとおれ」は、「エロス」を、ユーモアをもっていわば“等身大”に捉えた詩として、「特集」に載っていてもおかしくない詩だな、と私は思った。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『E 詩』26号(2015年1月10日発行)
詩は、福岡俊一「薔薇」「ツェルニー讃」、阿部栄子「午後のコーヒー」、いとう柚子「十一月がおわる日に」、芝春也「秋のつぶやき」。エッセイは、芝春也「ぽえ爺随考録② 家族の中の孤独」。ほかに、いであつし「アフォリズム 百馬鹿の柵②」。
いとう柚子の詩「十一月がおわる日に」を紹介し、感想を述べておきたい。
詩には、タイトルが詩の構成上欠かせない役割をもつ場合もあれば、「無題」としても大きく変わらないような場合もある。この詩の場合は、タイトルが大きな役割を担っていると考える。
私は、タイトルにはほとんど注意を向けないでまず本文を読んでしまうというくせがあり、本文を読んだあとタイトルにあらためて注意を向けるという場合が多い。いとうのこの詩を読んだときにも、そういう読み方をしてしまい、よい味わいのある詩だけれども心にすうっと入って来ない、というような印象をもった。そのあと、あらためてタイトルに着目し、タイトルから、第一連の1行目「枯葉が舞いこむように」と読み進んだとき、詩がすうっと心の中に入ってきた。この詩の魅力が“わかった”と思った。この詩に表現されていること全体が、「わたし」がすごす日常の日々に、「枯葉が舞いこむように」、入り込んできた一つのエピソードなのであり、それは、「わたし」の人生に何か決定的な影響を与えるようなものではないけれども、しかし、いわば“一日一日にその日を生きる味わいを与える”ような、そういうことなのではないか、と。
第一連。エピソードの始まり。
第二連。「わたし」がどのような日常を過ごしている人なのかがわかる。
第三連。「単調な日々と孤独」が「わたし」の「日常」と重なっている、と読んでよいのではないだろうか。この連の終わりの3行「突拍子もない けれど すこしも害にならない/たくさんの真剣な嘘で/単調な日々と孤独をまぎらそうとする中年女の物語」は、この詩全体が醸し出すアンニュイと言ってよいような感覚と第四連の1~3行目とを踏まえて考えると、この詩に表現されているエピソードが、「わたし」にとって、単なる偶然のできごとではなく、ある種の必然性のあるできごとであって、その必然性のいわば“由来”を表現している、と考えられる。
第四、五連。「詩の中でたくさん嘘をついたので/あのときよりずっと親しくなれそうだ」に、実は、私は疑問をもった。「詩の中でたくさん嘘をついた」は、“実感”だろうか。もし、そうであれば、「わたし」において、これまで自分が書いてきた「詩」は、「レミンスキー」の「嘘」と大差ないものととらえられていることになる。そうではなく、“アイロニー”であると考えることもできる。すなわち、「わたし」は、自分の「詩」が「レミンスキー」の「嘘」と同一視されるようなものではないと捉えているが、一方、ある面から見れば―「詩」で述べてきた内容が「事実」とは異なるものを含んでいるという点に目を向ければ、あるいは、自分の詩が“詩”として成立していないのであれば「レミンスキー」の「嘘」と変わりないものなのではないかと考えれば―「たくさん嘘をついた」という言葉から完全に逃れられるものではないので、自身に対しての“アイロニー”としてそう表現したということである。私は、後者と捉えるのが適切であると考える。日常の“アンニュイ”がもたらした、これまでの自身の詩業に対する、一抹の“疑念”―それこそ、「枯葉が舞いこむように」、「わたし」の心に入り込んできた“疑念”―が、この詩の、表には出ないモチーフなのではないか、と考えるからである。“実感”と捉えたのでは、その“疑念”の“底深さ”を捉えそこねることなると考える。
最終連の終わりの3行「せめて行く秋の長い夜/はじめての出会いのように/マダム・ジレンスキーの物語に入ってゆく」は、この詩に表現されたエピソードの結末にふさわしく、味わい深い。日常の“アンニュイ”を越えて、一日に“その日を生きる味わい”を与える手立てが示されていると考える。
芝の「ぽえ爺随考録② 家族の中の孤独」は、芝の自伝を含む内容であり、感慨を覚えながら読んだ。最後の二つの段落から、言葉を引いておきたい。「人間は一人では生きられない。家族の中にあっても、社会の中にあっても、人間は一人では生きられない。それは真実だ。しかし、そのことを分かっていてもなお、人間は一人で生きたいと思う生き物だ。その思いを消し去ることは出来ない。それも真実だ。 共同性と独在性と…、この二つのものの矛盾を生きるのが、多分人生というものだろう。//そしてあらゆる芸術の芽は、その矛盾のなかにこそ胚胎するのだといえる。」
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)