
詩集を読んで〈2014〉 その2
尾崎まりえ詩集『アリスのとき』(書肆犀、2014年5月1日発行)
尾崎まりえの第一詩集である。
収められた詩を一つ一つ読むと、テーマもモチーフも多様であり、「全体を貫くような特徴」は見出しにくいように思われる。一方、「アリスのとき」という詩集タイトルは、「想像力が自由に飛翔し、世界も自分も未知の可能性としてあった時期」を表現しており、この詩集によって作者が何を表現しようとしたのか、そのことを考える端緒となる、と考える。
この詩集によって表現されているもの(言うまでもなく、それは作者が表現しようとしたものとは必ずしも一致しない)は、一言で表現すれば「成長」ということではないかと思う。一人の人間として、と言うより、この詩集の場合にはむしろ一人の女性として、「アリスのとき」から現在にいたるまでの、自分の姿(や自分を取り巻くものの姿)を振り返り、そこに表現へと向かうモチーフを見出して表現している、そういうことが全体的な特徴として言えるように思う。
詩集冒頭の詩「アリス」は、詩集タイトルに直結する詩であり、前述した、「成長」を見るまなざしを、実感させる作品である。
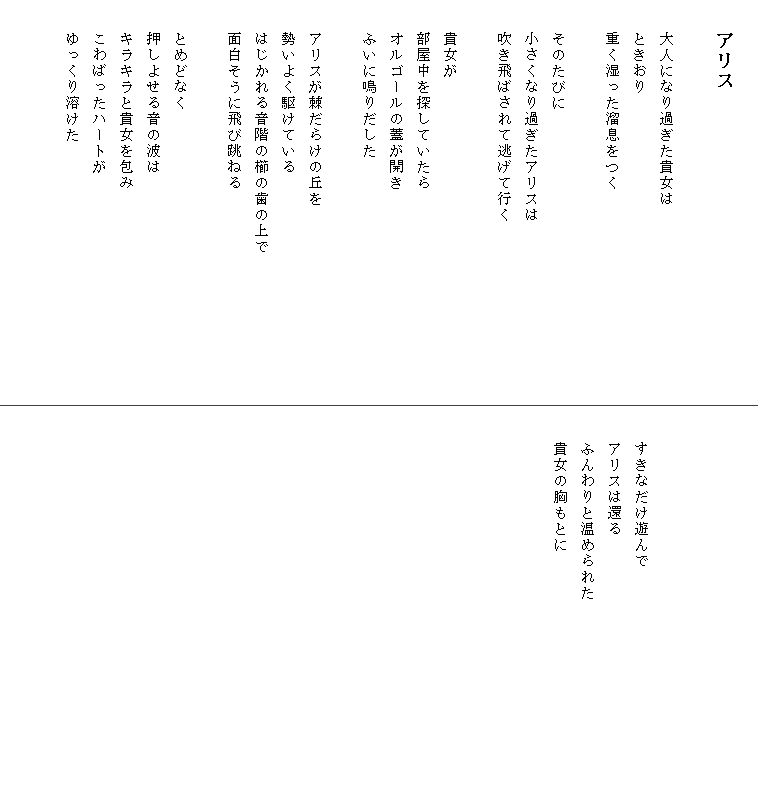
第一連。「大人になり過ぎた」女性の姿が描かれている。「重く湿った溜息」の理由は、述べられない。それがよいと思う。人が溜息をつく具体的な理由など、無数にある。一方、「重く湿った」は、「大人になり過ぎた」女性の溜息を形容するにふさわしい、効果的な表現。結果的に、この第一連の表現は、「大人になり過ぎた」という認識を実感として感じることができ、「重く湿った」と感じられる溜息をついた経験のある「大人」に、広く受け入れられるものになっている、と考える。
第二連。「アリス」は、“世間的なものごとや常識(それらは、しばしば、溜息の原因ともなる)に縛られることなく、行動も意識も伸び伸びとしていた少女の時期”を象徴している、と考えることができる。「小さくなり過ぎたアリス」には、『不思議の国のアリス』からの“本歌取り”の表現としてのおもしろさもある。
第三連、第四連。「アリス」の戯れは、少女の時期の、気の向くままの、自由奔放な行動と意識のあり方を表現していると考えてよいだろう。「棘だらけの丘(を/勢いよく駆けている)」が、一方では突起のあるドラムをもつ「オルゴール」の巧みな比喩でありながら、もう一方で「アリス」(=少女の時期)の自在な想像力の飛翔(オルゴールのドラムから、「棘だらけの丘」を想像するような)をも表していて、卓抜な表現となっている。
第五連。少女の時期の、自由奔放で快活な心の状態を思い起こして、心のこわばりが解消された状態が、聴覚と視覚を合わせた感覚的な表現で表されている。
第六連。少女の時期にはそれが当り前であった、世間的なものごとや常識にとらわれない、奔放で、快活な心のあり方を取り戻したことの表現、と読める。特記しておきたいのは、「アリス」と「貴女」との“距離”である。「アリス」は「胸もと」に「還る」のであって、それは、“完全に一つになった”ことを意味しない。もう一度「重く湿った溜息をつく」ようなことがあれば、その時には、「アリス」はまた「吹き飛ばされて逃げて行く」ことになる。すなわち、取り戻した、奔放で快活な心は、いつも、いつまでも、持ち続けることができるような性質のものではなく、心をこわばらせ、溜息をつかざるをえないような体験に際しては、また「探」さなければならなくなってしまう性質のものである。見方を変えて言えば、この詩は、最終の第六連から、最初の第一連へとつながって、循環する仕組みをもっている。その点も、この詩の、ユニークで大きな魅力になっている、と私は思う。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
遠藤敦子詩集『禳禱 』(土曜美術社出版販売、2014年10月20日発行)
“人生の不条理に対していかにして生きるか”。それが、この詩集のテーマであると思う。
「あとがき」に、次のようにある。
「受験の失敗に始まり、たび重なる流産や勤務先の団体の解散失職、家族や自分の病気など、何ゆえ降りかかる宿命と頭を抱えることが度々ありました。」
詩集をひもとけば、「あとがき」を読むまでもなく、慟哭し、無情を嘆かないではいられない体験が、詩によって表現されている。
冒頭の2篇の詩「乳房に」、「無情の部屋」に表現されているのは、流産という“人生の不条理”に対して、“悲しみ、恨み、嘆かざるをない人のすがた”である。その押えがたい感情は、例えば、「おまえを抱きしめ/万物の/親と子の縁を切り裂き/時間と天空の歪みを超えたい/母として/おまえの母として」(「乳房に」、最終連)と、表現されている。「おまえ」とは、「生まれ出ずして/命日のある」わが子である。
もしも、この詩集に収められている詩のすべてが、冒頭の2篇の詩のように、癒やされることなど終生ないのではあるまいかと思われる、深く激しい悲しみ、恨み、嘆きを伝えるものであったとしたら、―その気持ちが、散文的な冗漫さを伴わない、完成度の高い詩的な表現によって表されているだけに、なおさら―、この詩集を最後まで読みきることは読者にとってもつらさを感じ続ける体験とならざるをえなかっただろう。
しかし、詩集は、そうなっていない。
“人生の不条理”に対して“耐える人のすがた”を表現する詩が、次に、収められている。「病み床」、「車輪止め」、「がけっぷち」、「母」、「藪入り」と続く詩篇を、私は念頭に置いている。
それらの詩篇の中から、作者の詩的表現の特徴―無駄のない、簡潔なことば遣いで、気持ちを“説明”したり単に“叙述”したりするのでなく、“イメージの力を駆使して、実感を伝える”ことに成功している―そういう特徴が、よくわかる1篇「母」の全文を、次に引いておきたい。
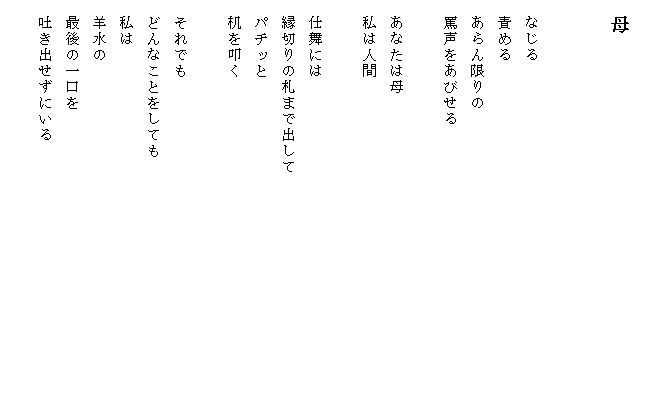
この詩集の“頂点”と私が個人的に思っているのは、「かざぐるま」、「さんりんしゃ」、「撫でし子」の3篇である。
この3篇には、“人生の不条理を体験してなお前向きに生きていこうとする人のすがた”が表現されている、と私は思う(作者の意図はわからないけれど、そのように読みとることができる)。その力のもととなるのは、“これまで生きてきた自分の人生と、いま自分は生きているということとを、いつくしむこと”と言ってよいのではないだろうか。
3篇の中から、「かざぐるま」の全文を、次に引きたい。
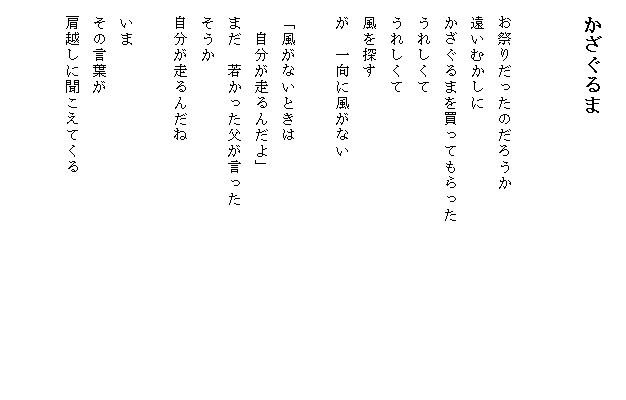
さて、詩集は、大きく、「Ⅰ」と「Ⅱ」、二つの章に分かれている。
「Ⅰ」には、“人生の不条理”を体験することの多かった“自分自身の人生”を直視する(ことによって書かれた)詩が収められている。一方、「Ⅱ」には、“自分”から視点を移して、“自分以外のもの”に目を向けた詩が収められている。
私がここまでに取り上げた詩は「Ⅰ」に収められているが、「Ⅱ」に収めらた詩もそれぞれに印象深い。
「Ⅱ」でも、作者のまなざしは、やはり、“人生の不条理”に向けられている。
詩「十一月某日 雪」に表現された「老婆」のすがた、詩「早冬」に表現された「君」のすがた、詩「土筆」に表現された「夫婦」のすがた、「広重の妻」に表現された「妻」のすがた、それらは、それぞれ、“人生の不条理を体験した人のすがた”として、心に残る。
そして、“人生の不条理”を自ら体験し、広く見聞きして、「天道は是か非か」の思いのもと、『史記』130巻を書き上げた司馬遷の、“人生の不条理に対する処し方”への共感によって書かれたと思われる、詩「谷」の最終連となっている、次のことば。それは、“人生の不条理に対していかにして生きるか”という問いに対する、作者の現時点での答えとして読むことができるように思うのだが、どうだろうか。
「明日/谷へ下りよう/二度と尾根を見ることができなくとも/後悔はしない/清廉の屍の谷に/明日 下りる」
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
2014年の早い時期に出版され、いただいておきながら、2015年1月現在、これまで感想を述べることができていない、一冊の詩集がある。それが、この詩集『Blent Junction』である。
理由は、二つあげることができる。一つは、まとまった感想を述べるほどには“この詩集が読めていない”と思っていたからだ。“この詩集で何が表現されているのか”について、自信をもって述べることができないと思われた。二つめは、“どのように読めばよいのか”、“何を読みとることが適切なのか”、迷いがあったからだ。榊は自分が統合失調症であることを明らかにしており(榊のブログ「アリエナシオン」のプロフィールで紹介されている)、その事実とそのことによって自他に生じることとを、詩を書く上でのいわば前提として受けとめて、詩を書いている。そういう詩人の詩を、“どのように読むことが適切なのか”。このばの意味づけ(一人の読者として、どのような意味をことばにもたせて受け入れるか)に“統合失調症による”という視点をどこまで持ち込むか、あるいは、“統合失調症による”という視点を抜きにして、少なくとも“いったん棚上げにして”詩を読むことが適切なのか、しかし、そのようにして読んだときに、ことばの意味づけがどこまで可能なのか。私は迷った。
とはいえ、榊の詩集は、ずっと気になっていた。“読めていない”ところ、すなわち“表現されていながら私が読み手として視野に入れることができていない内容”が少なからずあることは、確かである。それでも、ここで、感想を述べておきたい。榊の詩に、榊の詩ならではのことばの使い方と魅力があることは確かであり、それがどういうものであるのか、自分なりに整理してみたいと思うからである。
ここで、二篇の詩を引いておきたい。「―」(ダッシュ)は、本来すべて2文字分の長さである。「卜」は、「
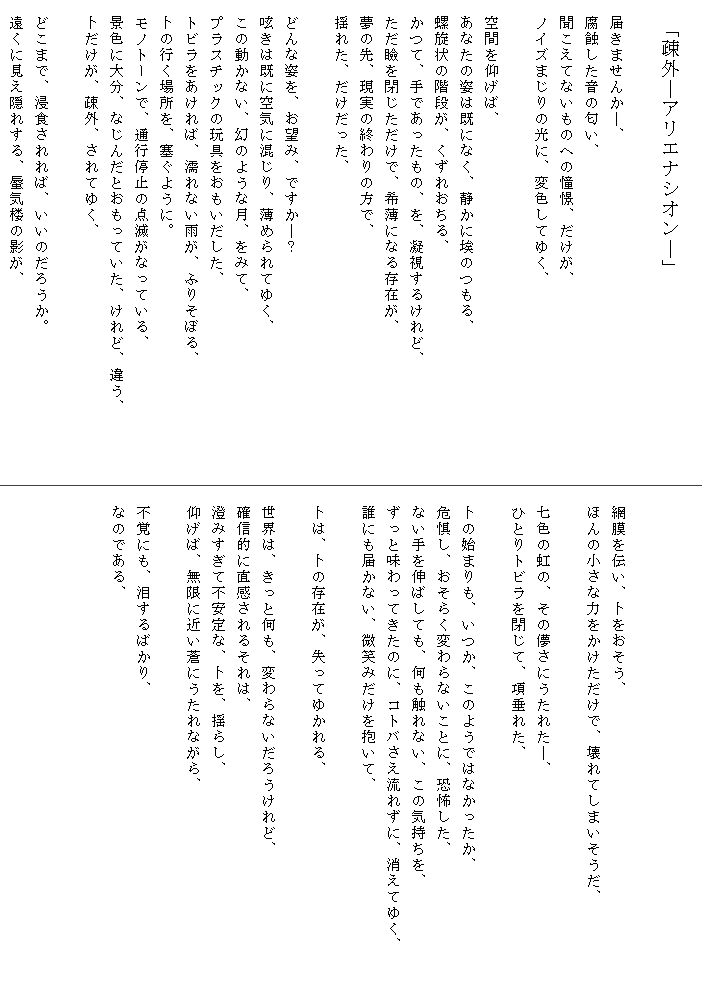
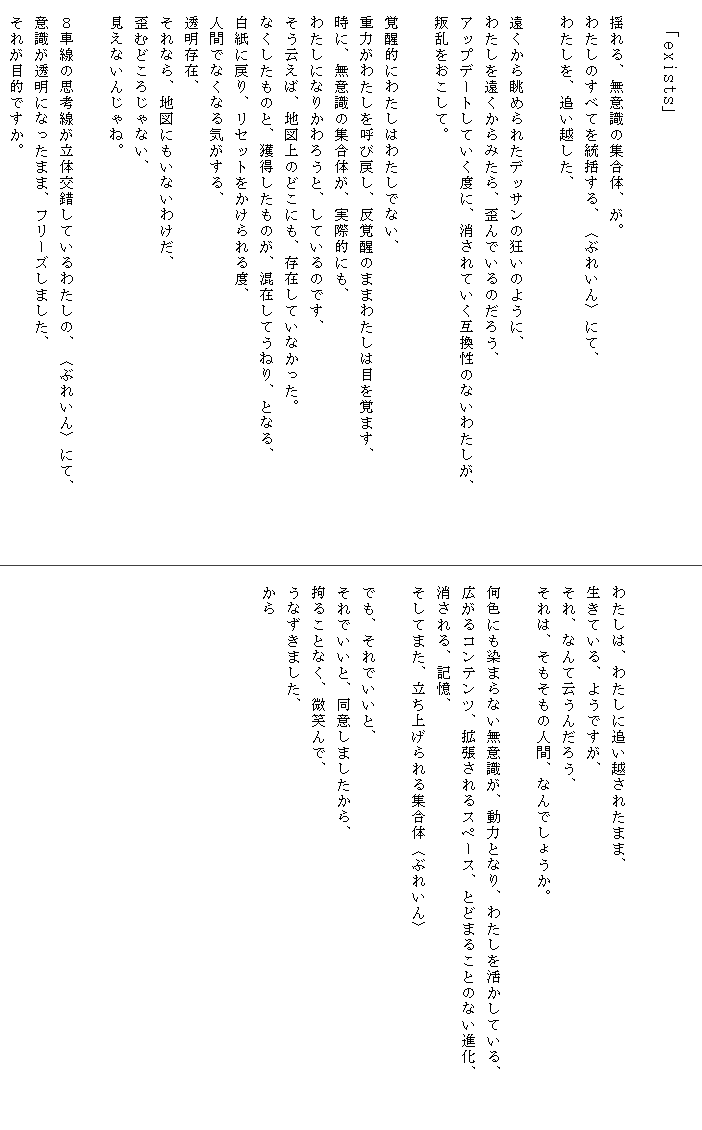
詩集で、榊は、三つの一人称を使っている。「卜」と「わたし」と「ぼく」である。この三つの一人称は、榊の中では置き換えができないものとして使い分けられていると思われる。特に、「卜」は、榊が統合失調症という状態の中で“自分”の“拠り所”としている一人称であると思われ、その点で他の二つと区別される。
詩「疎外―アリエナシオン―」では、一人称として「卜」が使われている。
「卜」には、「始まり」がある。詩「疎外―アリエナシオン―」の第6連に着目したい。「卜の始まりも、いつか、このようではなかったか、」。幻想と幻視におそわれて、“確かにそれが存在している”という信憑を得ることが基本的に困難な状態(=統合失調症に特徴的な状態)にあって、そうした状態が「変わらないことに、恐怖したとき」、すなわち、そうした状態から脱したいと望み、願ったときに、作者によって希求された“自分“の“核”が「卜」である、と読める。それは、作者にとって“確かに存在している”という信憑を与えることができるものではない。「卜の存在が、失ってゆかれる」(第7連)という状態と、いわばひとつなものとしてある。それほど「不安定な」(第8連)ものであるが、しかし、それは、作者が“確かなもの”を求めるときに、なくてはならない“自分”としてある。
「卜」は、作者にとって“自分”の“核”となる一人称なのだ、と私は読んだ。統合失調症という状態にあって、“自分”の“核”として、“拠り所”として希求されるところの自分である。
詩では、作者においては、世界を構成するすべてから“確かさ”が失われ、“確かにあるもの”と“感覚されても実際にはないもの”との区別がなくなってしまったことから、“確かにあるもの”として了解され構成されている「世界」(“客観的に存在している世界”と言ってもここではかまわだろう)から、おのずから「疎外、されていく」状況が表現されている。
第8連から最終連を読んで、感動する。「無限に近い蒼」とは、私たちが通常「空」と呼ぶものだろう。しかし、作者にとって、それは、「空」と言えるほど、確かなものではない。「無限に近い蒼」とは、「空」をより印象的・感覚的な表現に言い換えたレトリックではない。作者にとって、それは、“そのように表現するしかないもの”なのだ。それを「空」と言うこともできない、そんな不確かな状況にあって、しかし、「無限に近い蒼」に、作者の心は「うたれ」る。「仰げば、無限に近い蒼にうたれながら//不覚にも、泪するばかり、/なのである、」。どうして「泪する」のだろうか。うれしいからでも、かなしいからでもないだろう。“わけもないのにこぼれる”感傷のなみだでもあるまい。「無限に近い蒼にうたれながら、//不覚にも、泪するばかり」であるということ、それが、そのとき、作者にとって“もっとも確か”であったことであり、唯一と言ってよい“自分”の“拠り所”、すなわち「卜」そのものなのだ。感じやすくなった心のせいで、これといった理由もなく流れる感傷のなみだに、それは、似ているようであって、実は、まったく異なっている。感傷のなみだには、感傷にひたる自分、存在を疑われることがないという意味で、確かな、自分が伴っている。「感傷にひたってなみだを流す」ということを取り除いてもなお残る、確かな自分がそこにいる。詩では、「無限に近い蒼にうたれながら//不覚にも、泪する」という、そのこと以外に、確かな自分は存在しない。その状況は、「感傷」とは、とうてい比べることができないものだ。
一方、詩「exists」で一人称として使われているのは、「わたし」である。
「わたし」は、「認識と行動の担い手」(大修館書店『明鏡 国語辞典』「主体」の説明より)としての自分のことを言っていると考えられる。
この国語辞典で、「主体」は、次のように説明されている。「性質・状態・作用などの主として、それを担うもの。特に、認識と行動の担い手として意志をもって行動し、その動作の影響を他に及ぼすもの」。また、『コンサイス20世紀思想事典 第2版』(三省堂)では、「主体」の項目の説明の中に、次のようなことばがある。「自己の自由により自覚的・意志的に自己決定を行いつつ行為する個体としての人間の意」(箱石匡行)。どちらの説明も、「主体的に判断し、主体的に行動することが大切である」、「情報社会となった今日おいて主体性を確保することが難しくなってきている」と言うような場合の「主体」の意味、すなわち現在一般的に「主体的」や「主体性」と言う場合の「主体」の意味を説明していると考えられる。「主体」は、フロイトによって行動の動機としての「無意識」の存在が示され、構造主義の哲学によって、「人間は心的・言語的・社会的な構造ないしシステムに支配されている」(前掲、箱石)と「主体」の解体が示されても、一般的には、今日なお、人間は「自己の自由により自覚的・意志的に自己決定を行いつつ行為する」、「認識と行動の担い手」である、という了解が成り立っていると言えるだろう。
「自己の自由により自覚的・意志的に自己決定を行」うことが困難な状態になっても、人が自分で生きていこうとするときには、「認識と行動の担い手」としての自分が必要となる。それを表すのが、「わたし」という一人称であると考えられる。
詩「ixists」では、本来意識的に自己決定を行うことができるはずの自分が「無意識の集合体」に「なりかわろう」とする状況が表現されている。
「無意識の集合体、が。/わたしのすべてを統括する、〈ぶれいん〉にて、/わたしを、追い越した、」「無意識の集合体が、実際的にも、/わたしになりかわろうと、しているのです、」。ここに表現されているのは、明らかに、「認識と行動の担い手」としての「わたし」が、「自覚的・意志的に自己決定を行いつつ行為する」こと、すなわち意識によって自己を監督し、自己の行為をコントロールすることができなくなって、「無意識の集合体」に「なりかわろう」としている状況である。
この詩でも、私は、終わりの2連に感動する。
「何色にも染まらない無意識が、動力となり、わたしを活かしている、」。「無意識」による「わたし」への「なりかわ」りを、作者は容認するのだ。「でも、それでいいと、/それでいいと、同意しましたから、/拘ることなく、微笑んで、/うなずきました、/から」。“意識で自分をコントロールする”ことができなくとも、「自覚的・意志的に自己決定する」ことができなくても、「自由」ではなくとも、「無意識の集合体」であっても、いまの自分にとってはそれが“「わたし」として生きる”ことなのだと、作者は、その価値を認め、受け入れたのだ、と私は読んだ。
意識的な「自分探し」や「自分づくり」に汲々とするいまの時代にあって、「無意識の集合体」であってもそれがいまの「わたし」と受け入れて生きようとする作者の姿は、いわば究極の“自己受容”の姿とも言えるのであって、「自分探し」や「自分づくり」に、あるいは「自分を向上させる」ことに、こだわることへの反省を促し、また、そうしたことに疲れた人たちに対してはこれを慰撫する力がある、と私は思う。
なお、第4連に「8車線の思考線が立体交錯しているわたしの、〈ぶれいん〉」とあるが、「8本線の立体交錯は、かなり危険だがデフォルト」(p10)ということばも詩集中にあり、「8車線の思考線が立体交錯している」状態を「わたし」の「デフォルト」の状態、初期設定の状態であると作者は自覚している、と考えられる。「8車線の思考線が立体交錯している」状態とは、いったいどういう意識の状態だろうか。多くの思考が、まとまった方向性をもたずに、同時平行的に生起する状態、と捉えてよいだろうか。そのように捉えることができるとすれば、それが、作者における統合失調症の表れであると考えてもよいのではないだろうか。詩集タイトルの「Blent Junction」が、そうした意識の状態を受けたものであることは、確かだろう。
詩集は、「Blent Junction A」「a little break ―tanka―」「Blent Junction B」の3部で構成されている。
「Blent Junction A」には、“確かさ”の失われた世界で“確かさ”の失われた自分としてあり続ける「わたし」が、客観的な存在としての世界から疎外されている状況を表現する詩が収められている、と捉えてよいのではないだろうか。先に引いた2篇の詩は、ともに、「Blent Junction A」に収められている。「世界の新陳代謝は、わたしを除いて、行われる、」(詩「Betweenn the dimension」)、「規定確定されない、わたしの存在は。再度。光にくるまれて、分解される。」(詩「異伝子分解極メカニクル」)。そうしたことばの現れる詩で、終わっている。
そして、「Blent Junction B」には、「卜」を“核”として自分を「再構築」しようとする詩が収められている、と捉えてよいのではないだろうか。「再構築」のために、作者が手段として用いるのが「コトバ」である。
「コトバ」による自分の「再構築」は、どのように行われているのか。次に、1篇の詩を引く。引用する詩「ワンネス、フル」は、この詩集に収められた詩の、最後から2番目のものである。
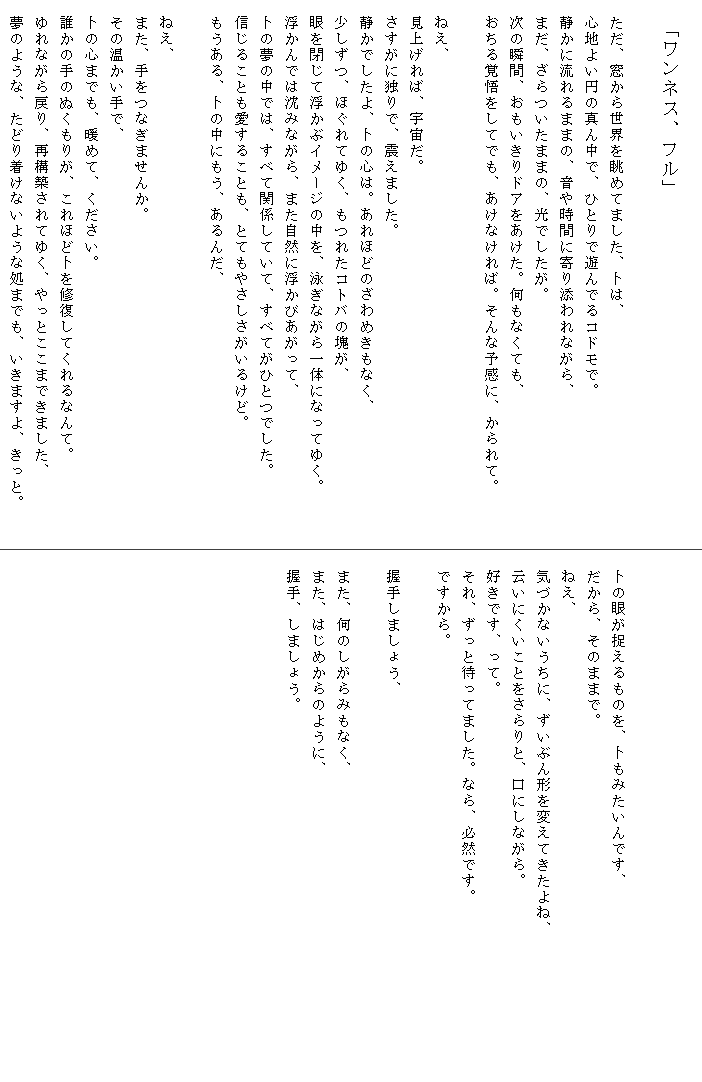
この詩では、世界とのつながりが回復される形で、自分の「再構築」が行われている。
全体に感動的であるが、第3連以降は、特にそうだ。「誰かの手のぬくもりが、これほど卜を修復してくれるなんて。ゆれながら戻り、再構築されてゆく、やっとここまできました、」。
自分を「再構築」する上での「コトバ」の重要性を、作者ははっきりと自覚している。「卜は異なる次元の、異なる方法で接続されている異なるコトバであった」(詩「brand new sound world's word」)。「もうすぐ収束がきて新しく刷新されようとするとき、コトバは必須の手段だろう、」(同前)。
作者における、自分の「再構築」のキーワードとなる「コトバ」は、「好き」。そして、「光」。ただし、「光」は、「コトバ」であるだけではなく、「波とか振動」(詩「light of prayer」)としても作者に自覚されていると思われる。
最後の詩「light of prayer」は、次のようなことばで終わっている。「卜は、今このときの最善を尽くしていこうと、思いました、/こんなに静かな場所から、/光だけを求めて。//えーる!/ぷりえーる!/眩い祈りの声が。/まだ、遙か遠くの卜を、みている。」
自分の「再構築」は、まだ達成されたわけではない。達成が「遙か遠く」にあることを、作者は自覚しているようだ。それでも達成を志向する、まさしく「祈り」と言ってよい気持ちを伝えて、詩集は終わっている。
この詩集の詩を読む上で、“統合失調症による”という視点を持ち込むことが適切なのか、持ち込まないことが適切なのか、という問題提起を先に行った。私の結論は、前者である。後者の立場に立って、この詩集の詩を、例えば、世界と自己に対する積極的な懐疑とその上での再構築の試みとして読むことも不可能ではない。しかし、そのように読むと、この詩集の詩は、根本的に作者から切り離されて、意味の根源とリアリティの根拠を失ってしまう。そのような読み方は、適切ではないと考える。誤解を避けるために、さらに言い添えておきたい。“統合失調症による”という視点を持ち込まないと、作者の意図を読み取ることができないと言いたいのではない(上記の文章でも、作者の意図とは異なる理解をしている可能性が少なからずある)。そうではなくて、“統合失調症による”という視点を持ち込まないと、詩に何が表現されているのかを適切に読み取ることができない、読み手として(詩という言語表現を受けとる者として)テキストのことばを(表現されている内容を)適切に解釈する(理解する)ことができないということである。
(以上、一部を除き、敬称と敬語表現を省略させていただきました。)
Copyright©2013 Masayuki Kuno All Rights Reserved.