
詩集を読んで〈2013〉 その2
相蘇清太郎詩集『ルネサンスに至る神々』(メディア・パブリッシング、2013年10月20日発行)
詩集のタイトルが、強い印象を与える。「あとがき」によれば、本誌集の第一章にあたる、七つの作品が、もともと、「ルネサンスの神々」の題名のもとに作られた連作であるという。その連作について、「あとがき」の中で、相蘇は次のように述べている。
「ルネサンスに至る神々」は、生まれ育った農業的環境の在所で生き死んでいった者たちへの思いが基底になっている。長く私はそれに囚われていて、その痕跡を引きずってきた。私は、死者たちを必ずや再生させようと思って、「ルネサンスに至る神々」の題名のもとに詩の連作を試みた。(中略)
「ルネサンス」という語を用いたのは、ヨーロッパにおける文芸復興などと言った歴史的な意味合いは持たないが、「再生・復興」という」意味で用いた。ふるさとの魂である神々―即ちイエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神―の再生を願わずにおれない心情を擁護したいと思ったからである。「ルネサンスに至る神々」は、「ふるさとの再生を夢見る神々」であると言ってよい。
長い引用になってしまったが、本誌集のいちばんの読みどころは、詩集のタイトルともなった、第一章の作品群であり、それらの作品にこめられた相蘇の思いを確認しておきたい、と考えた。 「私にとって、ポエジーの探究はアイデンティティの追窮でもあった。」(「あとがき」)と述べる相蘇にとって、「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」の確認と表現は、相蘇が詩人として真正面から向き合わなければならない課題であったと考えられる。
さて、では、相蘇が表現している「祖先に繋がる精神」とは、どのようなものか。
詩集の最初に、「ルネサンスに至る神々」の題名をもつ、九つの節(「Ⅰ」~「Ⅸ」)からなる詩が置かれている。その「Ⅰ」を、次に引く。
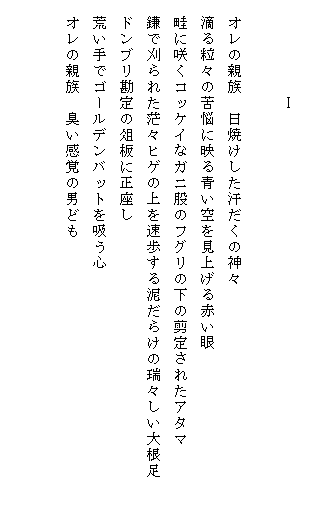
一読して、常識的な価値観にとらわれて書かれたものでないことがわかる。
ここで表現されているのは、「農業的環境の在所で生き死んでいった者たち」の、〝滑稽でたくましい精神〟のあり方である。この場合の〝滑稽〟は、〝人が生きていく上で本来もっている滑稽さ〟であり、その〝滑稽さ〟を文化的な洗練などによって隠そうとはしない〝生命力にあふれた、たくましい生き方〟の裏返しである。平安朝の貴族などから見れば、あるいは、いわゆるブルジョア的な価値観からすれば、「野卑」とさげすみ、「粗野」と難じる対象となるのであろうが、相蘇は、あえて、その〝滑稽さ〟を強調し、戯画化して、表現している。その強調、戯画化は、むろん、批判し、嘲笑しようという意図によるものではなく、「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」の再生を願う強い気持ちと、その精神を引き継ぐ者としてのプライドの現れだろう。
ところで、本詩集に収められている詩を全体に俯瞰すると、実は、詩 「ルネサンスに至る神々」だけが、他の詩と、内容的にも表現的にも異質であることがわかる。
本詩集は、全体が四つの章に分かれており、その分け方は、「あとがき」で、次のように述べられている。
第一は「ルネサンスに至る神々」の連作、第二は酒田の街を歌ったもの、第三は友人の死などに関わるもの、第四は祝婚歌である。
次の詩「種室の南に」(全文)は、第一章の中に位置するもので、「ルネサンスに至る神々」の連作の中の一つである。
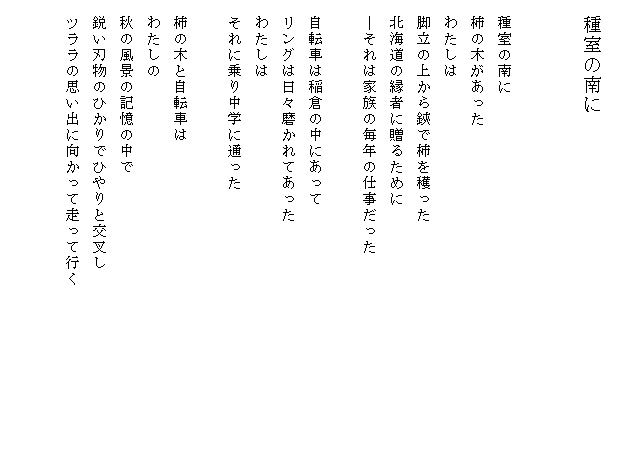
この詩が、詩「ルネサンスに至る神々」とは、内容においても表現においても、〝質〟(性質)を異にすることは、一読して明らかである。
この詩が、どうして「ルネサンスに至る神々」の連作の一つとして書かれたのだろうか。この詩のどこに、「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」が表現されているのか。このことについて考えることは、本詩集の第一章「ルネサンスに至る神々」で、相蘇が何を表現しようとしたのか、そして、表現しているのかを考えようとするときに、必要なことである。
考えるに、この詩は、(「祖先」ではなく)作者と「農」とのかかわり、作者にとっての「農」の位置づけを示しているのではあるまいか。
作者にあっては、「祖先」ほど、「農」とのかかわりが深くない。この詩に描かれているのは、作者が「中学」に通っているときのことであるわけだが、「種室の南に/柿の木があった」というように、第一連と第二連については、文末がすべて「た」であり、過去のこととして述べられている。第一連と第二連で作者が表現しているのは、「中学」に通っていたころの、作者と「農」とのかかわりであろう。そのころ、作者の家には、まだ、「種室」があり、「柿の木」があり、「稲倉」があった。しかし、作者と「農」とのかかわりという点では、「北海道の縁者に贈るために」「柿を穫った」という程度のことに過ぎない。そういう、「農」と作者との間の距離を示しているのではあるまいか。現在では、「柿の木」がもうないのは確実と考えられるが、「種室」や「稲倉」もあるのかどうか。「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」を引き継ぐべき者でありながら、現在の自分は、「農」との間に相当の距離を置いてしまっている、そういう自覚のもとに、わずかながらもまだ「農」とのかかわりをもっていた中学生のときを回想しているのが、この詩なのではあるまいか。
「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」の再生を強く願いながら、一方、自分には、その「精神」の土壌であった「農」との間に距離がある、「農業的環境」は自分の周囲から確実に失われていっている、そいう諧謔の自覚のもとに書かれているのが、本詩集の第一章の作品群であるように思われる。
その中にあって、「イエ、ムラに生きる、祖先に繋がる精神」を確認し、直接に表現しようとしたのが、詩「ルネサンスに至る神々」であり、私にとっては、やはり、この詩が、本詩集の中で最も読みごたえのある詩である。また、詩集における詩の位置づけという点でも最も重要な位置にある作品であると考える。
本詩集の全体を貫く、相蘇の詩の特徴を考えるならば、それは、「諧謔性」と「表現へのこだわり」と言えるのではないだろうか。前者は、本詩集の、第一章以外の詩の中でも、しばしば顔を表している。後者は、例えば、「種室の南に」の第三連によく現れている。
相蘇の「表現へのこだわり」は、詩の要所において、抒情性と結びついて、練りに練った、抒情的表現を作り上げている。表現によっては、抽象性が強くて、私などには理解の難しい表現もあるが、練り上げられた表現を、抒情性を味わいながら、その意味を考えつつ読むのも、本詩集の読みごたえの一つとなっている。
(以上、敬称を省略させていただきました。)
伊淵大三郎詩集『宇宙の青い いのちの星』(土曜美術社出版販売、2013年11月25日発行)
本詩集の書評が、12月3日発行「山形新聞」の「味読 郷土の本」のコーナーに掲載されている。評者は、高橋英司。紹介という点でも、批評という点でも、詩集の書評の手本となるような、みごとな書きぶりと内容であり、高橋の書評に多くを付け加える必要を感じない。
高橋は、「ほぼ半世紀にわたる」伊淵の詩歴を振り返り、そこには、「自然を観照し、そこに人生の意味を見いだすという点」で「一貫した詩作態度」があることを指摘している。そして、「わかりやすい清新な言葉で、事物をあるがままに、見たままに表現する」ことによって「一見、何の変哲もない、スケッチ風の情景」が「風景画のよう」に表現されるが、「読者は、表現された情景の裏に潜む含蓄のある世界を感知し、思索を促される」と述べている。以上の高橋の評言は、伊淵の詩の特色と魅力を的確にとらえていると考える。
書評の最後で、高橋は次のように述べる。「情景を観察した通りに書きつけた言葉は、時代や社会に対する風刺となり、批評となっている」。この評言もまた、伊淵の詩についてぜひとも指摘しておくべき、的を射たものであると考える。
高橋の書評には、「批評を秘めた 自然語る言葉」というタイトルが付いているが、このタイトルは、本詩集所収の伊淵の詩について、その本質的な特徴を、まさに正鵠を射るように、とらえていると言えよう。
伊淵のこれまでの詩集と比較したときの、本詩集の特色としては、「批評」が前面に出ている詩が少なくなり、「自然」に向けるまなざしに、一種の〝優しさ〟が、より丁寧な表現を探れば、〝静かで落ち着いた、共感と受容〟が、はっきりと加わっていることが挙げられよう。
そうした伊淵のまなざしは、「宇宙の青い いのちの星」地球に生きる「いのち」を、「生命あるものすべては生命の星地球に共に生きる存在である。夫々の違い、多様性を認めあい、貪欲を慎み協力しあってゆくほか未来はない。」(あとがき)という〝実感〟(建て前や単なる観念ではなく)を持って見つめるまなざしに他なるまい。
例えば、詩集の最初に置かれた、詩「雪虫」には、そうした「まなざし」がはっきりと現れている。
この詩に、「雪虫」の「生命」を見つめる、作者のまなざしがあり、そのまなざしのうちに〝共感と受容〟があることは、詩句を引いての説明を要しないだろう。〝受容〟とは、この場合、〝自己(人間)以外の生命について、それがそこにあることを、尊い価値のあることとして受けとめる、おのずからなる態度〟のことである。
さて、この詩を含めて、本詩集のいくつかの詩において、〝共感と受容〟がとりわけはっきっりと現れ、かつ、詩を詩として成り立たせる重要なはたらきをなしているのが、詩の最終連の終り2行である。本詩集所収の詩に特徴的なことの一つであり、また、詩を魅力あるものとしている要因の一つと思われるので、指摘しておきたい。
詩「雪虫」の場合は、「ひっそりと/季節を先触れする」の2行によって、「雪虫」の存在が、〝作者自身が生きる時間〟のうちに受け入れられ、位置づけられている。
「こんなに小さく/はかない生命」と雪虫の「いのち」に共感し、「いのち」ある存在(「生命の星地球に共に生きる存在」)として、雪虫の存在を、あるいは、その「いのち」の在り方を、あるがままに尊び、受け入れる一方、最後の2行において、作者は、四季のめぐりのうちに生きる自分にとって、それは「ひっそりと/季節を先触れする」ものであるという、作者自身にとっての意味づけを与えて(それも、たいへんさりげなく、無理なく、いわばあってもなくてもよい付け足しのように、与えて)、雪虫の存在を受け入れている。
詩「モズ」の終り2行「空の時が多い巣の上に/槿の花が 風に揺れている」や、詩「昼音」の終り2行「澄んだ晩秋の日差し/昼音が ひっそりと続いている」、さらに詩「心遣い」の終り2行「母が死んで気づいた/その 心遣い のように」についても、「〝共感と受容〟がとりわけはっきっりと現れ、かつ、詩を詩として成り立たせる重要なはたらきをなしている」という点で、また、その2行によって、作者がそのまなざし(意識)を向けているもの(対象)が「〝作者自身が生きる時間〟のうちに受け入れられ、位置づけられている」という点で、共通していると考える。
本詩集所収の詩は、総じて、「技巧的」という印象を与えないが、実は、非凡な技巧が用いられている。このことにも、触れておきたい。
詩「雪虫」一篇に例を限っても、このことを述べるには十分である。
第一連で広大な情景を表現し、第二連ではクローズアップで表現し、第三連では視点を転じ、第四連以降はもっぱら「雪虫」に焦点を当てている。そうした変化が、実に無理なく、作為を感じさせることなく行われている。そして、そのことについては、第一連と第二連が連用形で終わり、常識的な感覚では第二連の最後に置くであろう一行(「雪曇りのおだやかなひと時」)が第三連の最初に置かれているということも、効果を発揮している。
また、「この 小さな虫たち」(第四連5行目)のような、スペースの使い方も効果的である。
効果的な技巧が作為を感じさせることなく用いられている。このことをとらえて、「円熟」という言葉を使っても的外れとは言えないのではないだろうか。
「批評」という点では、詩「さくらんぼ」や詩「モズ」においてその点が前面に出ているが、「雪虫」のような「自然(を)語る」ことに徹しているような詩、あるいは、詩「蛍」(詩集付属の「帯」に全文が紹介されているこの詩は、私にとっては、詩集の中で最も魅力的な詩である)のように少年時の思い出にひたっているような詩でも、「批評を秘め」ているととらえることが適切なのではないか。すなわち、詩「雪虫」の場合は、静謐な自然の営みを破壊してやまない人間の営みに対する批評、詩「蛍」の場合は、従うべき「
長くなったが、私が述べたことは、その骨格を、先に取り上げた、高橋の評言に依っている。このことを、改めて述べておきたい。
(以上、敬称を省略させていただきました。)
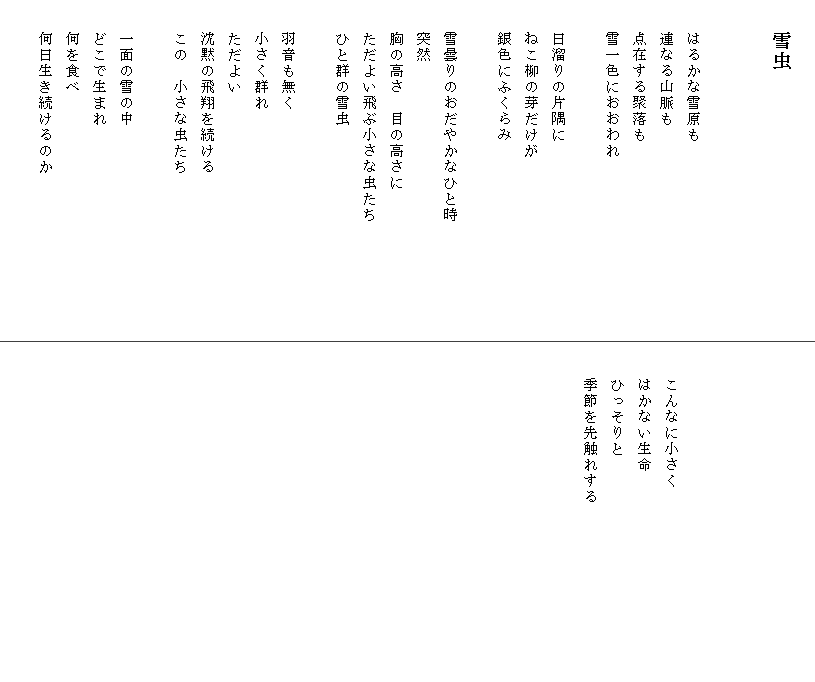
Copyright©2013 Masayuki Kuno All Rights Reserved.