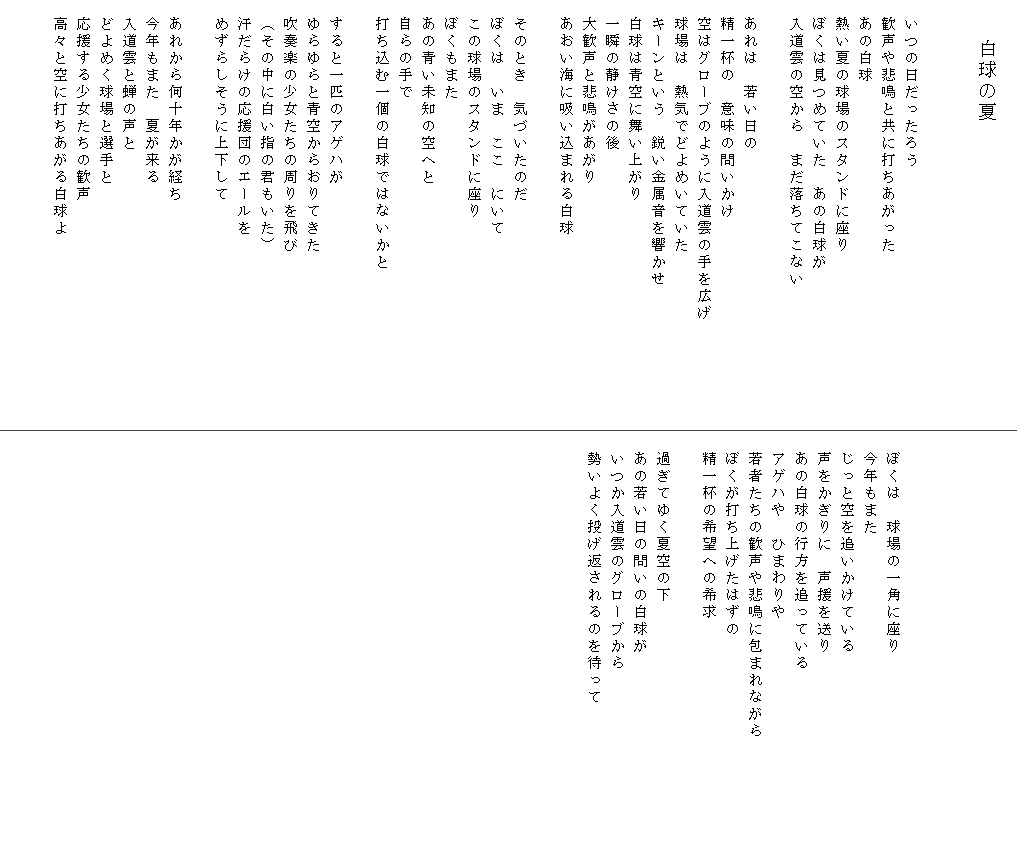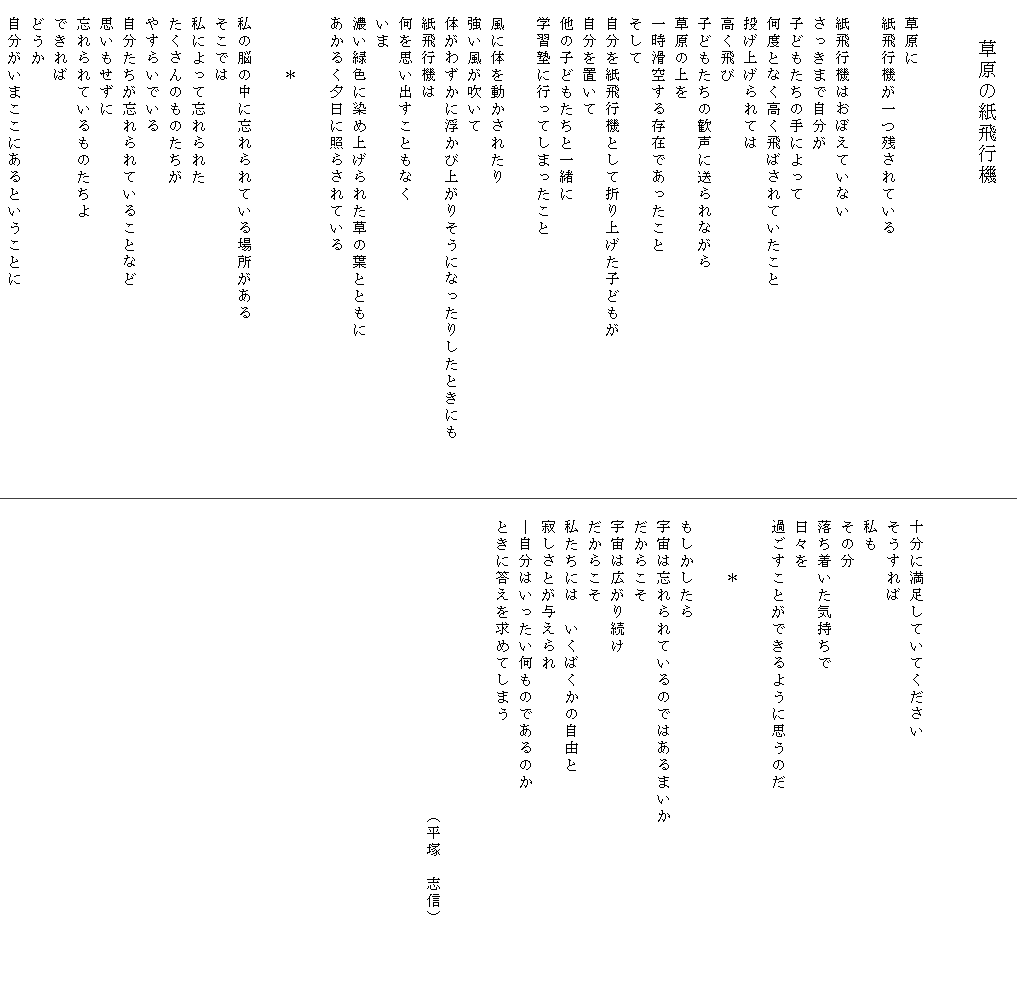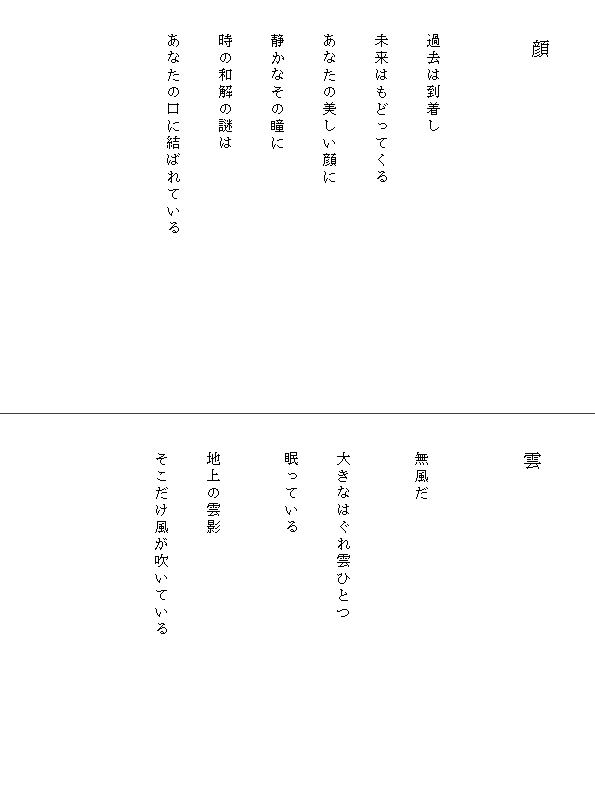一枚誌『表象』第42号(2013年8月6日発行)、第43号(2013年8月15日発行)、第44号(2013年9月14日発行)、第45号(2013年9月15日発行)、第46号(2013年10月8日発行)
詩は、万里小路譲(第42号)、房内はるみ(第43号)、尾崎まりえ(第44号)、近江正人(第45号、第46号)の詩を読むことができる。エッセイは、万里小路による、石垣りんと茨木のり子の詩の鑑賞に基づくものが継続して掲載されている。また、第46号には、このホームページでも紹介した、近江正人/詩・小野孝一/写真の詩写真集『希望への祈り』の紹介が、詩「
樹望」の鑑賞とともに、掲載されている。
近江正人の、二篇の詩「時の港から」(第45号掲載)、「白球の夏」(第46号)が、私には、特に味わい深い。
どちらの詩にも、「月並み」からは遠い、感性と想像力のはたらきによって得られた、「作者ならでは」のイメージの豊かな展開がある。
「時の港から」は、秋の終りの感傷的な思いが、詩に、いわば「昇華」されている。四つの連からなる。
第一連のイメージには、秋の空の、どこまでも澄みきったような高さと深さ、透明感がよく反映されている。第一連の全行を引く。「樹木はしんねりと口を閉じ/雲はもう無関心に山へ返ってゆく/空の高みのどこかに/窓がひらいていて/そこには透明な一つの部屋がある/古びた懐かしい椅子がおいてあるが/主人はいない/机には紫の水晶が静かに光っている/あの碧い透明な部屋のどこかに/あなたがいるはずなのだが/衣擦れのような風の音がしただけだ」。
「空の高みの
どこかに/窓がひらいていて」(3、4行め、下線は筆者)と言うのだから、「窓」は、見えないのだ。「窓」も、したがって、当然、「窓」のある手前側の“壁”も見えないが、部屋の中だけは見えている。そういうイメージであろう。いや、「透明な一つの部屋」(5行め)と言うのだから、見えないのは、手前側の“壁”だけではなく、向こう側の“壁”や“床”も見えないのであって、ただ、部屋の中に置かれているものだけが見える、そういうイメージととらるのが、適切だろう。「古びた懐かしい椅子」と「机」、机の上に置かれた「紫の水晶」が、まるでそれらだけが空の中に浮かんでいるかのように、「空の高み」に見える。そういうイメージととらえるのが適切と考えられる。そうとらえれば、「碧い透明な部屋」の表現とも合致する。「あの碧い透明な部屋のどこかに/あなたがいるはずなのだが/衣擦れのような風の音がしただけだ」の終わり三行の表現では、晩秋の季節感と「あなた」への喪失感とが一つになっていて、特に味わい深い。
最終連を引く。「ぼくは/夕暮れる時の港に残され/魂の目と耳をひらいたまま/はるかな星の海の訪れの静けさに/佇んでいる」。
「時の港」の比喩が、たいへん印象的だ。「港」からは、時に、“舟”が出る。その“舟”が、たとえば、生命の営みを終えた「虫たちとコスモスを乗せ」た「箱船」であることが、第三連からわかる。生き続ける限り、人は「時の港に残され」ることになる。それは、どうすることもできない、私たちの存在のあり方である。そのあり方を受け入れたうえで、私たちに何をどうすることができるのか(第二連の「だれもが」「抱え」ている「答えのない問い」とは、あるいは、このような問いのことだろうか)。「魂の目と耳をひらいたまま/はるかな星の海の訪れの静けさに/佇んでいる」の最終の三行は、そのような問いに対する、「答え」ではないしても、一つのありうべき「姿勢」を示す言葉として私は読んだ。
なお、この詩は、特に第一連と最終連がたいへんみごとな表現になっていると、私は考える。それだけに、第二連と第三連については、さらに推敲する余地があるように、私は思うのだが、どうだろうか。
「白球の夏」は、近江ならではの魅力ある内容と表現をもつという点では「時の港から」と共通するが、表現の完成度(すきのなさ)という点では、「時の港から」を超えているのではないか、と私は考える。長い詩であるが、次に全文を紹介したい。
第一連。「あの白球が/入道雲の空から/まだ落ちてこない」の表現によって、詩の世界にぐぐっと引きつけられた。
第二連。「空はグローブのように入道雲の手を広げ」という比喩を使った表現で、さらに詩の世界へ引き込まれる。入道雲の立ち上がる、夏の空の情景を思い浮かばせるとともに、第一連の「入道雲の空から/まだ落ちてこない」「白球」とのつながりから、「白球」が「グローブのよう」な「入道雲」につかまっているという言外のイメージを想起させる。
第三連。「まだ落ちてこない」「白球」が、「未知の空」へと「自らの手で」「打ち込」んだ「ぼく」自身のことであることが明らかにされる。第二連には、「あれは 若い日の/精一杯の 意味の問いかけ」の表現があるので、「ぼく」を「自らの手で」「未知の空へと」「打ち込む」ことには、「精一杯の 意味の問いかけ」が伴っていることがわかる。「意味の問いかけ」とは、「自分は何のために生きるのか」「自分は何を求めて生きるのか」という、“自分が生きることの意味”の問いかけと考えてよいのではないだろうか。第六連まで読むと、「ぼくが打ち上げたはずの/精一杯の希望への希求」という表現があり、「白球」の意味がよりはっきりするとともに、「意味の問いかけ」の内容を前述のように考えることの確かさも増す。
第四連。主題にからむ、エピソードの挿入。「(その中に白い指の君もいた)」の一行は、さりげない表現ながらたいへん効果的。十代後半の、異性へのほのかなあこがれを実感として思い起こさせる。この一行があるのとないのとでは、第四連の表現する内容が大きく異なる。
第五連。時間が、「今年」となる。
第六連。時間が、“いま”となる。「今年もまた/じっと空を追いかけている/声をかぎりに 声援を送り/あの白球の行方を追っている」。「何十年かが経ち」、なお“自分が生きることの意味”を問い続ける作者の姿がある。
最終連。「あの若い日の問いの白球が」「勢いよく投げ返される」ときとは、どういうときだろうか。“自分が人生において成し遂げた(あるいは、なした)こと”を、「おれもまずまずがんばった“というように、“成就感”をもって振り返ることができたとき、と私は読んだが、どうなのだろうか。
表現を丁寧にたどるほど、矛盾なく、意味がよりはっきりとしてきて、表現されている内容の深さがわかってくる。この詩は、そういう詩になっている。先に私が「表現の完成度(すきのなさ)」と書いたのは、このことである。
さて、第42号では、チャールズ・シュルツの漫画『ピーナッツ』(もちろん、スヌーピーやチャーリー・ブラウンが登場する、あれです)に取材した、万里小路の詩集が東北出版企画から2013年10月に発行予定であることが紹介されている。この詩集に収められるはずの詩については、このホーム・ページでも、「読んだ詩など」のページから進む「
日本の現代詩における山形の位置 ―「現代詩」の成果の紹介として―」の文章中で紹介し、感想を述べている。発行が楽しみである。
(以上、敬称を省略させていただきました。)
『山形の詩 アンソロジー・2013』(2013年10月10日発行)
山形県詩人会が三年ごとに発行している、会員の詩を集めたアンソロジーの第4集である。他県の「詩人会」の状況は、寡聞にして知らないが、山形県詩人会のように着実な活動を続けている会が、ほかにどれくらいあるのだろう。それほど多くはないのではないだろうか。このような活動が続いているのは、事務局長(現在の事務局長は、松田達男)をはじめ、事務局を務める方々、そして、今回のアンソロジーについては編集委員(委員長は、松田達男)の方々の熱意のたまものである。詩人会の活動にはろくに参加せず、こんなホームページを作っている自分を省みると、恥ずかしく思う。
とはいえ、『アンソロジー』については、私も、毎回、作品を寄せている。今回は、「草原の紙飛行機」という作品を寄せた。
「草原」に「くさはら」、「一時」に「いっとき」、「他」に「た」、「体」に「たい」とルビ。
さて、 今回の『アンソロジー』では、41人の詩人の詩を読むことができる。
このホームページですでに紹介した詩では、いとう柚子「たごとのつき」が収められている。
ここでは、この機会を逃すと、このホームページでは紹介できないかもしれない詩人(私の手元に普段送られてこない詩誌に参加している詩人や、どの詩誌にも参加していない詩人)の詩の中から、中江清満の詩を紹介し、感想を述べたい。ちなみに、中江が参加している詩誌『樹氷』は、以前は私のもとにも送られてきていたが、お礼も感想も申し上げないでいるうちに、送っていただけなくなってしまった。同様の詩誌は、ほかにもあり、そうした非礼をなくそうと思ったことが、このホームページを開設しようと思った動機の一つである。
今回のアンソロジーに収められている中江の詩は、「顔」と「雲」の二篇。
中江の詩には、以前から注目している。短い詩しか読んだことがないと記憶しているが、詩の短さは、中江の詩法と結びついた、特徴の一つであろう。
中江は、その詩において、散文的な言葉の使い方をしない。散文的に出来事を説明したり、情景を描写したりすることがない。感じ取ったポエジーを、短い言葉で、丁寧にすくい取るように表現する。時には、言葉が少なすぎて、伝えたいポエジーが読み手に伝わらないようなこともあったと記憶しているが、しかし、必要最低限の言葉でポエジーを表現しようとする、その言葉の使い方は独特で、かりにまねをしようと思ってもまねることが難しいのではないかと、私は思う。上の二つの詩でもそうだが、行間がたっぷりとってあることも、中江の詩法と本質的に結びついている。言葉を少なくし、行間にポエジーをかもし出す。そういう詩法である。
「顔」。すでに若いとは言えない年齢の、美しい女性を思い浮かべる。「過去は到着し」は、年齢と経験が顔に現れているということだろうと考えられる。問題は、「未来はもどってくる」。「顔」に「未来がもどっくる」とは、どういうことだろうか。「未来がもどる」ということは、それだけ「未来」が“増える”ということであり、ということは、こんな風な表現をしたのではポエジーを壊してしまうことになるが、意味だけを考えれば、つまり“若さがもどる”というではないだろうか。では、“若さがもどる”のは、どういうときか?“恋をしているとき”と、考えられる。この女性は、心中に恋心を隠しており、その恋心によって年齢に反するような“若さ”が顔に現れている。「顔」に、年齢相応の様相と年齢に不相応な様相がともに現れているということ。それが、「時の和解」ということであり、「謎」は、そのことをもたらした恋の事情。最後の一行は、その事情がその女性の口から語られることはないということの表現。そのように私は読んだが、どうなのだろうか。
以上の解釈が、どの程度作者の意図にかなっているかはわからないが、何にせよ、この詩は、内容によって成り立っている詩ではなく、表現によって成り立っている詩である。私は、読む回数を重ねるにつれて、大人の女性の美しい横顔を思い浮かべるようになった。西洋の絵画にある、美しい女性の横顔を、まさに真横から描いた絵、そういう絵を見るような趣=ポエジーが、この詩にはある、と私は思う。
「雲」。最終の二行は実景なのだろうか、それとも、作者の心象風景なのだろうか。どちらにせよ、シュールな印象を与える。そういうシュールな情景を含みながら、詩全体が表現しているのは、大きな“寂寥感”と言ってよいのではないか。そうした感じを、私は、この詩から、そのポエジーとして受け取った。
巻末の「名簿」上の記載によれば、中江は、まだ一冊も詩集を出していない。詩集という形で、まとめられたときこそ、中江の詩は、その真価が伝わりやすくなり、その詩集は非常に読みごたえのあるものになるのではないかと期待している。「金を出してでも読みたい詩集」になると思う。くれぐれも、購入しかねる金額にはしないでほしいと願っている。
(以上、敬称を省略させていただきました。)