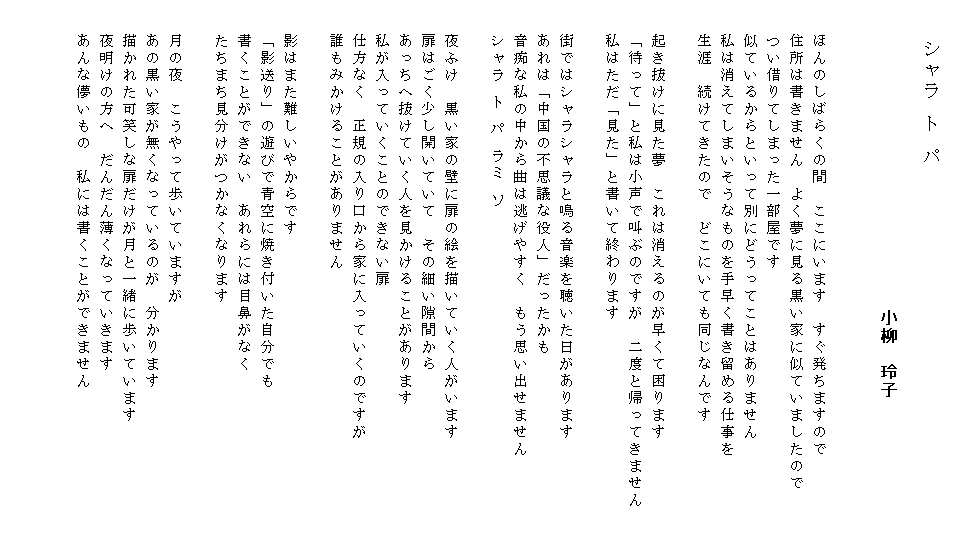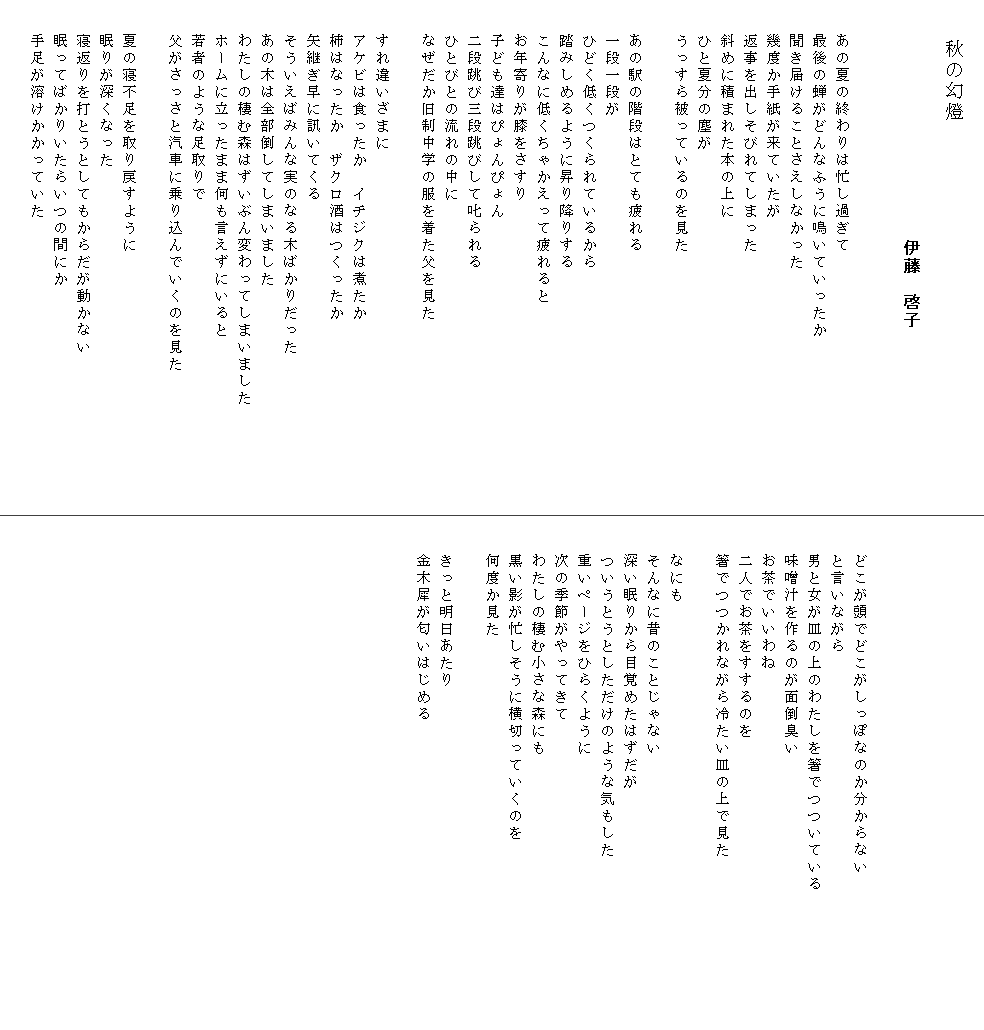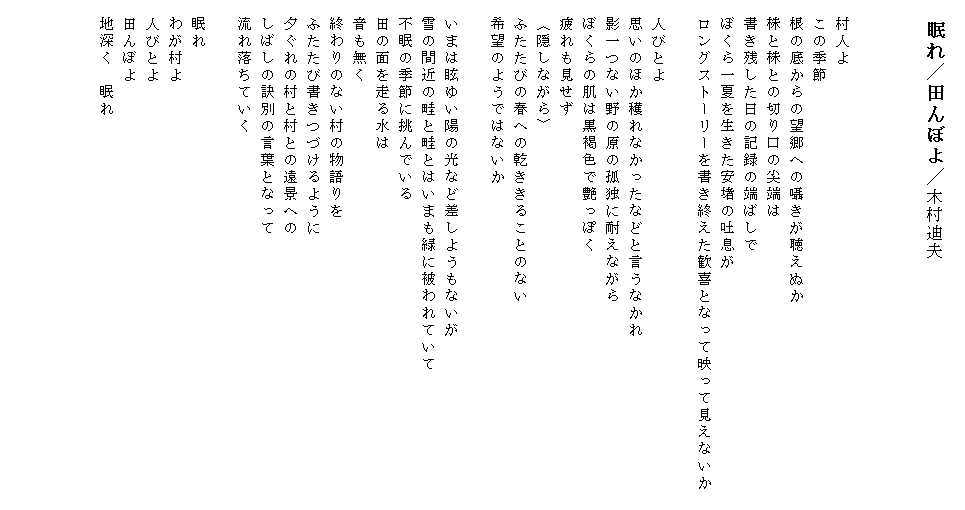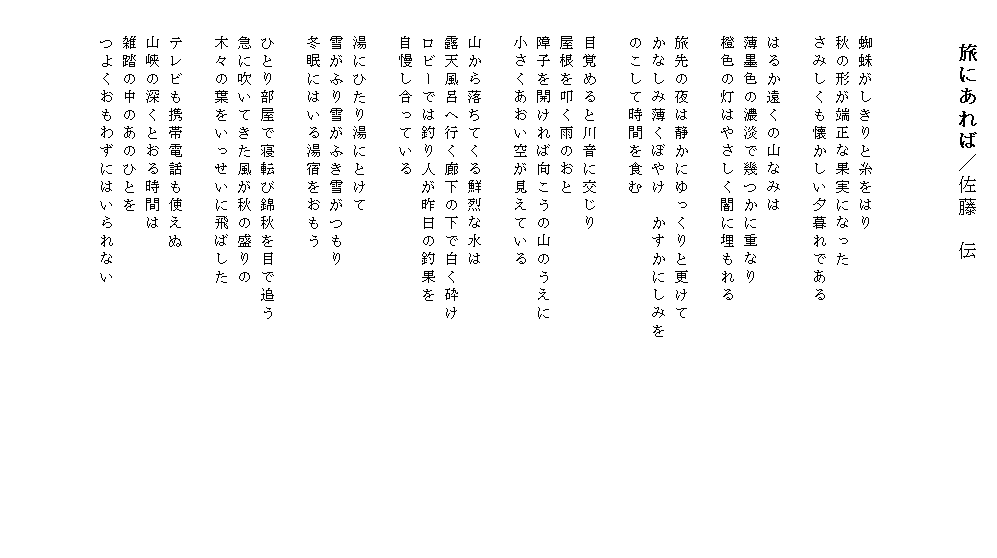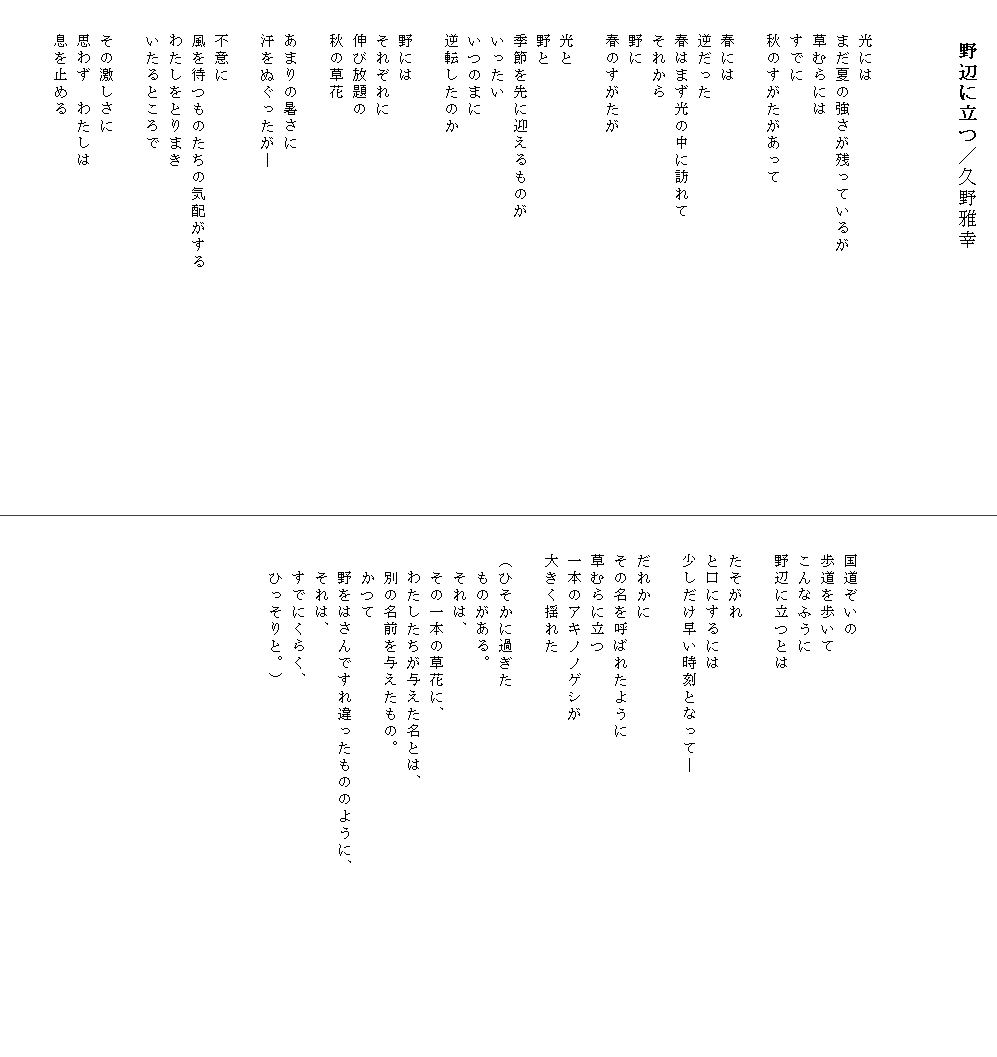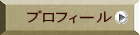

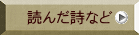
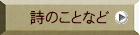
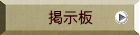
詩誌を読んで〈2014〉
『表象』第47号(2013年11月3日発行)、第48号(2013年12月8日発行)、第49号(2014年1月4日発行)、
第50号(2014年1月7日発行)
詩は、近江正人の詩3篇(第47号、第49号、第50号)、尾崎まりえの詩1篇(第48号)を読むことができる。発行人である万里小路譲による、石垣りんの詩の鑑賞が継続している。第47号では、スコット・ウォーカーについてのエッセイ、第50号では庭野富吉の詩「アンモナイト」の鑑賞が、それぞれ、万里小路によって書かれ、掲載されている。
万里小路が鑑賞を書いている、石垣りんの詩の一つ、「女」という詩を読んで、考えることがあった。
「女」は、三連からなる。
第一連「それでもまだ信じていた。/戦いが終わったあとも。/役所を/公団を/銀行を/私たちの国家を。」
さりげない表現だが、「それでもまだ信じていた。/戦いが終わったあとも。」に、“戦後の日本社会”への期待がこもっていて、大きな内容を蔵していると思う。
第二連「あくどい家主でも/高利貸でも/詐欺師でも/ない。/おおやけ/というひとつの人格を。」
皮肉の効いた表現。「役所」「公団」「銀行」「国」が、「あくどい家主」「高利貸」「詐欺師」とどう違うのか、同じではないのか、と考えさせられる。
第三連「「信じていました」/とひとこといって/立ちあがる。/もういいのです、/私がおろかだったのですから。」
視点の切り替えのみごとさに感嘆する。女が男に離縁を告げる際の決まり文句を使い、その場面をありありと想起させて、「おほやけ」への幻滅をみごとに表現している。
このように読むと、住民や住人、生活者、国民へのあるべき配慮に欠ける「おほやけ」の在り方、というより、そもそも「人格」と言えるものを持たない、ということはすなわち、“人間性に欠ける”ということになりがちな、「おほやけ」の在り方を鋭く批判した詩、そして、「人格」を持たないものを「人格」を持つもののように「信じて」いた自身の「おろか」さを省みた詩として、みごとである、と評価することができる。また、そのように評価することに、異論はない。
しかし、気になる点がある。
第三連。男にきっぱりと離縁を告げる「女」の姿が想起され、「おほやけ」に対する幻滅の表現としてみごとである、ということは、先にも述べた。しかし、男と「おほやけ」は、違う。一人の男に対しては「もういいのです」と言って、縁を切り、それですませることもできるだろう、一方、「おほやけ」に対しては、“縁を切る”というわけにはいかない。いかに幻滅しても、付き合い続けていくしかない。そして、一人の「女」に幻滅を告げられたところで、「おほやけ」にとってはいたくもかゆくもない。こうしたことに、石垣の思慮が及ばなかったということが考えられるだろうか。
そうとは、考えにくい。では、そうしたことを承知の上で、第三連を書いたとしたら、それはどういうことだろうか。
いま私が思いつくことは、三つある。
一つは、“心の中で縁を切って幻滅を告げる”ことを、一人の女がやったところで、「おおやけ」にとっては、いたくもかゆくもない、しかし、それが、この国の、多くの「女」によってなされた場合には、話が違ってくる、そのときには、「おおきけ」に大きな打撃を与え、「おほやけ」の在り方を変える力ともなる。そのことを、石垣は見据えていたのだ、と解釈することである。このように解釈すると、第三連は、一人の女の態度・自覚の表現にとどまるものではなく、この国の「女」たちへの呼びかけ・訴えかけをも含む表現ということになる。
もう一つは、第三連を、一人の「女」が「おおやけ」に対してできることの帰結を表現したもの、と解釈することである。
万里小路は、この詩について、「闘うべき相手がどこにも存在せず、闘う意志が殺がれていく状況を写し取っている」と、とらえている。そして、「信じていた」ことが「偽りであったと判明する。しかし、なす術がない。展開しうる状況はただひとつ<もういいのです>と席を立つことである。しかし、誰/何に向かってそうなしうるのか? <役所・公団・銀行・国>である。しかし、そこにひとはいない。<あくどい家主>も<高利貸>も<詐欺師>もいない。抽象的概念である<おほやけ>こそがそこに巣くっている。それをシステムと言い換えてもよい。システムが被る仕打ちはただひとつ、ひとりのおろなかな女に愛想をつかれることである。」と述べる。
万里小路は、第三連を、「闘うべき相手がどこにも存在」しない状況の中で、「闘う意志」の対象の不在を自覚した「女」が、「おおやけ」に対してなし得ることを表現したもの、すなわち、一人の「女」が「おおやけ」に対してできることの帰結を表現したもの、ととらえていると考えられる。
三つめは、男と「おおやけ」との違いにはあえて目をつぶって、きっぱりと男に離縁を告げる「女」の姿を、「おおやけ」に対する幻滅の表現として描こうとした、と解釈することである。このように解釈すると、石垣は、「内容」上の不備には目をつぶって、「表現」としての魅力を優先させたということになる。
何ともややこしい話になってしまって、恐縮である。
私が述べたいのは、表現においても、内容においても、ともに魅力的で、かつ不備や矛盾のない作品をつくることの難しさである。
全体として魅力ある詩なのだが、ある部分に不備があると思われて、せっかくの魅力が損なわれてしまうこと、魅力的な作品世界が、一ヶ所に矛盾があると思われることによって、壊れてしまうこと。そういうことは、詩を読んだり、書いたりしていると、ときに出くわすことである。不備がないか、矛盾がないか、推敲に推敲を重ねる必要があると、自戒を込めて、思う。
石垣ほどの詩人であっても、魅力的な表現の内に不備を含んでしまうということが、あるいはあったのではないか、と思った次第である。もちろん、それは、“げすの勘ぐり”であるかもしれないけれど。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『きょうは詩人』第25号(2013年9月7日発行)、『きょうは詩人』第26号(2013年12月15日)、
個人通信『萌』No.40(2014 冬の号)
『きょうは詩人』第25号では、苅田日出美の詩2篇、吉井淑の詩2篇、小柳玲子の詩2篇、長嶋南子の詩2篇、万亀佳子の詩2篇、福間明子、森やすこ、伊藤啓子、鈴木芳子、古谷鏡子の詩各1篇、長嶋南子のエッセイ1篇を、読むことができる。
『きょうは詩人』第26号では、伊藤啓子、吉井淑、福間明子、小柳玲子、長嶋南子、古谷鏡子の詩各1篇、森やすこの詩2篇、鈴木芳子の詩2篇、万亀佳子の詩2篇、苅田日出美の詩2篇、吉井淑のエッセイ1篇を読むことができる。
『萌』No.40では、伊藤啓子の詩3篇を読むことができる。
『きょうは詩人』第26号掲載の、小柳玲子の詩「シャラ ト パ」が、特に印象に残った。
第一連に「黒い家」が出てくるが、これは、第25号に載る、小柳の二つの詩「夢びと」「夜回り」にも、出てくる。
「夢びと」では、「家が建っている とても黒い 私の家ではない/でも私のようなものがうようよと群れている気配」とあり、「夜回り」では、「月の晩 霧の明けがた とても黒いあの家を見かける/軍服姿の男がこっそりと裏口から出てくるのに出会う」とある。二つの詩からは、「黒い家」が、自己の“意識の枠組み”を示すものなのだろうと想像がつく。二つの詩は、ともに、シュールレアリスム的なイメージのうちに、「なんでもないからっぽのものが好き/からっぽの馬鹿げて無駄なところへいくところ」(「夢びと」)、「家の中では古い古い日の牧師様が イザヤ書を読まれている」(「夜回り」)のように、自己の意識の特徴的なありよう(つまり、“自分らしさ”)を表すことばが明示的、暗示的に示されていて、魅力的である。
その二つの詩を受けての(と言ってよいと思う)、「シャラ ト パ」である。
第一連から第三連は、“自分らしさ”の表現として読むことができる。その一方で、第一連の表現は、「私」がいま「夢」の中にあるのか、それともその外にあるのかを、不明確にしている。
第四連から第六連は、シュールレアリスム的なイメージの魅力が際立っている。安易な解釈をせず、イメージ自体を味わう、想像してそこから感じられるものをもってその“意味”とする、という読み方をするのが基本であろう。解釈は、イメージを十分に味わったあと、“想像してそこから感じられるもの”を受けとめ、それを踏まえて、それと矛盾しないように行わなければならない。最終連3行目のイメージが、なんと魅力的であることか。はかないが暗くはなく、ユーモラスだがさみしい。
第六連で「あの黒い家が無くなっている」というのは、“意識がその枠組みを失ってしまった状態”として読むことができる。その中にさまざまな意識や無意識を詰めこんで、「私」を「私」として成り立たせていた、まとめあげていた“枠組み”がなくなってしまった状態。そのような状態は、それ自体がシュールレアリスム的である。
「夜明けの方へ だんだん薄くなっていきます」は、目覚めへと向かっている状態、「夢」の世界から現実の世界へ向かっている状態とも読めるが、意識自体が失われようとしている状態とも読める。その多義性もまた、―文学、美術、音楽を問わず、優れた芸術の多くがそれを、いわば“深み”として、もっているように―大きな魅力の一つである。
第26号の巻頭に載る、伊藤啓子の詩「秋の幻燈」もまた、特に印象的な作品であった。
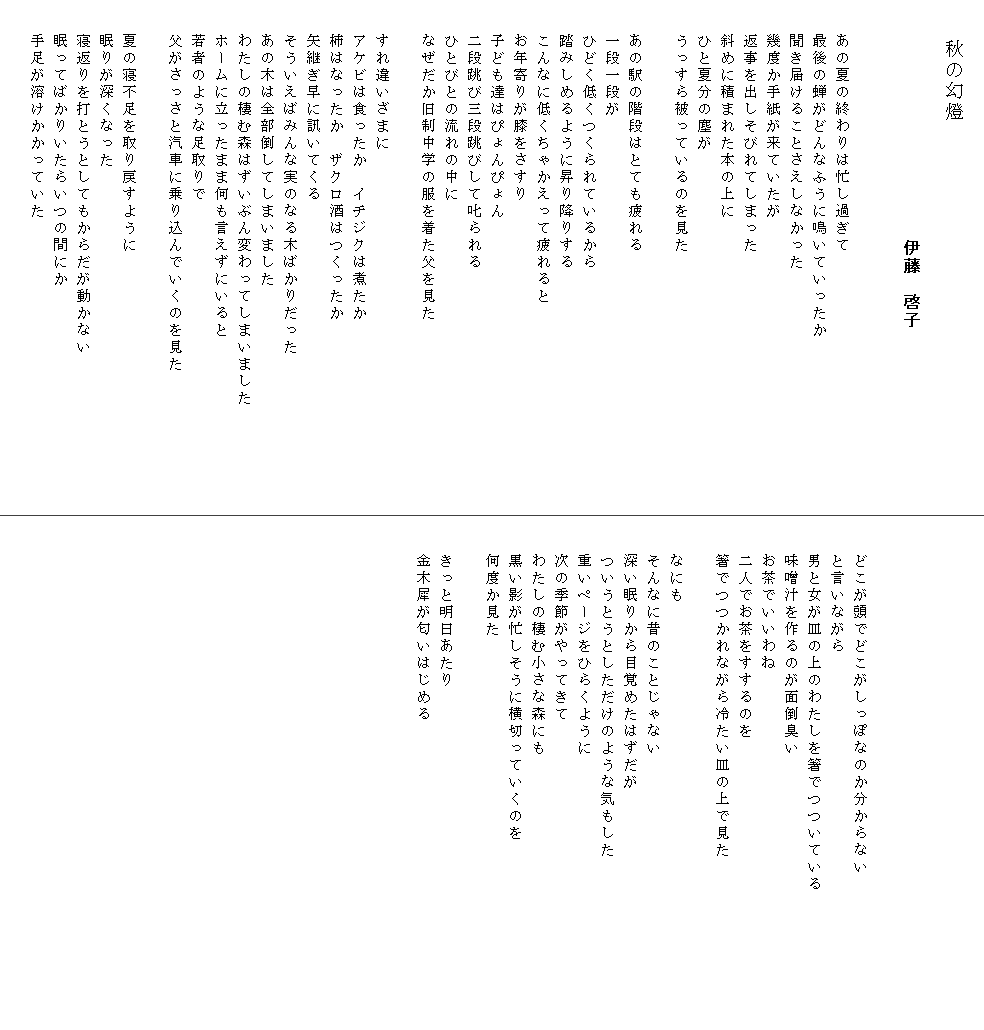
全部で六連からなる、長い詩だが、どの連も味わい深い。
第一連の、季節感と生活感が不可分に結びついた表現。第二連の、いきなり「あの駅の階段」に目が向けられる、あざやかな視点の変化。そして、そこから始まる、奇妙な現実感を漂わせた第三連までの表現。第四連の、眠りと夢の感覚。そこにも、第三連と共通する“奇妙な感じ”がある。第五連の「重いページをひらくように/次の季節がやってきて/わたしの棲む小さな森にも/黒い影が忙しそうに横切っていくのを/何度か見た」は、とりわけみごとで、味わい深い表現と思う。季節感とともに、「森」の“異界性”も、魅力的な表現でとらえられている。最終連の味わい深さも、大胆な視点の変化を伴って、格別である。
なお、第25号に掲載されいる伊藤の詩「捨て子」も、たいへん印象的な作品である。「秋の幻燈」とどちらを大きく取り上げるべきか、迷った。題名の「捨て子」は、第四連の表現による。全部で五連からなる詩であるが、第四連と第五連を、次に引く。「帰り支度を察したのか/樹々の揺らぎがおさまり/森が安堵しているように見えた/振り返ってはならない/捨てられるのはいつもわたしたち//帰り道は/肩のあたりがおもくなる」。最終行は、帰り道をたどるさみしさの表現として読むことができるが、「森」から、目に見えない何ものかがついてきているとも読める。ここにも複層的な意味の重なりがあって、味わい深い。
『きょうは詩人』第25号には、伊藤啓子の詩「捨て子」が載っている。「森」の“異界性”を、「七月」の季節感で包み込んだような作品である。「秋の幻燈」の「森」と、「捨て子」の「森」が、同じ森なのかは、わからない。しかし、“異界性”が共通しており、同じ森、少なくとも“つながった森”として読むことができる。そう読めば、「捨て子」と「秋の幻燈」を、連作として読むことができ、連作として読んだときには、個別に読んだときとは異なる味わいが加わることを、言い添えておきたい。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『山形詩人』第84号(2014年2月20日発行)
木村迪夫、久野雅幸、近江正人、佐藤伝、高啓、万里小路譲、佐野カオリ、山田豊、菊地隆三、高橋英司による詩、計11篇と、阿部宗一郎の俳句について清水哲男氏がブログ「増殖する俳句歳時記」に載せた文章の引用を、読むことができる。
木村は、『山形詩人』第80号に載せた詩「眠れ/田んぼよ」の、“もとの詩”を載せている。
第80号に載せた詩は、読売新聞2009年11月21日「ウィークエンド文化」に掲載された詩の改作であったのだが、今回、第84号には、読売新聞に掲載された詩を転載している。初出時の表現にもどしたわけである。“もとの詩”と言うのは、そういう事情からである。
次に、全行を引きたい。
第80号掲載の詩については、当HPに全行を掲載し、私は、次のような感想を述べている(
比較のため、第80号掲載の詩を参照してほしい)。
まず、特筆したいのは、この詩の「調べ」である。全体に、生命感の感じられる、生き生きした調べが一貫している。
“もとの詩”にも、もちろん、“調べ”はある。詩に表現されている時期の実感に根ざした“落ち着いた調べ”があると思う。また、その“調べ”には、農の仕事に取り組む人にふさわしい“力強さ”も感じられる。しかし、“改作”にあって、私が以前に取り上げた「生命感の感じられる、生き生きした調べ」、「生命の躍動を思わせる、『勢い』を伴っ」た、“どんどんとたたみかけていくような調べ”は、この詩にはない。
「わかりやすい」という点では、今回のもののほうが、わかりやすい。また、“改作”にあった表現の重複がなく、表現として整理されているという印象がある。しかし、その一方で、整理された「表現の重複」は、「調べ」の上では、「ことばの繰り返し」として、「調べ」をつくりあげる大きな要素であった。
今回、“もとの詩”をあらためて掲載したということは、木村は、“改作”よりも、“もとの詩”のほうがよりよいと判断したのだろう。
どちらがよい、などということは、私には言えない。というより、正直に言って、私には、どちらがよいのか、判断することができない。しかし、“改作”と“もとの詩”では、根本的な違いがある、と考える。
“改作”では、「ひと夏」の仕事を終えた「安堵」と「歓喜」が、「ふたたびの春」への思いに直結していて、そうした気持ちが「生命感の感じられる、生き生きした調べ」となって表れ、詩全体を貫いていた(“もとの詩”にはない、最終連における「ふたたびの春の/醒めのために(死ぬなよ)」の2行は、そうしたことの端的な表れとみることができる)。一方、“もとの詩”では、収穫が終わったあとの、「雪の間近」な時期における“休息”の気持ちが中心となっており、最終連で繰り返される「眠れ」のことばに強い実感がこもる。
“改作”にも、“もとの詩”にも、それぞれに、詩としての魅力がある。繰り返しになるが、“もとの詩”をよりよいとする木村の判断に異論があるわけではない。“もとの詩”の第三連、4~10行目で表現されている「情景」の魅力は、“改作”よりも、よりはっきりと伝わってきて、読みごたえがある。
以前に紹介した詩が大きく改められたので、紹介者としてそのことを伝える責任があるとも考え、やや詳しく述べた。
さて、今号に掲載の詩の中で、私が最も魅力を感じたのは、佐藤伝の「旅にあれば」である。
全体に、内容にふさわしい、落ち着いた「語り口」で表現されている。そして、はっきりとイメージを思い浮かばせ、しっかりと情感を伝える、無駄のない、端正なことばづかい。
そうした表現を通して、旅先の宿でひとり時間を過ごしているときの思い、「さみしくも懐かしい」気持ちにひたる思いが、実感として伝わってくる。「さみしくも懐かしい」ということは、“ひと恋しい”ということにもつながるわけであり、最終連の表現は、強く共感を誘う。
佐藤の旅の詩は、寂寥感とひと恋しさが、せつなく伝わってきて、魅力的である。
『山形詩人』第81号に載る「日々の余白に」もそうであった。
私は、「大分むぎ焼酎二階堂」のテレビコマーシャルが大好きなのだが、佐藤の旅の詩を読んでいると、あのコマーシャルの、あの郷愁感あふれるナレーションを思い出す。これは、悪い意味でとらないでもらいたいのだが、この詩などは、そのまま、あのコマーシャルで使われ、あのナレーションで語られても、まったくおかしくない、というか、実にふさわしいのではあるまいか(プロデューサーの目にとまらないかな、などと思ってしまう)。
私は、「風を待つ」という詩を載せたのだが、あらためて読み返すと、あまりにももの足りない詩だ。ここに、改作を掲載したい。題も、「野辺に立つ」と改めたい。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)