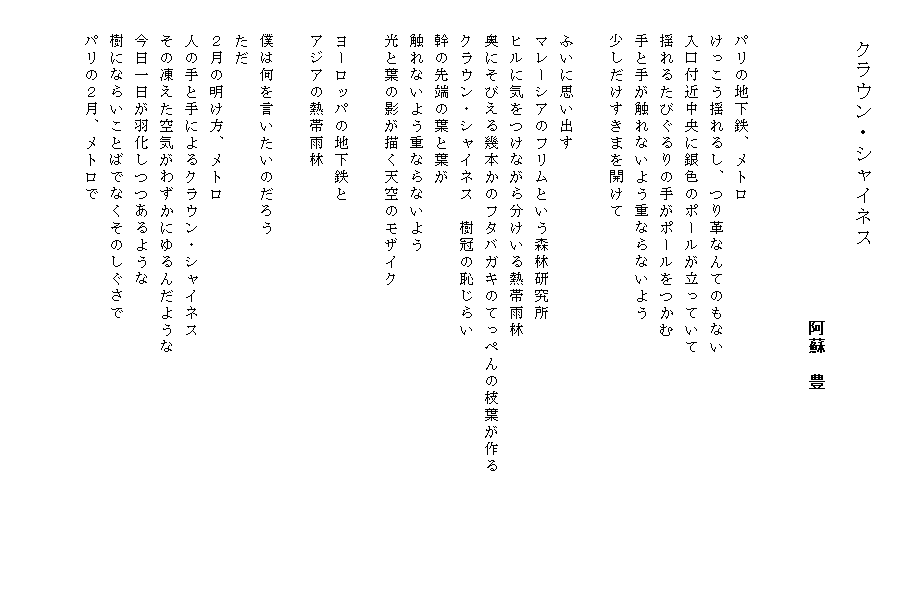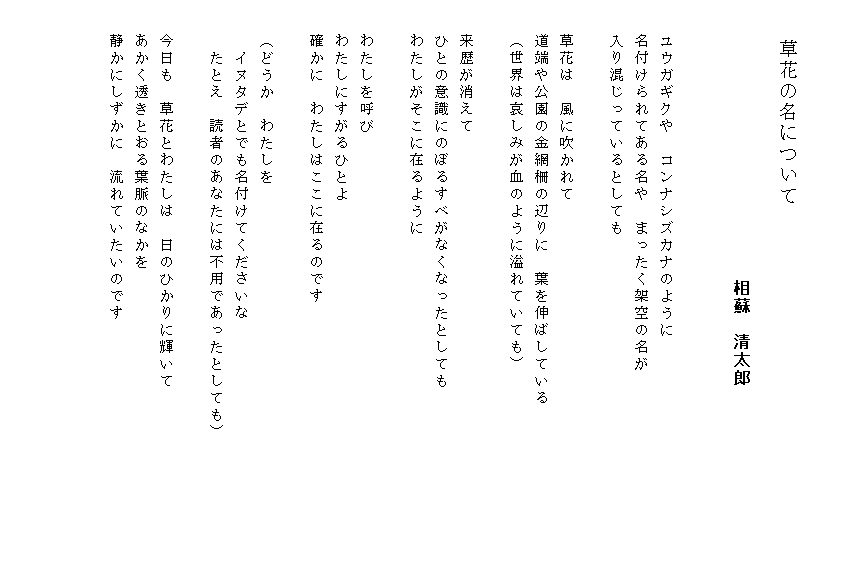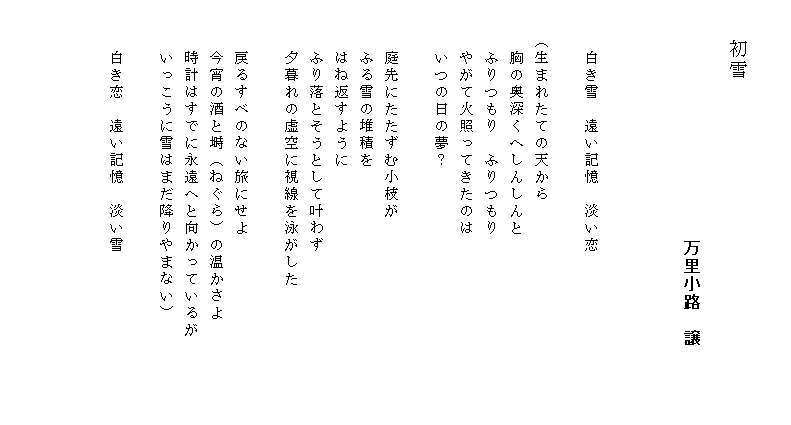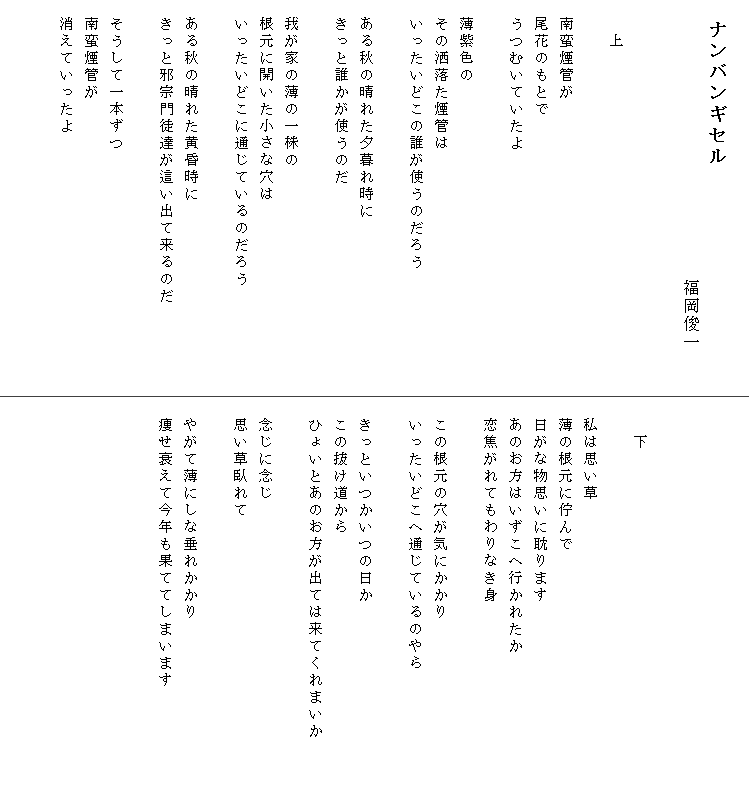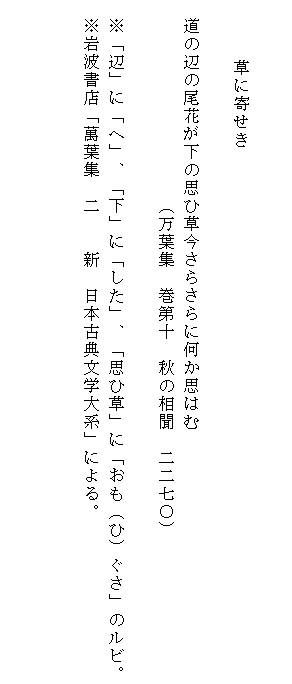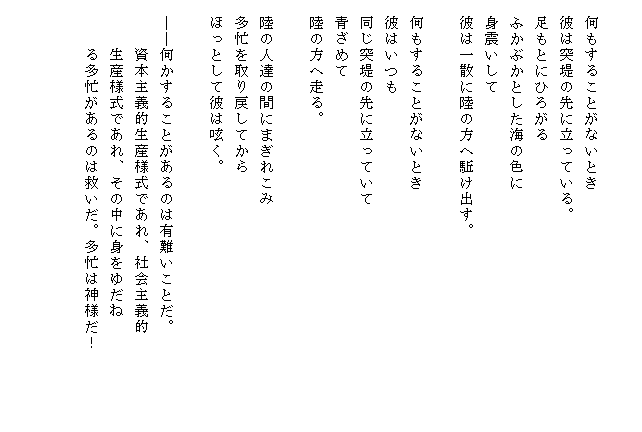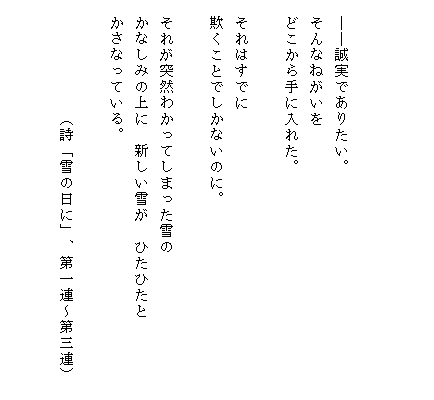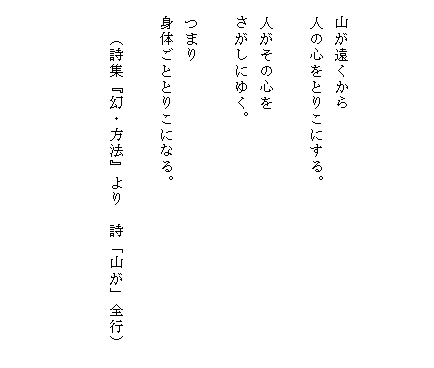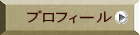

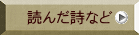
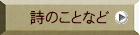
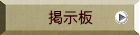
詩誌を読んで〈2014〉 その2
『シテ』創刊2号(2013年11月30日発行)、第3号(2014年3月15日発行)
『シテ』は、山形県の庄内地方、酒田市と遊佐町に在住の詩人たちによる詩誌である。同人は、相蘇清太郎、阿蘇豊、今井富世、江口暢子、大江進、高瀬靖、早川孝子、南悠一の8人。「シテの会」として、月1回の例会をもち、自作詩および『シテ』の合評会、句会、好きな詩の鑑賞会など、「ことばを磨く活動」を行っているとのこと。そうした活動の成果が『シテ』誌で読むことのできる詩に表れている、と私は思った。
『シテ』創刊2号では、阿蘇の詩「クラウン・シャイネス」に大きな魅力を感じた。部分的に引いても詩の魅力は伝わらないので、全行を紹介したい。
「クラウン・シャイネス」ということばは、この詩を読んで初めて知った。そして、すぐに記憶した。ことば自体が、強くうったえかけるものを内包していると思う。
それが、どういうものかは、詩の第二連を読むと、理解できる。「幹の先端の葉と葉が/触れないよう重ならないよう/光と葉の影が描く天空のモザイク」。樹木の密集する「熱帯雨林」において、まるでお互いに光を十分に受けとめることができるようスペースを譲り合うかのように、隣り合う木々が、枝葉を重ねることなく生長し、見上げると、重なりのない樹冠の枝葉が、精巧な透かし彫りのように、「光と葉の影が描く天空のモザイク」をつくり上げている。そういう状態を表すことばであることが、詩を読めばわかるように書かれている。うまいなぁと思う。そして、言わば“志の高さ”を感じる。こういう特殊な意味をもつことばを、「注」に回さないで、詩を読めばその意味がわかるようにしている点、しかも「散文的な説明」にならないように、すなわちリズムを与え、イメージが思い浮かぶようにし、また自分(作者)がそこに感じとっているものが読者に伝わるように表現している点。
第一連。作者が表現しているのは、まったく日常的な、気にとめる人はまずいないであろうと思われる、ありふれた、パリの地下鉄の、車内のようすである。しかし、その何げないようすに、作者の意識は反応した。
第二連。作者は、第一連の人々のようすから、マレーシアの熱帯雨林における「クラウン・シャイネス」を思い浮かべ、前述したように、巧みに表現している。
第三連。何げなく置かれているような二行だが、「僕」の意識の動きを表現していて、効果的である。
第四連。3・4行目「2月の明け方、メトロ/人の手と手によるクラウン・シャイネス」という短く、印象的な表現で、第一連の人々のようすと第二連の「クラウン・シャイネス」が明確に結びつけられ、第一連のありふれたようすに、“意味づけ”がなされている。
詩の主題は“共生”ということばで表すことができるだろう。熱帯雨林における樹木の“共生”と、「パリ」という大都市における人々の“共生”とが、作者の中で結びついたことによって、この詩は成立したと考えられる。作者は、しかし、そのことを語らない。「僕は何を言いたいのだろう」と、「何を言いたい」のか、その読み取りは、読者にゆだねている。ここも、うまいなぁと思う。ここで、“共生”についてあれこれ語れば、詩はひどく理屈っぽくなり、場合によっては、「散文的な説明」になってしまう。それを避けて、「凍えた空気がわずかにゆるんだような」「今日一日が羽化しつつあるような」という、“あたたかみ(詩をきちんと読めば、“共生が成り立っていることを感じてのあたたかみ“とわかる)”と“一日の活動が始まることを喜びとして感じる気持ち”を表現して、それ以上のことを語らないで終わっている。
出勤する前や、出勤の途中、緊張や憂鬱をやわらげて、気持ちを“あたたかな”ものにしてくれる、そういう詩であると思う。
この詩を読んで、私は、詩の成立要件を「発見」と「飛躍」ということばで表す、高階杞一の考え方を思い起こした。孫引きであるが、私自身が共感している考え方でもあるので、次に紹介しておきたい。
「一番大事なのは、固定観念、先入観を捨て去ること。それが、発見への近道です。そうすることによって、見えないものが見えてきたり、聞こえないものが聞こえてきたりするんじゃないかなと思います。そのためには目や耳を鍛えることが大事です」
「それでは、『発見と飛躍』の『飛躍』とは何か。一口では言いにくいんですけれど、発見したことを深めたり、普遍化したりする方法の一つだと理解してもらえたらと思います」
(1999年講演「発見と飛躍」から。ここでの引用は、砂子屋書房版現代詩人文庫『高階杞一詩集』所収の神尾和寿「〈どこか〉への約束」による。)
阿蘇の詩「クラウン・シャイネス」には、高階が言うところの「発見」と「飛躍」がある、と私は考える。
教えられることが多かったので、阿蘇の詩への言及が長くなった。
第3号では、高瀬靖の詩「弟たちのこと」に表現された“覚悟”とも言える気持ちと、相蘇清太郎の詩「草花の名について」の諧謔が、特に印象に残った。相蘇の詩は、最終連の抒情的な表現も、特徴的で、味わい深い。全行を紹介しておきたい。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『表象』第51号(2014年1月23日発行)、第52号(2月3日発行)、第53号(2月14日発行)、第54号(3月11日発行)、第55号(3月28日発行)、第56号(4月1日発行)、第57号(4月19日発行)
詩は、51号に万里小路譲「初雪」、52号に万里小路譲「いま」、53号に近江正人「風の野に立ち ~三陸から」、54号に万里小路譲「生という死の母からの旅立ち ―故吉野弘氏に」、55号に近江正人「新学期」、56号に奥山美代子「白い駅」、57号に近江正人「慢性水晶病」が載る。
詩の鑑賞は、51号に石垣りん「初日が昇るとき」、52号に庭野富吉「寒波襲来」、53号に石垣りん「三十の抄」「ちいさい庭」、茨木のり子「居酒屋にて」、54号に吉野弘「六体の石の御仏」「病院の庭の芝生を」「漢字喜遊曲」、55号に吉野弘「韓国語で」「闇と花」、近江正人「冬の裸樹」、56号に吉野弘「「止」戯歌」「過」、石垣りん「夫婦」、57号に久野雅幸「さみしい」の鑑賞が、載っている。書き手は、いずれも万里小路譲。
他に、第51号に、ジョン・レノン「God」、ビートルズ「Free As A Bird」、第57号に、小椋佳「デジャブー」、小田和正「言葉にできない」の鑑賞が載る。
万里小路譲の詩「初雪」を、味わい深く、読んだ。
※「(ねぐら)」は、「塒」のルビ。
第一連と最終連は、俳句と捉えるべきだろうか、それとも、三つの言葉の連なりと捉えるべきだろうか。どちらでもよい、そんなことは考える必要がないと、考える人もいるだろう。しかし、私は、そうは考えない。
俳句とするか否かは、第一連と最終連の、この詩の中における“自立性”にかかわるからだ。俳句とすれば、それぞれの連は、それ自体が完結した俳句として読めるもの、鑑賞することが可能なものとなり、詩の中において、強い“自立性”をもつことになる。一方、俳句でない、三つの言葉の連なりとすれば、“自立性”は、あくまでも一篇の詩の中での一つの連としてのそれにとどまることになる。
第一連と最終連のどちらについても、三つの言葉を単独に並べたものではなく、三つの言葉をひとまとまりとして捉えるべきであることは、表現に表れている。すなわち、二つの連において、どちらも、最初の言葉だけが「白き雪」、「白き恋」と、「白い」という口語ではなく、「白き」という文語を使って表現されているということである。第一連を取り上げて述べると、仮に「白い雪 遠い記憶 淡い恋」と表現されているのであれば、三つの言葉を個別に並べたと捉えることもできるだろうしかし、「白き雪 遠い記憶 淡い恋」と表現され、かつ、最終連の「白き恋 遠い記憶 淡い雪」と、同じつくりで呼応する以上は、第一連と最終連の三つの言葉は、どちらも、三つの言葉を一つのまとまりとして捉えるべき表現上の仕組みをもっていると考えるのが妥当である(念のため述べておくと、これは、作者の意図を推し量っているのではない。作者の意図はさておき、そう考えるべき表現上の仕組みがあると指摘しているのである)。
三つの言葉を一つのまとまりとして読むべき表現上の仕組みがあり、また、音数が「5・6・5」と「5・7・5」の一音足らずであり、加えて、「白き」という文語の使用があり、さらに、「雪」という季語とみなせる語がある。以上のことを考え合わせるならば、第一連と最終連は、それぞれ、単なる三つの言葉の連なりではなく、俳句(もちろん、いわゆる、字足らずの俳句)ないしは“俳句的な表現”として捉えることが妥当であると考えられる(繰り返して述べるが、これは、作者の意図の推測ではなく、表現を根拠とする解釈の妥当性の主張である)。
“俳句的な表現”という奇妙な言葉を使ったのは、“俳句になろうとしてなりきれなかった表現”として読みたいという考えが、私にあるからだ。
俳句として成り立つには、込められる思いがあまりに口語自由詩的であったために、“俳句的な表現”として一篇の詩の中に位置づけられることとなった、そういう表現として、第一連と最終連を読むのが、私はふさわしいと思う。
「淡い恋」が、いかに「胸の奥深く」で「火照ってきた」にしても現実としてよみがえるはずがなく、「初雪」が、いまは「降りやまない」にしても結局は「淡い雪」として根雪にはならずに消えていく、そうしたことがあたかも表れたかのように、第一連と最終連の表現は、俳句になることを志向しながら、結果的には“俳句になりきれずに口語自由詩の一節となった”、そういう表現として読むのがふさわしいように、私は思う。「白き」という文語の使用で始まりながら「遠い」「淡い」という口語の使用に移って終わっていることも、そう捉えることがふさわしいと思う理由の一つである。
これは、もちろん、作者の意図の推測ではない。また、表現を根拠とする妥当な解釈の主張でもない。表現を踏まえて考えたときに読者にゆるされるであろう(誤りとはならないであろう)と判断される読み方の範囲内での、一つの読み方の提案である。
「初雪」が、「遠い記憶」の中から、恋の記憶を引き起こす。「白き」「淡い」という形容句の下で「雪」と交換が可能な、そういう恋である。
初雪を目にしながら、遠い恋の記憶にふける、そんな現在の時間を話主は過ごしている。その時間は、「戻るすべのない旅」の過程として、「永遠へと向かっている」という性質を免れることなく、過ごすにつれて消え去ってゆくが、しかし、「今宵の酒と塒の温かさ」と「降りやまない」「雪」、「恋」の「記憶」が、現在という時間に、虚無に陥らずにすむ、意味を与えている。
そういう内容の詩として、私は読んだ。
「恋」と「記憶」と「雪」は、どれもはかないものではあるけれども、この詩においては、むしろ現在という時間に意味を与えるものとしてある。
第一連と最終連での「雪」と「恋」との交替は、現在という時間(意識)における前景と後景との交替を表している。
そのように私は読んだが、これははたして作者の意図に合致しているだろうか。
奥山美代子「白い駅」での、「都会に行く孫」を見送った「祖母」の思いを託された「真っ白なハンカチ」の比喩(私は、「真っ白なハンカチ」は、「千切れるほど手を振った祖母」の手に握られていたのではなくて、あくまでも比喩、実体としてあるのではなくて、祖母の思いを形象化した比喩と捉えて読んだのが、どうなのだろうか。表現上は、そう読むのが妥当であると考える。)と、近江正人「慢性水晶病」での「六の神秘」の発見・表現も、印象に残った。
さて、第57号で、万里小路は、拙作「さみしい」を取り上げて、鑑賞を書いてくれている。「さみしさ」の理由を、「それは心を回復させ、精神を立ち上がらせる契機のひとつの感情なのであった」ととらえている点や、「時間が止まるのは死によってであり、その総体が眺められるのはその瞬間である」「さみしさとは何か? 眺められうるものとして、それが自らの外にあったことを知るのは、臨終の間際であろう。宇宙もまた、さみしいのであったと。」という指摘が印象に残った。
万里小路は、拙作の全行を紹介してくれている。それを読んで、一部修正する必要を感じた。このHPの「書いた詩など」に収めている「
新年を迎えて」の中に、「さみしい」を載せているが、一部を修正してある。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『E 詩』24号(2014年5月2日発行)
詩は、福岡俊一「シューベルト讃」「ナンバンギセル」、細矢利三郎「山陰」、阿部栄子「小道」「白薔薇のようだった範子」、芝春也「廃墟の灯明」。エッセイは、いとう柚子「ひとつで二度美味しい?」、芝春也「エロスの詩②」。
福岡俊一の詩「ナンバンギセル」が、よい詩だと思った。
「ナンバンギセル」は、ススキなどの根元に寄生する1年草。秋になると、キセルを逆さまにしたような姿を見せて、紫色の花を咲かせる。開花期までは地中にあり、開花期になると地上に姿を見せるので、突然現れたという印象を受ける。姿を知らない方は、ぜひネット検索等で見てほしい。緑素を持たず、寄生した他の植物から養分を摂る寄生植物であり、他の植物とは異なる、特異な姿をしている。
その特異な姿は、突然姿を見せることと相まって、“異界”に通じる印象を与える。「ナンバンギセル」という名前が、「南蛮」という“異国”を含むことも、その印象を強くすることにつながっていると言えよう。
福岡の詩は、「ナンバンギセル」のそうした印象を、よくとらえている。「上」の詩の第4連、「下」の詩の第2連に表れる「穴」は、まさに“異界”に通じる印象を象徴的に表現するものとなっており、「上」の第5連、「下」の第3連の印象的なイメージを導いている。
「上」も「下」も、連と連とのつながりがよく、無駄な表現がない。
「上」の最終連は、季節の移りゆくはかなさを、ユニークな表現で、しみじみと感じさせる。「下」の最終連は、1年草として枯れてゆく「思い草」(「ナンバンギセル」の異名)の姿が、“思い焦がれ思いかなわず息絶える”という、平安朝以来伝統的に描かれきた女性の姿と重なっており、ここでは和歌・物語的な深刻さよりむしろ歌謡的を趣を感じさせる点もユニークで、味わいがある。
「上」も「下」も、花の名前と姿をモチーフとして、そこから一篇の詩を成り立たせうる魅力的なイメージを思い浮かべ、無駄なく展開して、リアリティを保ちながら、味わいのある情感を感じさせる。ともに、よい詩だと思う。「草臥れて」に「くたび(れて)」のルビを振らなかったのも、「思い草」と「草臥れる」を、文字の上で掛け合わせようという意図のためだろうか。
さて、ここからは、福岡の詩を離れて、植物の名前について、思うことを述べたい。
「ナンバンギセル」は、幸せな植物である。“怪異”とか“奇怪”といった言葉で表現されても仕方がないような姿に対して、「思い草」(こちらの方が古名で、次に示すが、万葉集にも「思ひ草」に寄せて詠んだ短歌が載っている)や「ナンバンギセル」といった、風情のある名前を付けてもらえたのだから。万葉集には、次の一首が載る。
この和歌も、よい歌だと思う。「道の辺の尾花が下の思ひ草」のイメージを受けて、「今さらさらに何か思はむ」(今さらもうあのひとのことを思ったりはしない)と率直に思いを述べて終わっている。あらずもがなの技巧、言わずもがなのもの言いのない点がよいと思う。「思ひ草」については、「新 日本古典文学大系」では「未詳」としているが、「ナンバンギセル」のこととする説が有力のようである。ともあれ、現在では、「思い草」は「ナンバンギセル」の別名とされている。
一方、草花の中には、“ひどすぎる”と言わざるをえない、気の毒な名前を付けられたものもある。私の知る中では、“ひどすぎる”名前の第3位は「ブタナ」、第2位は「オオイヌノフグリ」、第1位は「ヘクソカズラ」である。
次の写真が、「ブタナ」。
タンポポに似ていて、タンポポよりも長い茎が途中で枝分かれして花を付ける。外来種で、私の住む山形県天童市近辺では、近年進出が著しい。外来種で、芝生を枯れさせるとされ、在来種の植物へのよからぬ影響も懸念されるので、憎しみを込めてあえて「ブタナ」と呼びたいという方もあるかもしれない(名前の由来は、他にあります。念のため。)。しかし、それにしても、同じような“強力外来種”である「セイタカアワダチソウ」程度の名前が付いてもよかったのではあるまいか。別名も、「タンポポモドキ」とさえない。ともかく、「ブタナ」では、風情ある花として詩の中に登場することは考えにくい。
次の写真は、「オオイヌノフグリ」。
「フグリ」の意味がわからない方は、辞書を引いてほしい。ここに書くと、このHPがフィルタリングの対象になってしまいそう(?)である。
早春の道端でよく見かける、他の花に先んじてかれんな花を咲かせる草花である。名前の由来は、この花に似て、この花とは別の「イヌノフグリ」(現在は、絶滅が危惧されている。オオイヌノフグリが外来種なのに対して、こちらは古くから日本にある)の実が犬の「フグリ」に似ていることによる。「天人唐草(てんにんからくさ)」が別名とされることもあるようだが、それが「イヌノフグリ」の別名なのか、「オオイヌノフグリ」の別名なのか、あるいは両方の花の別名なのか、私にはわからない。
他の花のまだない時期にかれんな花を咲かせるので、よく目につくのだが、「オオイヌノフグリ」という名前で風情のある花として詩の中に登場することは、やはり、考えにくいのはないだろうか。もっとも、ある種の現代詩の中では好んで使われるかもしれないけれど(「オオイヌノフグリ かわいい名前」といった、詩の一節が、ありそうである)。
次の写真が、第1位の「ヘクソカズラ」。
実際に「悪臭」を放つそうだが、それにしても、花も実も、見た目には風情がある。しかし、「ヘクソカズラ」では、やはり、詩の中に風情のあるものとしてその名前が登場することはないのではないだろうか。
花の赤い部分がお灸を思わせることから、「ヤイト(お灸の意味)バナ」の別名を持つそうだが、現在ではそれも“ぴんとこない名前”と言えるように思う。
野草の図鑑などを読むと、ほかにも「ひどい」と思われる名前を付けられた草花が少なからずある。逆に、この花にこの名前では「果報者」と言うべきかと思われるものもある。草花の名前は、「あやなし」(筋道が通らない、わけがわからない)の世界を作り上げているとも言えよう。ひどい名前を付けられた植物たちは、何とも気の毒である。
とはいえ、先にも述べたが、現代の詩(短歌、俳句を含めて)は、幅が広い。「ブタナ」「オオイヌノフグリ」「ヘクソカズラ」という三つの名前を入れて詩を書くことも、難しいことではない(実は、簡単に書けそうだと、いま思っている。自分と関連づければよいのだと……)。しかし、それにしても、ひどい名前を付けられた植物たちが気の毒であることに変わりはない。
とりあえず一句。
クソカズラ今日の授業も自虐ネタ
くの
「E 詩」に話をもどそう。
いとうのエッセイ「ひとつで二度美味しい?」と、芝のエッセイ「エロスの詩②」は、ともに読みごたえがあった。いとうのエッセイで紹介されている吉野弘の詩と、芝のエッセイで紹介されている小池昌代の詩は、それぞれ魅力ある詩であると思う。吉野の詩の、最後の四行(ご苦労な/霧よ!/親密に触りつつ物を抱くことが霧の愛し方なので/距離をとって物をみることが不得手なのだ)は、「物事を客観的に眺める目を持っている」(鮎川信夫、引用は、いとうのエッセイによる)、ということはつまり「距離をとって物をみること」になれた吉野の「親密に触りつつ物を抱く」「愛し方」への羨望を、逆説的に表現しているように私には思われるが、どうなのだろうか。小池の詩は、エロスを人間性(あるいは、人間として生きること)の中に適切に位置づけていて、ことばに読む者を共感させる力があると思った。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『シテ』第4号(2014年7月25日発行)
詩は、西方ジョウ「プール」、大江進「もうすこし」、金井ハル「午後のヒゲ」、早藤たかこ「白摘草」、今井富世「蛸」、南悠一「消えては光る日」、阿蘇豊「春の窓」、高瀬靖「蜜柑と毛布」、相蘇清太郎「運動会」を読むことができる。
本号は、今年1月15日に、満87歳で亡くなった吉野弘の追悼特集を組んでいる。
酒田市で出版されている詩誌が、酒田市で生れた吉野の追悼特集を組むのは、特筆すべきこととは言えないかもしれない。だが、「特集」の内容は特筆すべきものだ。
追悼特集として、本誌には、吉野弘の詩について述べた文章が4本載っている。大岡信「吉野弘論」、佐高信「吉野弘讃歌」、相蘇清太郎「吉野弘の格闘」、阿蘇豊「吉野弘作品に関する断片―「つまり」について」。そのうち、大岡と佐高の文章は、既出の文章の再掲載、相蘇と阿蘇の文章は書き下ろしである。
特筆したいのは、大岡の文章と阿蘇の文章が、吉野の詩を批判する立場・視点で書かれていることだ。日本の戦後の詩史を述べるときにはその業績を見ないわけにはいかないと考えられる、同郷の詩人の「追悼特集」において、その詩の魅力を述べる文章だけではなく、その詩を批判する文章を掲載している点に、詩誌としての、『シテ』誌の、「健全さ」と「志の高さ」が現れている、と考える。
吉野の詩の魅力を述べる文章は多い。私も、吉野の詩について述べるのであれば、その詩の魅力を述べたいと思う。一方、吉野の詩を批判する文章は、多くない。特に、「観」(価値観、世界観、人間観、歴史観、詩(人)観)の違いや拠って立つ思想に基づいて吉野の詩を“詩としての魅力を吟味する以前に受け入れない”という立場からの批判ではなく、吉野の詩の読みとりをきちんと行ったうえで批判している文章は少ない。まず、その点で、大岡の文章と阿蘇の文章は、着目に値する。
大岡の「吉野弘論」について、述べたい。
大岡のこの文章は、1957年に、当時酒田市で出版され、吉野も同人の一人となっていた詩誌『谺』39号(1957年7月刊)に初出のものである。『谺』39号は、吉野の最初の詩集である『消息』(1957年5月刊)の出版記念号となっており、大岡の「吉野弘論」は、その巻頭に置かれたものである(『シテ』第4号による)。初出時、吉野は31歳、大岡は26歳であった。
「読んだことがある人は、そう多くはいないだろう」(『シテ』第4号あとがきより)と思われる、この貴重な論は、『シテ』誌の編集を行っている阿蘇豊の強い思いと阿蘇による一度ならぬ大岡への依頼、そして、おそらくは大岡の
好意によって(この論の内容は、現在の大岡の考え方と、かなりの部分が一致していない可能性がある)、再掲がかなったものである。
現在の大岡が、あらためて吉野の詩を論じたならば、かなり、あるいは根本的に、違った内容のものになるかもしれない。
以上のことを承知の上で、私は、これから、あえて、大岡の論への反論を述べようと思う。この論に述べられている、吉野の詩への批判・不満は、
今日、吉野の詩を読んで、評価・共感よりも批判・不満が先に立つ人の、吉野の詩についての思い・捉え方と共通する点があるのではないかと考えるからである。
この論における、大岡の吉野への批判・不満は、「吉野さんは自分を語らない詩人である」ということばに集約される。
「自分を語らない」とは、どいうことか。そのことを、大岡は、吉野の詩を丁寧に読みながら、説明している。説明の中心になっているのは、詩集『消息』の序詩である。次に、全行を引く。
この詩について、大岡は、次のように批判している。長くなるが、批判の内容がわかるように引用する。
・この詩の、たとえば第二連は、鮮やかなイメージを形づくっていて、「彼」の現実感をずい分強めているのだが、その「彼」の現実感の強まりが必ずしも詩の現実感の強まりをもたらしていない所に問題がある。それは恐らく、こういう理由からだ。ぼくらは「青ざめて 陸の方へ走る」男と一緒になって、詩の末尾に向かって走っていく。すると彼は、「何かすることがあるのは…」という気取った自嘲で、「青ざめて」走った自分の姿を覆ってしまうのだ。(略)彼が青ざめて陸の方へ走っていったとき、かれ(ママ)の中に生き生きと動いていたのは、たしかに海のあの深い、孤独な、恐ろしい色じゃなかったのか。読者もその色に心を染められたのではなかったか。かれは「青ざめ」たとき、多忙の中に帰ってもすでにそれ以前の彼とはちがったものにされているような、ある本質的な、根源的な怖れを感じていたはずではなかったか。だから、かれが多忙の中でなおもあんな呟きを口にしたとすれば、かれに「青ざめる」だけの力がなかったか、それともかれを生みだした吉野弘氏の生み方が、少しまちがっていたのじゃないだろうか……
・ぼくらは、造形された人物の表面から内部に導かれるのではなく、逆に内部から表面へ引きずり出され、ついにはこの人物を遠くから眺めるだけの位置にまで押しもどされてしまう。
大岡は、詩「雪の日に」(詩集『消息』所収)についても、その第一連~第三連を引いて、あとのように批判している。
・これ(第二連「それはすでに/欺くことでしかないのに。」、久野補足)は奇妙な二行である。「すでに欺くことでしかない」とわかっているなら、なぜあらためて、「それが突然わかってしまった」というのだろうか。そもそも、「誠実とは欺くことでしかない」という観念は、
突然わかる種類のものだろうか。わかってしまったら、あとはかなしみの雪を重ね重ねするだけで事足りるような観念なのだろうか。もし吉野さんが「そうだ」と言うなら、ぼくはそれを嘘だと思う。誠実でありたいと不断に願う精神は、「すでに……でしかない」というような限定的、排他的な語法とは最初に縁を切ってしまっているはずではなかろうか。だから、ぼくとしては、吉野さんがここで、誠実に関する観念にとりつかれ、必要以上に感傷的になっているか、またはレトリックのわなにかかっているのだと推測せざるえない。もともと、誠実という倫理的態度は、それをおのれに課する人に自己撞着を強いるものではなかったろうか。言いかえれば、そこでは欺かれ、欺くことは、規定の条件ともいうべきではなかったろうか。だから、ここでも、吉野さんは必要以上に感傷的になっているか、またはレトリックのわなにかかっているのだと推測せざるをえないのである。こうしたことは、吉野さんが、わが意に反して自分を許してしまうことがあると、自分自身の追求を中途で放棄してしまうことがあると、ぼくらに推測させる理由になる。
こうして、大岡は、吉野の詩について、次のような問題を指摘する。
・たしかに、吉野さんにあっては、自我の遠心力と求心力とが、互いにせめぎ合いながら、究極において妥協するという図式が、かなり明瞭にみてとられるのだ。
・吉野さんの自己追求が、砂に吸われる水流のように、その過程においてしばしば抒情的な詠嘆のうちに飽和し、立ち消えにさえなってしまう(略)。
・吉野さんの自己追求は、サラリーマンとしての一般的な自己規定との相対関係において働き、その枠を踏みはずすことはないように思えるのだ。これは、生活を構成する具体的事実からのみ詩を獲得しようとする吉野さんの人間的誠実さを示すものにほかならないが、同時に吉野さんの自己追求を、「青ざめて」孤立した自己の実存的追求とまでは深めさせない原因ともなっているとぼくには思えるのだ。
大岡が「吉野さんは自分を語らない詩人である」と述べているのは、吉野がその詩において「自己追求」や「真実追求」(このことばも、大岡が、論の中で、吉野の詩においてはそれが不十分であるという文脈の中で用いている)を徹底しておらず、中途半端な状態のまま終えているという意味である、と捉えることができる。
先にも述べたが、大岡の、このような、吉野の詩への批判・不満は、今日、吉野の詩を読んで不満を感じる人に、多く、共通するものなのではないだろうか。
それでは、「自己追求」は、詩を書く上で、それほど重要なことなのだろうか。
大岡は、「自己追求」が、詩を書く上で
一般的に重要で不可欠なことであるとは述べていない。また、詩を「自己追求」の道具とすることをよしとするような考え方を示してもいない。
大岡は、次のように述べる。
・自分を語る、ということにそれほど意味があるのか、と問われるなら、こう答えよう。「自分および自分の周囲を執拗に、しかも可能な限り正確に、観察し、それによって自分の位置を、といより自分の重心を、ひとつの現実的構図の中で確保していこうと努める人が、自分を語っていないとすれば、それは奇妙なことではないか。いや、それ以上に、何か大きな問題がひそんでいることを暗示していないか」と。
すなわち、吉野が「自分および自分の周囲を執拗に、しかも可能な限り正確に、観察し、それによって自分の位置を、といより自分の重心を、ひとつの現実的構図の中で確保していこうと努める人」であることを前提とし、そういう吉野にあって「自己追求」が十分に行われないことには、吉野の詩を評価する上で指摘しないわけにはいかない大きな問題があるというわけである。
しかし、吉野の詩を評価する上で、「自己追求」の度合い、その徹底ぶりというのは、それほど重要なことだろうか。
吉野弘という実際の人物がそのふだんの生活において「自分および自分の周囲を執拗に、しかも可能な限り正確に、観察し、それによって自分の位置を、といより自分の重心を、ひとつの現実的構図の中で確保していこうと努める人」であったかどうか、私は知らない。しかし、詩を書く際に、吉野がそのように「努め」ていたとは、書いた詩からは考えづらい。むしろ、「自己」にこだわらずに、自分を含めた人間のあり方や社会のあり方、人間以外のもののあり方やそれを含む世界のあり方といったところに、広く目を向け、認識の対象とし、詩の素材としていったことが、吉野の詩を豊かな、実りあるものにしているのではないだろうか。
『詩の楽しみ ―作詩教室』(岩波ジュニア新書、1982年)の中で、吉野は、詩の定義を「言葉で、あたらしくとらえられた、対象(意識と事物)の一面である」と述べている(p2)。このように述べられたのが、大岡の論のはるか後年のことであることを考えると、“後出しじゃんけん”のうしろめたさを覚えるが、この定義において吉野が「対象」を「自己」に限っていないことは明らかである。吉野が詩作において重要視したのは、「自己追求」ではなく、“言葉で、対象を、あたらしくとらえなおす”ことであり、その際の「対象」は、広く「意識と事物」であったと考えられる。
吉野が詩を書く上でのキーワードとしていたのは、、「自己追求」や「真実追求」ではなく、「認識」と「感動」であった。そのことは、1959年初出の「詩とプロパガンダ」(思潮社『現代詩文庫 12 吉野弘詩集』所収)中で、次のように述べられていることからわかる。
・僕は詩を認識だと思うんだ。詩に限らず、芸術は、事物を人間の意識の中にもたらすための一種の言語だと思うわけだ。感動というのは、謂わばそれの端緒だ。感動の未発展の曇った状態から確実と明晰との段階に高めるための作業が即ち認識だ。」(前掲書、p91)
・(「作業」をどのように進めるかというと、久野補足)漠然としか言えないけれども、簡単に言うと、感動に即して、とでもいうのかな。(同前)
・感動から遊離しないで、ということで、消極的な言いかたのようだが、このことが仲々(ママ)困難なのだ。感動そのものに忠実につき従ってそれを発展させるには集中力と持続力が必要なんだ。(同前)
・一体に芸術は直感ということを重視するのだけれど、芸術が感動の意味を直感的に把握するというのは作業のはじまりなのであって、その把握を拠りどころにし、それから
外れないで、感動の未知の領域をしんぼう強く発展せしめ完結せしめる作業があるわけだ。(同前)
・僕が、芸術の領域で、ひとつの思想、態度に期待するのは、その思想、態度が、どれだけわれわれの認識を拡張してくれるか、どれだけ認識に新しいものをもたらしてくれるかということであって、思想そのものの解説ではないんだ。(前掲書、p92)
引用が多くなったが、吉野が「認識」と「感動」をキーワードとして詩を考えていたこと、「感動」から離れずに新しい「認識」を示すことを詩作の方法の根本に据えていたことがうかがわれる。
詩作とは、吉野にとって、「直感的に把握」された「感動の意味」を「拠りどころにし」て、「それから
外れないで、感動の未知の領域をしんぼう強く発展せしめ完結せしめる作業」であった。
「感動の未知の領域をしんぼう強く発展せしめ完結せしめる」過程においては、「直感的に把握」された「感動の意味」を「拠りどころにし」ていること(=「感動に即して」いること)を条件として、詩において表現される“現実”は、いわば“自在に構成されることがゆるされた”と考えられる。詩「I was born」における「やっぱり I was born なんだね」の気づき(=「認識」)は、事実としては、「少年」の時に得られたものではなかったかもしれない。詩「夕焼け」における「やさしい心の持ち主は/いつでもどこでも/われにもあらず受難者となる。」の「認識」も、事実としては、「電車」の中で得られたものではなかったかもしれない。そうであったとしても、そのことをもって、吉野の詩の「現実感」が揺らぐことはない。吉野の詩の「現実感」は、示される「認識」の確かさと、その「認識」に伴う「感動」に依拠しているのだから。
『消息』序詩の詩としての価値は、“狂気(一歩間違えば海に身を投げ入れそうになる)と日常(「多忙は神様だ」と自分に納得させて日々を過ごす)の間をつねに往還するような危機的な状況にある人のあり方”を、“現代の社会において労働者として生きる者のあり方”として、“新たに見出してことばで表現することができどた”ことにあるのであって、詩に表現されている「彼」の姿の現実感は、実際の人間の行動や心理に照らして検証したときどれほど現実的であるかということではなく、「何もすることがないとき」には「突堤の先に立って」「海」をのぞき込んでみたいという気持ちにもなるという「意識」のあり方の現実感、「海」をのぞき込めば怖れを感じ「身震いして」逃げ出したい気持ちにもなるという「意識」のあり方の現実感、「多忙は神様だ」ということばに逃げ込まなければ虚無の思いにとらわれてしまうこともあるという「意識」のあり方の現実感、すなわち、この詩において見出され表現されている「意識」のあり方が、詩(=「認識」を表現したことば)を受けとめる私たちにとってどれほど実感をもつものか、切実であるか、によって計られ、支えられている。
この詩は、“現代の社会において労働者として生きる”私たちの姿について、確かに「われわれの認識を拡張してくれ」ている。
「雪の日に」の詩についても、同様のことが言える。「雪の日に」の詩は、「誠実でありたい」という、自覚的、無自覚的に、誰もがもっていると言ってもそれほどの言い過ぎにはならないであろう思いについて、私たちの「認識に新しいものをもたらしてくれ」ている。それも、「感動」を伴って。
大岡は、「『誠実とは欺くことでしかない』という観念」と述べているが、吉野が表現しているのは、「観念」ではなく「実感」である。「観念」として捉えるならば、なるほど、大岡が言うように、「『すでに欺くことでしかない』」とわかっているなら、なぜあらためて、『それが突然わかってしまった』というのだろうか。そもそも、『誠実とは欺くことでしかない』という観念は、
突然わかる種類のものだろうか」という批判も有効性をもつかもしれない。しかし、吉野が表現しているのは「実感」であり、「実感」である以上、それは“あるとき、突然、はきりと意識される”性質をもっている。加えて言うならば、「もともと、誠実という倫理的態度は、それをおのれに課する人に自己撞着を強いるものではなかったろうか。言いかえれば、そこでは欺かれ、欺くことは、規定の条件ともいうべきではなかったろうか。」と大岡は述べているが、「雪の日に」の詩を読む以前に、はたして、大岡にそういう自覚があっただろうか。「誠実」について、そういう「認識」で振り返ることが(まして、切実な「実感」として振り返ることが)あっただろうか。「コロンブスの卵」ということばが、思い浮かぶ。
次に、阿蘇豊「吉野弘作品に関する断片―『つまり』について」について、述べたい。
阿蘇は、吉野の詩について、次のように述べる。
・どうも吉野弘は、そばで冷たく笑っているに過ぎないのではないか。……分析的で、論理的で、感情がわしづかみにしたものを、まだ少し熱いままでは提示しない。……彼が分解、分析して見せるから、読むほうの思いはその先に行かない。……その論理のもって行き方にうなづくけれど、それは同意であり、熱い共感にはなりにくい。
阿蘇の、こうした「思い」は、「ぼくらは、造形された人物の表面から内部に導かれるのではなく、逆に内部から表面へ引きずり出され、ついにはこの人物を遠くから眺めるだけの位置にまで押しもどされてしまう」と述べた、大岡の吉野批判と、その原因を同じくしていると考えてよいのではないのだろうか。
私自身は、吉野の詩を読んで、「そばで冷たく笑っているのではないか」と感じたことはない。「熱い共感」とまでは言えないにしても、「さめた同意」ではなく、「共感」をもって「認識」を新たにしたり、強くしたりすることが多い。
一方、「分析的で、論理的で、感情がわしづかみにしたものを、まだ少し熱いままでは提示しない。……彼が分解、分析して見せるから、読むほうの思いはその先に行かない。」というのは、私にあってもその通りである、言ってよいように思う。それは、先に述べた、「どれだけ認識に新しいものをもたらしてくれるか」に詩の意義をみて、「直感的に把握された」「感動の意味」を「拠りどころ」とし、「感動に即して」、「感動の未知の領域をしんぼう強く発展せしめ完結せしめる作業」を詩作の過程とした、吉野における詩作のねらいと方法が、その結果として必然的に伴うものと考えられる。詩作の過程において、「感動」は客観視され、分析され、ものごとについての新しい「認識」として、「言葉で、あたらしくとらえられた、対象(意識と事物)の一面」として、示される。
「詩とプロパガンダ」を読むと、吉野は「経験」ということばも詩作上のキーワードとしている。
・この作業(「感動の未知の領域をしんぼう強く発展せしめ完結せしめる作業」、久野補足)の遂行を妨げる要素を注意深く排除してゆかないと、感動というかたちで与えられた新しい経験の意味が明らかにならないでしまうわけだ。(前掲書p91)
・或るひとつの思想が、従来見落としていたものを、新しい次元で掬いあげるということが素晴らしいわけだ。そしてその作業が、どこまでも詩人自身の経験に即して展開される限りに於いてだね。(前掲書p92)
上記の引用部分で、吉野が、「作業」(詩作もその中に含まれると考えられる)は「どこまでも詩人自身の経験に即して展開される」べきだと述べているのは、実は、「コミュニズム的立場の詩」や「愛国詩」におけるように「プロパガンダ」が「経験に即した認識の発展を阻害する」こと、があってはらない、「芸術は本来、経験に即した認識作用であるのに、途中でその作業を宣伝用に変えたりしては、いけない」ということを述べる文脈においてである。とはいえ、吉野が「経験」を重視することには、それを離れて「認識」を述べようとすれば、詩が「感動」を伴わない、観念的な性質のものになってしまうということを念頭においていたと考えてよいのではないだろうか。
吉野の詩を読んで、読み手が「感動」を感じるかどうかは、吉野のことばを、読み手が自分の経験に照らして、「観念」としてではなく、「実感」として受け入れるかどうかによる、と考えるのだが、どうだろうか。
さて、阿蘇は、吉野が「作者の論理を貫」き、「読み手は彼の論理の中にあって、自由な読み方ができにくくなっている」ことの一つの現れとして、吉野の詩における「つまり」ということばの使用に着目している。この着眼は、吉野の詩における特徴的なことばの使い方への着眼として卓抜なものであると思う。
阿蘇が着目しているのは、次の詩に見られるような「つまり」の使用である。
阿蘇は、この作品の最終連の「つまり」について、「なぜ、ここに『つまり』を入れたのか。そのまま『身体ごととりこになる。』でいいのではないかだろうか。」と疑問を投げかけている。他の作品での「つまり」の使用例を探し、「乳房に関する一章」「幻・方法」「かたつむり」「ひとに」で見られたことを述べ、「これらの作品にみられる『つまり』は、単にことばをわかりやすく言い換えるというより、やはり論理を強め、帰結を説明するものになっていると感じた」と述べている。
私は、この詩における「つまり」の使い方を、おもしろいと思う。そして、「つまり」を取り除いたらこの詩は詩として成り立たない、と言ってもよいのではないかと思う。作品全体のおもしろさが、この「つまり」に依拠していると考える。
「つまり」を、他のことばに置き換えるならば、「結局」や「結果的に」ということばへの置き換えが可能だろう。可能であるというよりも、論理をたどる表現としては、そうしたことばを使うほうが、自然な表現となる。すなわち、論理的につなぐことばとしては、ここでの「つまり」は、収まりが悪い。阿蘇が「違和感」を覚えたのは、当然なのである。
第二連「人がその心を/さがしにゆく。」。何のために? 「とりこ」になった「心」を探し出して取り戻すために、ということになるだろう、第一連とのかかわりから考えた場合、論理的には、そういう意味になる。
第一連の「人の心をとりこにする」が、実は、非常に巧みな表現なのだ。一般的に「心をとりこにする」とは、“対象にすっかり魅了される”という意味の比喩表現として使われる。この詩においても、第一連を単独で読めば、“遠くから山を見ているとどうしようもなく山に行きたくなる“という意味に読める。というより、そういう意味にしか読めない。ところが、第二連を読むと、「心をとりこにする」に文字通りの意味が生じる。
第二連では、一転して、“(とりこになった心を)取り戻すために探しにゆく”という、“文字通りの意味”のほうが前面に出る。そして、“山に行くことで、山に行きたいと思う心を解消する”という意味が、背面に隠れてひそかに重なり、ことばのリアリティを支えている。
第三連。第一連、第二連から続く文脈においては、第二連と第三連のつながりにおいて、“心を取り戻しにゆくのに、それどころか、身体まで取られてしまう”という、逆接的なつながりのニュアンスが生じる。「身体ごととりこになる。」の前に、何のつなぎことばも置かないということになると、第二連と第三連の間が、読み手の中でうまくつながらず、第三連が切り離された感じになり、結果的に、第一連、第二連、第三連のつながりによって生じるこの詩のおもしろさは感じられなくなってしまう。「結局」や「結果的に」、あるいは「そして」といったことばを置けば、つながりがはっきりしてわかりやすいが、理屈っぽい印象になる。その点、「つまり」で強引につなぐと、その強引さが、“当然の帰結として、身体まで取られてしまう”というニュアンスを醸し出し、“心を取り戻しにゆくのに、それどころか、結局、当然の帰結として、身体まで取られてしまう”という諧謔のニュアンスを強めることになる。論理的な客観性(冷たさ)を“装って”。
うまく言い切れていない印象を私自身感じているのだが、この詩における「つまり」の使い方は、「論理を進め、帰結を説明するもの」として使われているのではなくて、「感動」に即して詩の世界を構成し、表現したい「認識」をうまく表現する役割を担って使われたと捉えるのが適切なのではないだろうか。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)