
詩集を読んで〈2014〉
新・日本現代詩文庫115『近江正人詩集』(土曜美術社出版販売、2014年1月7日発行)
土曜美術出版販売の「新・日本現代詩文庫」の一冊として、『近江正人詩集』が出版された。
近江が2014年2月現在までに出版した詩集の内、小野孝一の写真とのコラボレーションによる詩集『希望への祈り もがみ風景と抒情』(2013年4月、当HPに感想を掲載)を除く6冊の詩集(『日々の扉』、『羽化について』、『北の鏃』、『樹の歩み』、『地上の銀河』、『ある日 ぼくの魂が』)からそれぞれ作品を選び、これまでの詩集には未収録の作品9篇と合わせて、計100篇の詩を収めている。エッセイは、「光の
近江のこれまでの詩を俯瞰的に読むのに適していることは、言うまでもない。
近江の詩については、これまで当HPでしばしば紹介し、感想を述べている。穏やかで誠実な語り口によって表現される豊かなイマジネーション、希望へと向かう方向性を伴って行われる思索、宇宙的な視点を伴って生命の在り方を追究するまなざし等、近江の詩の魅力を、本詩集を読んであらためて確認することができた。
高橋は、解説「近江正人の詩」の中で、近江自身が自らの詩を「希望であり、生命であり、コスモスであり、自然を含む命あるものへの讃歌」と意識していることが窺われると述べ、万里小路は、解説「花のなかに宇宙がある」の中で、近江は「己れがなぜここにこのような
もちろん、近江の詩の性質は決して一様ではなく、特に魅力的と思われる作品についても、その魅力にはそれぞれ特色があり、10人が好きな作品を一篇ずつあげてもまったく重ならないという可能性も少なからずあると言えるだろう。
例えば、山形県内でも北に位置して雪の多い最上地方の風土性が強く出た作品をあげる者もあるだろう(「音信」、「北の矢じり」、「雪おぼれ」など)。
希望へと向かう姿勢が強く表れた作品を選ぶ者もあるだろう(「
作者の心の深い部分に、重い何かを残したと思われる、家族や親族の姿を描いた作品を選ぶ者もあるだろう(「赤い手ぶくろ」、「おにやんま」、「みみず讃歌」、「どじょう」など)。
宇宙的な視点で(あるいは、その視点を背後に置いて)生命の在り方を見つめた詩を選ぶ者もあるだろう(「あさがお」、「生命の時間」、「二六〇〇万年の鼓動」、「コスモス」など)。
「樹木」や「花」の在り方それ自体に目を向けた詩を選ぶ者もあるだろう(「樹の歩み」、「コスモス讃歌」など)。
散見される官能性の強い作品を選ぶ者もあるだろう(「真夜中の秘儀」、「遠雷」など)。
時代や、文化、文明の在り方への批判が強く表れた作品を選ぶ者もあるだろう(「秋の老婆」、「死に魚」、「おにぎり」など)。
青春期に持ちがちな、挫折感や焦燥感、寂寥感、虚無感、空漠感、人生を生きていく上での思い等を強く感じさせる作品を選ぶ者もあるだろう(「光る五月」、「霧になりたい」、「八月の空」、「あじさい」、「井戸」、「日々の扉」など)。
私が、いま、自分がいちばん好きな詩を一つだけあげなさいと言われたら、「日々の扉」をあげる。この詩の、内容はもちろんだが、その内容を伝える、イメージと表現、それに語り口(調べ)は、私にとって、格別なものである。ただ、この詩は、すでに、当HPで紹介済みである。そこで、もう一つあげるとしたら、近江にとってはもしかしたら不本意かもしれないが、私は、「あじさい」をあげたい。この詩は、「日々の扉」と(どちらが先に作られたものかはわからないが)、イメージやことばの使い方はまったく異なっているものの、しかし、通底するものがある、と思う。
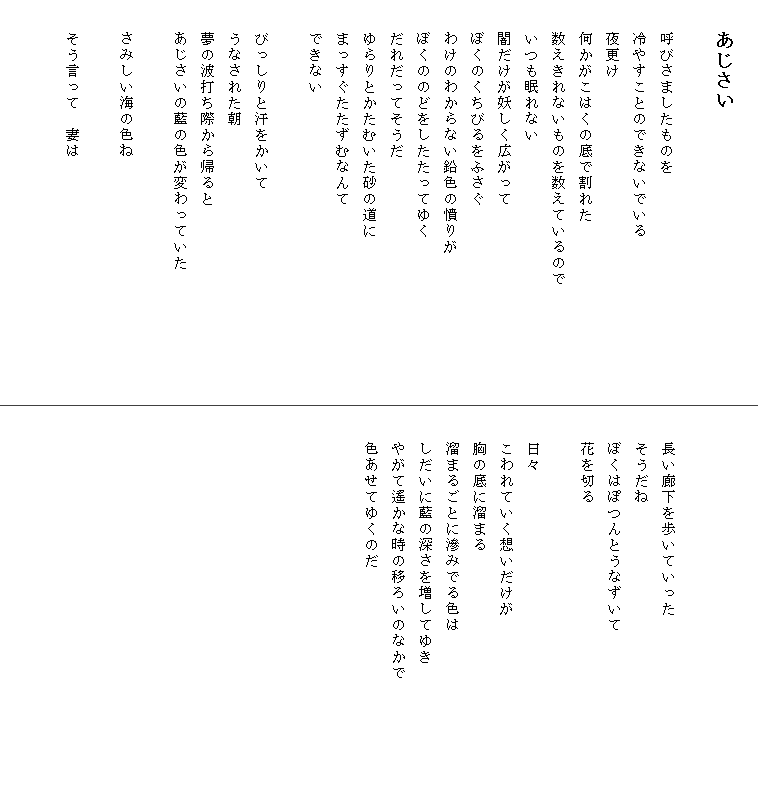
第一連。「呼びさましたものを/冷ますことができない」という興奮した思い、「数えきれないものないを数えている」という解決不可能な思い、「わけのわからない鉛色の憤りが/ぼくののどをしたたってゆく」というやり場のない思い、「ゆらりとかたむいた砂の道に/まっすぐたたずむなんて/できない」という不条理な思い。そういう思いにとらわれる経験を一度もしないで人生を過ごせる人が、はたしているものだろうか。表現が抽象的であることによって、個人的な体験の説明ではなく、広く、普遍的な経験の表現になっている、と評価したい。しかも、抽象的でありながら、読み手に想起させる思いには、実体感が伴う。
第二連。「夢の波打ち際から帰ると/あじさいの藍の色が変わっていた」を読んで、私は、藤原定家の「春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空」(『新古今和歌集』)の和歌を思い起こした。「夢の波打ち際から帰る」は、「波打ち際」すなわち海の出てくる夢を見たともとれるが、それでは、第三連の「妻」のことばが“できすぎた偶然”になってしまう。“どっぷりとつかっていた悪夢から、海から上がるように覚めた”ことの表現ととりたい。
第三連と第四連。「妻」のことばと「ぼく」のしぐさが、何ともせつない。
第五連。表現の性質について、第一連と同様のことが言える。また、最終4行は、「藍」の色を使うことによって、「あじさい」との関連をもたせる一方、「こわれていく想い」に、それにふさわしい色をもたせて、本来イメージ化することの難しい「想い」をイメージ化することに成功している。
全体の構成が、起(第一連)、承(第二連)、転(第三、四連)、結(第五連)となっており、整っていることにも目を向けておきたい。
悲観する必要はないけれども、しかし、受け入れて生きていくしかない人生のせつない在り方が表現されていて、味わい深い詩であると思う。
(以上、敬称を省略させていただきました。)
奥山美代子詩集『曼陀羅の月』(書肆犀、2013年5月30日発行)
奥山美代子の詩集が出版されたことを知り、書店で購入した。昨年、「山形新聞」紙上の「味読 郷土の本」で紹介されてまもなくのことである。「やましん詩壇」で奥山の詩を読み、その詩に魅力を感じていたからだ。
詩集を読んで、私は戸惑いを覚えた。収められている詩が、「やましん詩壇」で読み魅力を感じていた詩とは違う印象を与えるものだったからだ。暗い、重い、という印象を受けた。私が期待していたのは、魅力的な比喩表現が巧みに、無理なく、使われて、読後にさわやかな印象を残す、そういう詩である。そもそも、「曼陀羅の月」という詩集のタイトルが、私がもっていた奥山の詩の印象にはそぐわないものであり、どうしてこういうタイトルなのか不思議に思っていたのだが、収められている詩は、たしかにそのタイトルにふさわしいものが多かった。
「あとがき」を読んで、なぜタイトルが「曼陀羅の月」なのか、なぜ収められた詩の印象が暗く重いのか、私なりに理解した。「東日本大震災後の原発事故で苦し」み、「見えない放射能に翻弄され続け」ている、「私の故郷・福島」への思い、そして、広く東日本大震災の被災者への思い、加えて、「五年前になりますが、甲状腺癌の手術をうけました。それからずっと喉を切開したままの状態なので、いまだに言葉が出ません」という自身の体験にかかわる“人間への思い”、そうした思いがタイトルにこめられているのだろうと思った。また、そうした思いが、詩集に収める詩の選択と配列にもつながっているのだろうと思った。
そうした思いのこもった詩集としてこの詩集を読むとき、言い換えるならば、そうした作者の思いを受けとめようという気持ちでこの詩集を読むとき、この詩集に収められた詩で共感を覚えない詩はないと言ってよい。少なくとも、私の場合は、そのように言える。
一方、一読者としての私の好みは、それとしてある。また、作品の評価においては、「あとがき」を読まなければ、あるいは「あとがき」に書かれなければ、知り得ない作者の事情や体験を反映させるべきではない、という考え方も適切なものだろう。
いま、私の好みに基づいて、そして、作者の事情や体験とは切り離して、詩集中で最も魅力的な一篇をあげるならば、私は、次の詩をあげる。
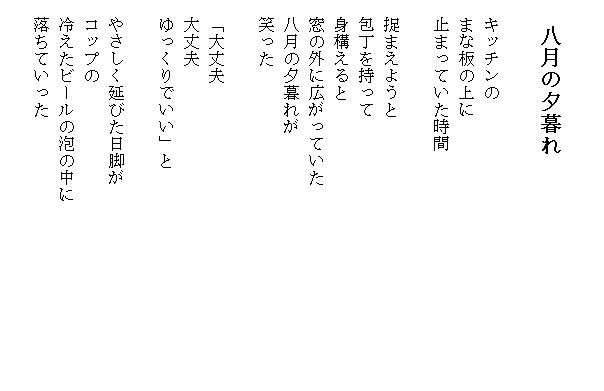
「キッチンの/まな板の上に/止まっていた時間」とは、日々の生活をすごすうえで必要な時間、ある目的のために行動しなければ先に進まない時間であり、この場合は“夕食までの時間”と捉えてよいのではないだろうか。
夕食の支度を早くすませようと、話主(作品中の“私”)は、「包丁を持って/身構える」。すると、「八月の夕暮れ」という、日々の生活をより大きく包み込んでいる時間が、「大丈夫/大丈夫/ゆっくりでいい」と「笑っ」て語りかける。“私”の意識は、常に目的にせかされているような日常の時間から解放されて、安心を取り戻す。“生活の時間”から“生きる時間”に、意識が移ったと言ってもよいだろう。
最終連は、そのような意識によって見出された、魅力的な情景である。ぐぐっと一杯飲んで、ほおっと一息つきたくなるようではないか。「生き返るね」とは、そのような時によく使われることばであるが、単に“からだにしみ入るような感じ”を表現しているだけではなくて、多くの場合、“生活の時間”から“生きる時間“への移行をも表現していることばになっているのではないかと思う。
(以上、敬称を省略させていただきました。)
比暮 寥詩集『憂感悲唱集』(文芸社、2014年3月15日発行)
本詩集は、
「読者側の視点に立って」選んだことによって、これまでの比暮の詩集に比べると、一般的な読者にとって読みやすいものになっていることは、確かである。これまでは「悲唱」に包み込まれてわかりづらかった、比暮の詩の“詩としての特色”が伝わるようになったと言うこともできる、と私は思う。
自身が書く詩についての比暮の願いが、「詩として高く評価される」といったところにあるのでないことは承知している。「戦後六十有余年を経ながら」「未だに胸奥深く谺してまいる」、「死者たちからの呼び声」や「異境に埋もれたままにある骨たちの語りかけ」、「風浪に目覚めて怒り叫び続けている髑髏たちの、無念の呻き」を表現し、日本が再び戦争へと続く道を進み始めることがないようにすること、それこそが比暮の願うことだろう(引用は、いずれも「あとがき」による)。そのことを承知のうえで、私は、ここで、あえて、比暮の詩の「詩としての特色」について述べたいと思う。他の人と共有しておきたい「詩としての特色」を、この詩集を読んで見出したと思うからである。
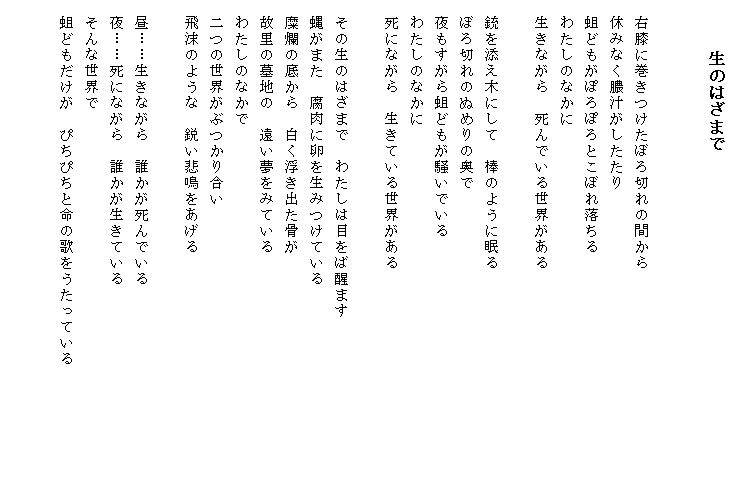
最初の詩集『骨かげろう』に収められた一篇。
第一連で、「わたしのなか」で「生きながら 死んでいる世界」が表現され、第二連では、「わたしのなか」で「死にながら 生きている世界」が表現されている。前者は、具体的で、肉体的な「世界」であり、方向性としては、死に向かうそれとして、後者は、抽象的で、精神的な「世界」であり、方向性としては生を保とうとするそれとして、それぞれ表現されていると捉えることができるだろう。もとより、二つの「世界」が別々な世界としてあるはずはなく、肉体と精神を切り離すことはできないという点で二つの「世界」は一つであり、また、一個の「生」が生と死の「はざま」にある状態の表現として一つ(どちらか一方だけで十分ということなく、一対の表現となっていなければならないもの)である。
さて、それでは、第一連の終わり2行の表現(「わたしのなかに/生きながら 死んでいる世界がある」)と、第二連の終わり2行の表現(「わたしのなかに/死にながら 生きている世界がある」)は、交換可能なのか、と考えると、どうだろうか。
それほど気楽な―レトリックとして表現を一対に組み立てただけというような―ものではあるまい。「わたしのなかに/生きながら 死んでいる世界がある」と自覚されるのは、すなわち(自分の一部が)「死んでいる」という事実から逃れがたいのは“肉体”なのであり、一方、「わたしのなかに/死にながら 生きている世界がある」と自覚されるのは、すなわち、「生きている」という事実と向かい合わなければならないのは“精神”なのだ、と私は思う。
こうして、第一連の終わり2行の表現と第二連の終わり2行の表現は、みごとに対称的で、また対照的な、表現として構成されながら、内容において、交換不可能な切実さをもっている。
第三連。2~4行目の表現は、具体的で、強烈なイメージを伴い、強い印象を与える。「骨が…夢をみている」の、「骨」を主語とした表現も、肉体が、精神のありよう・意識の持ち方によらず、確実に死に向かっていることの表現として、気楽に使われた擬人法表現とは一線を画している。終わり3行の表現における、「二つの世界がぶつかり合い」あがる「鋭い悲鳴」とは、肉体的な痛みによる悲鳴とは別の、生と死の「はざま」にある精神の発する「悲鳴」と思われ、この詩において表現されている精神のありようの頂点をなす表現と言えよう。
最終連。視点は、「わたし」の外にも広がる。1行目と2行目が、ここでも、対称的で、対照的な表現をつくっているが、「生きながら、誰かが死んでいる」は、“生き生きと動く”ことが求められる「昼」のものとして、「死にながら、誰かが生きている」は、“死んだように眠る”ことのゆるされる「夜」のものとして、やはり、交換不可能な切実さを有している、と言えよう。
全体が、「起承転結」の整った構成となっていることにも、注意しておきたい。
吉野弘は、詩の「内容」について、次のように述べている。
詩の面白さは、そこに何が書いてあるかということだけでなく、何が、どのような言葉で表現されているかによって、
大きく左右されると私は思っています。詩の内容は、「何が」「どのように」書かれているかの二つであって、とりわけ、
表現の鮮度、その新しさが詩の生命と言えます。(吉野弘『詩の楽しみ 作詩教室』岩波ジュニア新書、1982、p18)
着目したいのは、「何が」だけでなく、「どのように」も、詩の「内容」と吉野が捉えている点である。「何が」を“内容”とし、「どのように」は“表現”として、区別して捉えるのが、通常の捉え方だろう。それに対して、吉野は、詩の場合には、「何が」と「どのように」が不可分なものとしてともにその詩の「内容」となるのだ、と述べているわけである。
ある詩について、その「内容」を考える場合には、「何が」書かれているかに着目するだけでは不十分なのであって、「どのように」書かれているかにも着目しなければならない、そして、その二つのどちらにも「新しさ」のあることが、その詩の詩としての価値を判断するうえで重要となる。吉野はそのように考えていた、と思われる。
比暮は、自分が書く詩に「面白さ」を求める人ではない。比暮の詩について述べるのに、吉野の考え方を引用する必要があるのかと疑問に思う人もいるだろう。私がここで吉野の考え方を引いたのは、先に示した吉野の考え方が、詩についての考え方として広く一般性をもつものであり、比暮自身の詩についての考え方から離れて、そうした一般性をもつ考え方に基づいて判断した場合にも、比暮の詩の中には、高い評価に値するものがあることを述べたいからである。
「わたしのなかに/生きながら 死んでいる世界がある」という捉え方=表現、「わたしのなかに/死にながら 生きている世界がある」という捉え方=表現、「わたしのなかで/二つの世界がぶつかり合い/飛沫のような 鋭い悲鳴をあげる」という捉え方=表現。その三つの捉え方=表現を主軸として、詩「生のはざまで」には、“この詩ならではの「何が」「どのように」”がある、と私は考える。吉野の言う「新しさ」とは、“前衛的な新しさ”に限ったものではなく、“その詩ならではのもの(その詩によって新しく見出され表現されたもの)がある”ということだろうと、私は理解する。
比暮の詩が、総じて、「何が」において後世に残すべき価値をもつものであることに異論はない。加えて、私は、「『何が』『どのように』書かれているかの二つ」という視点で考えた場合にも、比暮の詩には高い価値を認めることのできるものがあることを述べておきたい。
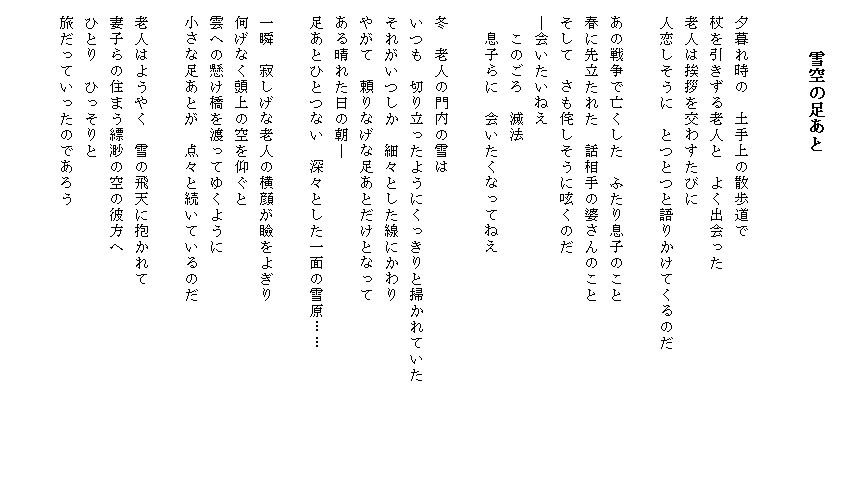
三冊目の詩集『日本憂歌』に収められた一篇。
比暮は、自分が生きることについては、「どれほどの人たちの/どれほどの人生を食らい続けて/こうものうのうと 生き長らえてこれたのであろう」(詩「人生を食らう」より)と「ざんげ」の気持ちを抜きに振り返ることのできない人と思われるが、他人の人生を見つめるまなざしには、非常なやさしさがこもる。この詩についても、他人の人生をいとおしむ気持ちが強く感じられる。
特に着目したいのは、第三連。他人の「門内の雪」を、このようなまなざしを持って見つめ、表現した詩がほかにあるだろうか。
この詩にも、“この詩ならではの「何が」「どのように」”がある、と思う。
詩集の最後に、「香華悲唱」としてまとめられた十一篇の詩は、いずれも亡き「妻」への思いをつづったものである。愛情の真直さが、心に残る。
詩「歌かたみ」の中に、「妻」が詠んだ、二つの俳句と二つの短歌が置かれている。「妻が亡くなった年の 晩秋のある朝―/箪笥の開き戸から 妻の日記を取り出そうとした時/はらりと 落ちてきた」「紫紺の千代紙に包まれた/懐かしい筆あとの 四枚の短冊」(詩「歌かたみ」より)に書かれていたものである。
四つの俳句・短歌は、いずれも、しみじみと、せつせつと、思いが伝わってくるものだ。とりわけ、「虫しぐれ…」の一句は、「虫しぐれ」に耳を傾ける気持ちのうちに、ひとり「夫」の帰りを待っていた女性の愛情がこもり、一つの俳句作品としてもすばらしいものと思う。
一方、詩「歌かたみ」の最後には、比暮の詠んだ短歌一首が置かれている。「妻」の残した俳句・短歌に対する返歌として読むことがきる。
次に、「妻」の詠んだ俳句・短歌と、比暮の短歌を引いて、比暮の詩の読み方としては異例なものを示したと言えるかもしれない、この文章の終わりとしたい。
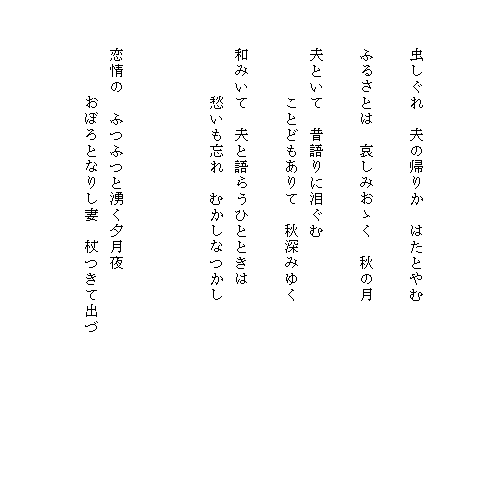
(以上、敬称を省略させていただきました。また、「―」(ダッシュ)は、すべて、本来2文字分の大きさです。)
Copyright©2013 Masayuki Kuno All Rights Reserved.