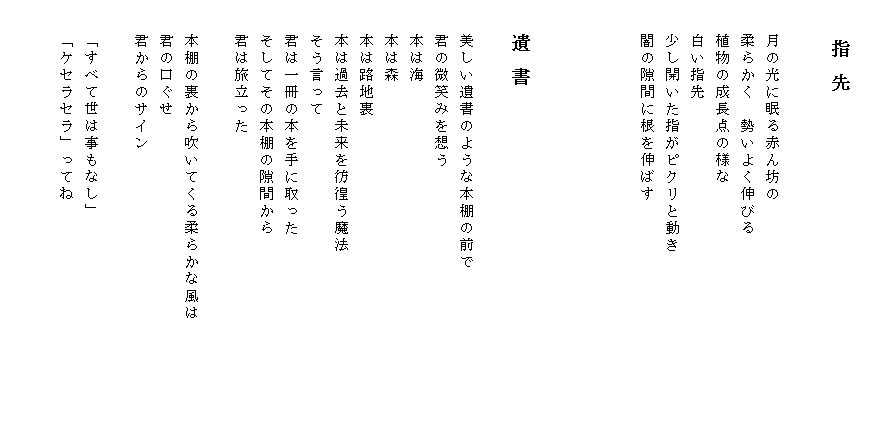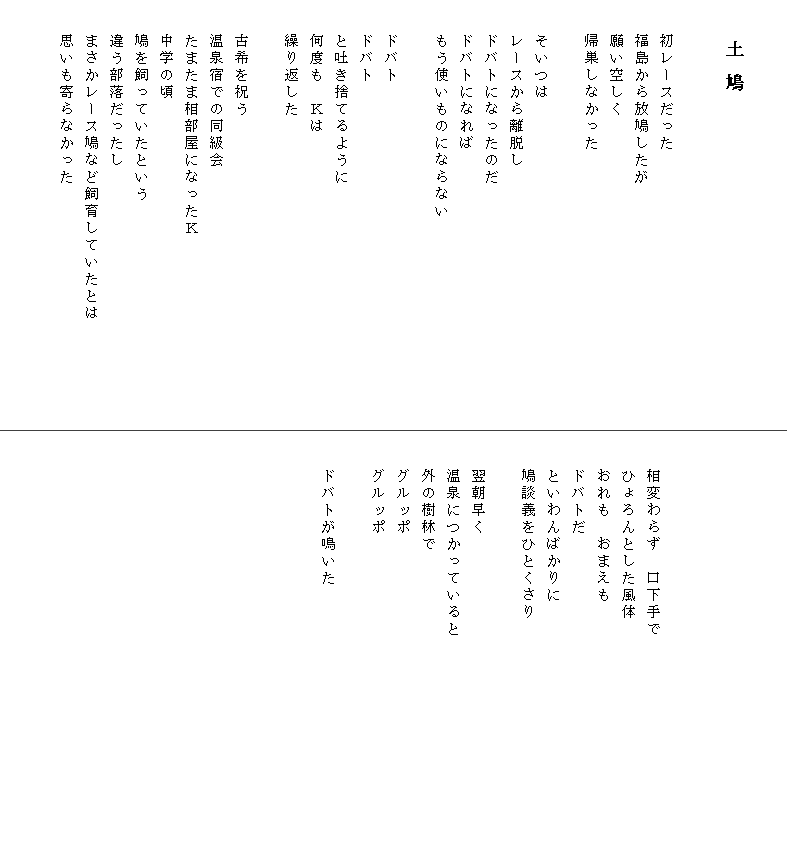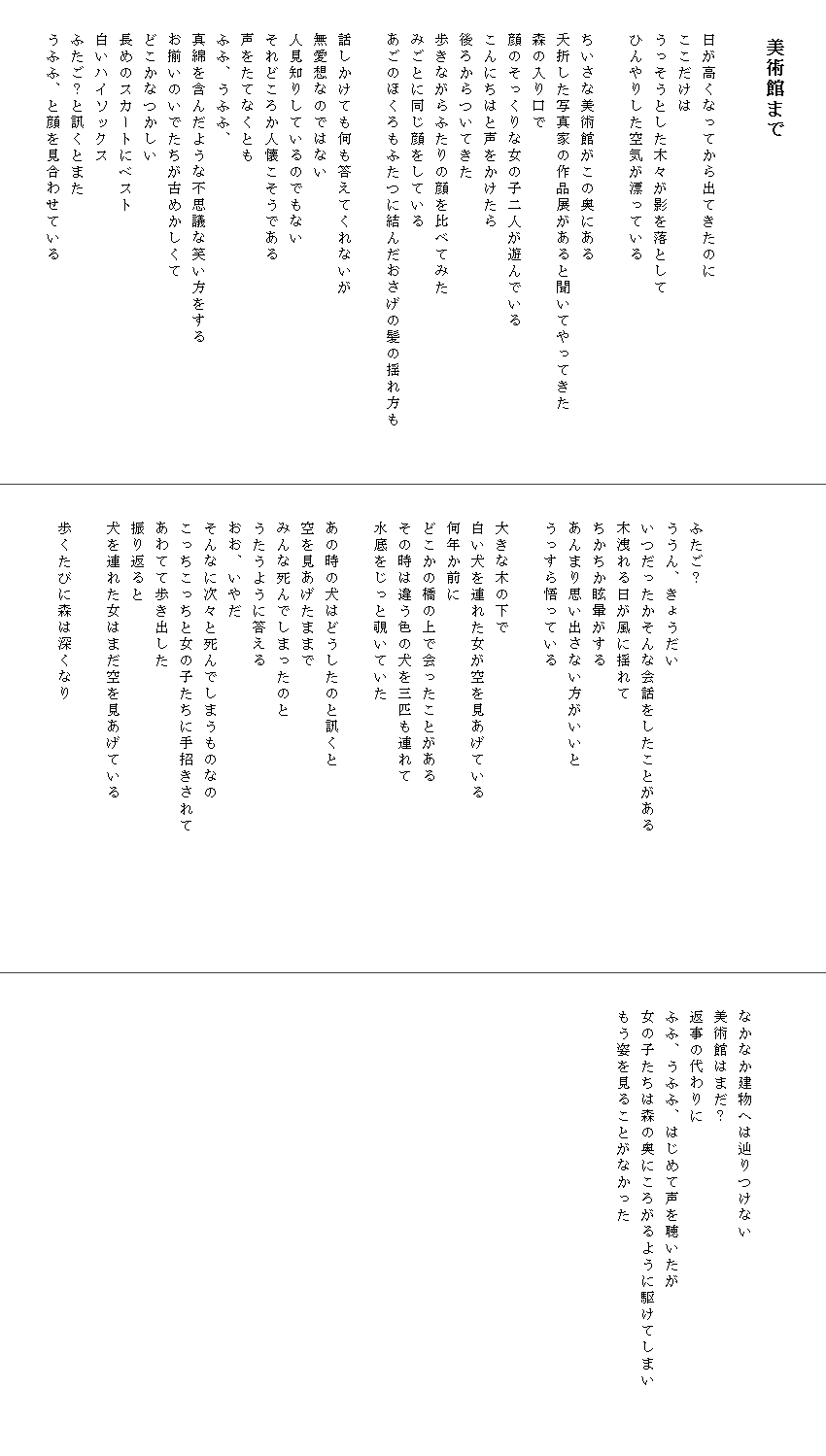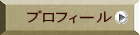

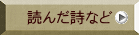
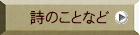
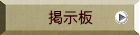
詩誌を読んで〈2014〉 その3
『E 詩』第25号(2014年9月1日発行)
『E 詩』第25号を読んだ。詩は、安達和明「指先」「遺書」、阿部栄子「ほたるの里」、いとう柚子「器」「梅雨冷え」、細矢利三郎「水仙からめ」、福岡俊一「桜」「フォスター讃」、芝春也「土鳩」。エッセイは、いとう柚子「喪の場で朗読された詩」、芝春也「ぽえ爺随考録① 詩の原理を求めて」。「アフォリズム」として、いであつし「百馬鹿の柵 ①」が載っている。
私が最も惹かれたのは、安達和明の2篇の詩。次に、紹介したい。
「指先」は、「赤ん坊」の「白い指先」を「植物の成長点」とみるまなざしが印象的。「月の光に」から「白い指先」まで、一文でつながる伸びやかな文体それ自体
が、「柔らかく 勢いよく伸びる」成長の実感を感じさせる。「闇の隙間に根を伸ばす」は、「闇」におおわれやすい世界にあって、新しい命の成長こそが希望であるという、世界観をも思わせる表現。「闇の隙間」は、“月の光に照らされているようすを表す比喩でもある”と読んだが、適切だろうか。
「遺書」は、本が好きな一人の女性が別の世界に行ってしまった、そのかなしみのこもった詩。本棚を「美しい遺書」とする、一行目の比喩に、まず惹かれる。「本は海/本は森/本は路地裏/本は過去と未来を彷徨う魔法」という「君」のことばが、“私たちにとって本とはどういうものか”という問いに対する答えを、ありきたりでない深いレベルで、みごとに捉え、魅力的に表現している。「そう言って/君は一冊の本を手に取った/そしてその本棚の隙間から/君は旅立った」は、本が好きな女性が別の世界に行ってしまったことを、単に“述べる・語る・伝える”だけでなく、“イメージを通して、実感させる”表現になっている。こういう表現を、“詩的表現”と言うのだろうと、私は考える。
第二連。「風」は、第一連で表現された、「君」が「一冊の本を手に取った」その「本棚の隙間」から吹いてくるのだろう。そのことによって、「風」は自然に「君」を思い出させることになる。
第三連。「すべて世は事もなし」「ケセラセラ」のことばが、“個人的な思い込み“や“個人の信条”とは異なるレベルで、説得力をもって、それこそ心に風が吹き込むように、読む者に受け入れられる。その理由は、ここでは、それらのことばが“「本」のもつ価値に裏付けられ”ており、“「本」の側からこの世の中の出来事を見れば”という前提をもっているからだろう、と思う。
芝春也の詩「土鳩」は、“「生きる」ことを励ます力をもった”詩だ(芝の詩については、前にも同様の表現を使った。参照:
詩誌を読んで〈2013〉、詩「雪を掘る」)。
「ドバト」は、「レースから離脱」し(=競争から離脱し、期待された役割を果たしきれずに)、「もう使いものにならない」と判断されたもの。しかし、一方では、生きる環境の厳しさと引き替えるようにして、自然の中で自由に生き、飛翔することを得たもの。詩を書いている人間で、そうした意味での「ドバト」の自覚と無縁な人がどれだけいるだろうか。
終わりの二つの連が、「ドバト」に対する共感を、さりげなく表していると、私は読んだ。
いとう柚子のエッセイ「喪の場で朗読された詩」は、「88歳で亡くなられたAさん」という「日本画家」の女性の葬儀で、喪主である「弟のK氏」が、茨木のり子の詩「私が一番きれいだったとき」を朗読したエピソードを紹介している。「〈そんなばかなことってあるものか〉(第5連)という1行には、何万人ものAさんの悲しみや怒りや無念がひそんでいて、あるときは叫びとなって、またあるときは呟きや呻きとなって、聞こえてきそうである」。印象に残るエピソードである。“不特定多数のひとによって共有されることば”という性質は、優れた詩のことばに共通するものではないだろうか、と思う。
芝のエッセイ「ぽえ爺随考録① 詩の原理を求めて」も興味深く読んだ。芝は、「詩の本質」としての「ポエジイ」について、述べている。「詩は、感情であったり思考であったり、認識であったり思想であったりもする。しかし、詩のエッセンスあるいは詩の本質(ポエジイ)というのは、それらのいずれでもない。それらの中に生じる電流のようなものだ。」「詩は言葉の電流体である。ポエジイとはその詩的電流のことだ。詩的電流は読む人の内面を刺激し、活性化して、生命を励ますはたらきをする。それが詩の効用というものだろう」。なるほどと思い、「ポエジイ」についてそういう捉え方をしている人だから、芝の詩には「ポエジイ」があるのだろう、と思った。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)
『個人通信 萌』第41号(2014.夏の号)、『きょうは詩人』第27号(2014年4月19日発行)
『個人通信 萌』第41号では、伊藤啓子の詩「美術館まで」「ことり屋界隈」を読むことができる。
『きょうは詩人』第27号では、詩は、苅田日出美「ゆりかもめ もめるかもめ」「エスカルゴロゴロ」、長嶋南子「猫1 大風が吹き荒れた夜」「猫2 ことのてん末」、鈴木芳子「嘘のように」、伊藤啓子「インカのめざめ」、福間明子「ノンフィニート」「会話」、吉井淑「いもうと」「時間隧道」、万亀佳子「仏師」、小柳玲子「ロンゴ坂下駅」、古谷鏡子「かげ 踏んじゃった」を、エッセイは、万亀佳子「広部英一に寄せて」を、読むことができる。
次に、伊藤啓子の詩「美術館まで」を紹介したい。
「森」にモチーフ(の一つ)を得た伊藤の詩は、これまでにもあった。『きょうは詩人』第25号に載る詩「捨て子」、『きょうは詩人』第26号に載る詩「秋の幻燈」が、それである(参照:「
詩誌を読んで〈2014〉」)。三つの詩は、どれも魅力である。どれも、「森の深さ・神秘性・異界性」を捉えてみごとに表現している。
この「美術館まで」は、「森の深さ・神秘性・異界性」それ自体を主題としている点で、詩「捨て子」と共通している、と言ってよいのではないだろうか。ただし、主題は同じでも、「表現」はまったく異なる。
第一連。以前にも伊藤の詩について、同様のことを述べたが、伊藤の詩のことばは「(散文的な)説明」にならない(参照:「
詩誌を読んで〈2013〉」)。この第一連もそうである。「実感を伝える、イメージ」として成り立っている。
第二連。「顔のそっくりな女の子二人」が登場する。詩を最後まで読めばはっきりすることだが、「女の子二人」は、森の精霊とも、何らかの理由で森と一つになった霊的な存在ともとれる、いずれにせよ、森と一つになって森の異界性を表す存在である。
この「女の子二人」に、“現実性(=「詩的リアリティ」とでも言うべきもの。それは、はじめから「虚構」として受け入れられる小説におけるリアリティとは異なる)”をもたせることができるかどうかが、この詩の、詩としての成立の可否に決定的にかかわる鍵だったと考える。それができれば、この詩は、「森の深さ・神秘性・異界性」を表現した詩として成立するし、できなければ、「物語」ではあっても「詩」とは言えないものになっただろう。それができている、と私は考える。
第三連と第四連の表現が、「女の子二人」に、“現実性”をもたせている。特に、第四連(「ふたご?/ううん、きょうだい/…」の連)が、“現実性”をもたせるという点で、実に効果的だ。
第五連と第六連は、「白い犬を連れた女」に関するエピソードであり、そのエピソードは、「女の子二人」とともに、森の異界性を―このエピソードでは、まるで、森が“異なる時間(それも、死と深くかかわっている時間)が入りこんでくる場所”であるかのように―、表現している。それと同時に、この二つの連は、「女の子二人」の“現実性”を、いわば“補強する”役割を果たしている、と私は考える。
最終連は、「建物」に辿りつくことができるのかどうか、不安になるような、「森の深さ」を表現して、終わっている。
さて、では、上で述べた「詩的リアリティ」とは、どういうものだろうか。
理論的に述べることは、たいへん難儀なことである(すでに、誰かがどこかで述べているかもしれないけれども)。しかし、その本質をみごとに表現したことばが、いま、手もとにある。谷川俊太郎の詩集『ミライノコドモ』(岩波書店、2013年6月5日発行)の帯に記された、おそらくは谷川自身のことば。
「物語には終わりがあるが詩に終わりはない」(詩集『ミライノコドモ』の帯より)
「物語には終わりがある」。なるほど、と思う。「物語」は、一つの自己完結した虚構世界を作りあげる。「物語」を夢中になって読んでいるとき、読者は、その虚構世界の中に入り込んでいる。そして、「物語」を読み終えたときには、その世界がどんなに魅力的なものであっても、そこから出て、自分にとっての「現実の世界」にもどることになる。もちろん、「物語」を読んだ結果として、読み終えたあとに、「現実の世界」を生きる上での世界観や人生観、価値観、あるいは、“世界の感触”とでも言うべきものが、変わっているということはあるだろう。しかし、「物語」の世界は、あくまで自己完結した虚構の世界であり、「現実の世界」とは厳密に区別される。
一方、詩のことばは、「現実の世界」に入り込む。たしかに、詩においても、一つの世界が表現されるが、その世界は、“現実の世界の中に見出すことができる“”ものだ。あるいは、「現実の世界」を生きていくとき、自分の“現実の体験の中で文脈を得る”ことができることばだ。三好達治の詩でも、中原中也の詩でも、吉野弘の詩でも、茨木のり子の詩でも、谷川俊太郎の詩でも、そうである。「詩に終わりはない」。なるほど、と思う。
その詩が「詩的リアリティ」をもっているとき、そのことばに「終わりはない」。
伊藤の詩も、「現実の世界」における「森の深さ・神秘性・異界性」を表現していて、「終わりはない」ものになっている。
(以上、敬称や敬語表現を省略させていただきました。)